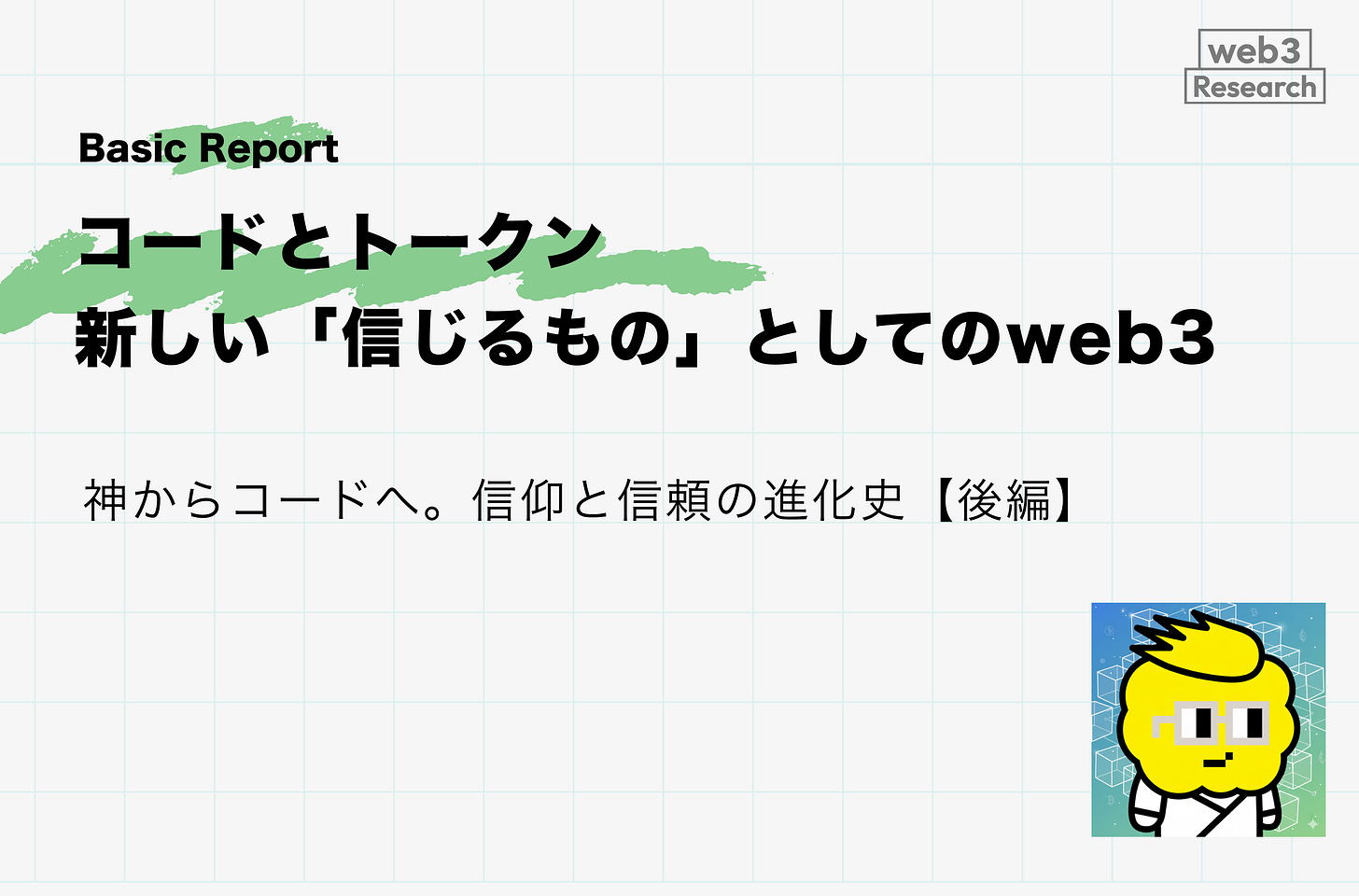おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎レポートを更新しています。今週は「神からコードへ。信仰と信頼の進化史」という少し抽象的ですが、人類が信じてきたものについて解説します。ぜひ最後までご覧ください!
1. 前編の振り返り
2. プラットフォームへの信頼とその限界
3. コードは法である ― ブロックチェーンの哲学
4. トークンと共同幻想
5. 信じるものの未来 ― web3が示す方向性
6. 結論
1. 前編の振り返り
前編では、人類が大規模な社会を維持するために不可欠な「信頼」の対象が、歴史と共にどのように移り変わってきたのかを辿りました。
前編の振り返り
太古の昔、私たちの祖先は「神」という絶対的な権威を信じることで、共同体の秩序を維持しました。近代に入ると、信頼の対象は「神」から「法」へと移行しました。人間が定めたルールと、国家という制度的装置によって信頼を担保する「法の支配」が確立されました。そして現代、グローバル化と資本主義の進展に伴い、「市場」への信頼が社会の基盤となりました。
神、法、市場。これらは形こそ違えど、いずれも人類が社会を維持するために生み出した「信頼の装置」であり、私たちが共有する「共同幻想」でした。
では、21世紀のインターネット時代、人々は何を信じるのか?
そして今、私たちは21世紀のインターネット時代を生きています。この新しい時代において、私たちは何を信じ、どのように信頼を築いているのでしょうか。
デジタル化された社会においては、新しい形の「信頼の仲介者」が登場しています。それが、GAFAMに代表される巨大なプラットフォーム企業です。
私たちは、彼らが提供するサービスを日々利用し、彼らが作り上げたデジタル空間の秩序を当然のように受け入れています。しかし、この新しい「信頼」の形は、かつてないほどの脆さと危険性を孕んでいます。
後編では、まず現代社会が依拠しているプラットフォームへの信頼とその限界を明らかにし、その上で、新しい「信じるもの」として登場した「コード」と「トークン」、すなわちweb3の思想とその可能性について考察していきます。
2. プラットフォームへの信頼とその限界
インターネットの普及、特に2000年代半ば以降の「Web2.0」の時代は、インターネットが社会の基盤として不可欠なものとなった時代です。しかし、このWeb2.0の世界は、少数の巨大プラットフォーム企業によって支配される中央集権的な構造を持っていました。
Web2の秩序:「GoogleやAmazonが保証するサービス」への依存。
私たちは日常生活の中で、無意識のうちにプラットフォーム企業を深く信頼しています。
例えば、何かを知りたいとき、私たちはGoogleで検索し、検索結果の上位に表示された情報が正しいものであると信じます。Googleのアルゴリズムが、信頼できる情報源を選別してくれていると信じているからです。
オンラインで買い物をするとき、私たちはAmazonを利用し、商品が確実に届き、決済が安全に行われると信じます。Amazonというプラットフォームが、取引の安全性を保証してくれていると信じているからです。
このように、Web2.0の世界において、プラットフォーム企業は「信頼の仲介者」として機能しています。私たちは、プラットフォーム企業という中央集権的な管理者を信頼することによって、間接的にデジタル空間全体の秩序と安全性を信じているのです。
この構造は、非常に効率的で便利なものです。プラットフォーム企業がサーバーを管理し、サービスを開発・運営することで、私たちは無料で(あるいは安価で)高度なサービスを享受できるようになったのです。インターネットがこれほどまでに急速に普及したのは、間違いなく彼らの功績です。
しかし、この中央集権的な信頼モデルは、重大な問題を孕んでいます。
中央集権型の問題:検閲、アカウント凍結、企業倒産リスク。
プラットフォーム企業への信頼は、彼らが善良で公正な存在であり続けるという前提に基づいています。しかし、現実は必ずしもそうではありません。権力が一箇所に集中するとき、そこには常に濫用のリスクが伴います。
第一に、「検閲と情報操作のリスク」です。プラットフォーム企業は、デジタル空間における情報の流通をコントロールする絶大な力を持っています。彼らは、自らの判断で特定のコンテンツを削除したり、表示順位を操作したりすることができます。
もちろん、違法なコンテンツやフェイクニュースを取り締まることは必要ですが、その判断基準は企業の恣意的なものになりがちです。プラットフォーム企業のポリシーやアルゴリズムは不透明であり、その判断が常に公正であるとは限りません。少数の民間企業が情報の門番(ゲートキーパー)として振る舞うことの危険性は、民主主義に対する脅威となり得ます。
第二に、「アカウント凍結とデジタルアイデンティティの喪失」のリスクです。プラットフォーム企業の規約に違反したと判断されれば、アカウントを突然凍結(BAN)されたり、削除されたりするリスクがあります。
現代において、SNSのアカウントやメールアドレスは、私たちのデジタルなアイデンティティそのものです。長年かけて築き上げてきた関係やデータすべてが、プラットフォーム企業の一方的な判断によって、一夜にして失われてしまう可能性があるのです。
第三に、「企業倒産とサービス停止のリスク(単一障害点)」です。プラットフォーム企業もまた、永遠の存在ではありません。企業の倒産や経営方針の転換によって、サービスが突然停止するリスクがあります。中央集権的なシステムは、中心点が崩壊すれば、システム全体が機能不全に陥るという構造的な脆弱性を抱えているのです。
「信じられないはずのもの」を信じる脆さ。
プラットフォームへの信頼が抱える根本的な問題は、それが「属人的な信頼」であるということです。私たちは、プラットフォーム企業の経営者や従業員、あるいは彼らが設計した不透明なアルゴリズムを信じるしかありません。
しかし、歴史を振り返れば、権力は必ず腐敗するものであり、人間は常に間違いを犯すものです。企業は利益を追求する存在であり、公共の利益よりも自社の利益を優先するのが当然です。
にもかかわらず、私たちは、これほどまでに重要な社会基盤を、少数の民間企業の手に委ねてしまっています。これは、本来「信じるにはあまりにも危ういもの」を、利便性と引き換えに信じ込もうとしている状態と言えるかもしれません。
さらに深刻な問題は、私たちが自らのデータに対する主権を失っていることです(データ主権の喪失)。Web2.0の世界では、私たちが生み出す膨大なデータは、プラットフォーム企業によって収集・分析され、広告ビジネスなどの収益源として利用されています。私たちは、自分のデータがどのように使われているのかを完全にコントロールすることはできません。
Web2.0がもたらした中央集権的な信頼モデルは、効率性と利便性をもたらした一方で、権力の集中、透明性の欠如、データ主権の喪失といった深刻な問題を生み出しました。
だからこそ今、信頼の構造そのものを再設計しようとする動きが生まれています。特定の管理者に依存するのではなく、テクノロジーの力によって、より透明で、公平で、分散化された信頼の仕組みを構築しようとする試み。それが、「コード」を信じるという思想、すなわちweb3の挑戦なのです。
3. コードは法である ― ブロックチェーンの哲学
Web2.0の限界を乗り越えるために登場したweb3の思想。その中核にあるのは、「人」や「組織」ではなく、「コード(プログラム)」を信頼の拠り所とするという考え方です。
ローレンス・レッシグの「Code is Law」の概念。
「コードへの信頼」という思想を理解する上で重要な概念が、アメリカの法学者ローレンス・レッシグが1999年に提唱した「Code is Law(コードは法である)」という言葉です。
レッシグは、社会における人々の行動を規制する力として、従来の「法」「規範」「市場」に加えて、第四の力として「アーキテクチャ(構造)」が存在すると指摘しました。そして、インターネットというデジタル空間においては、この「アーキテクチャ」の役割を果たすのが「コード」であると主張しました。
プログラムコードは、デジタル空間の物理法則であり、私たちがそこで何ができて何ができないかを決定します。「Code is Law」という言葉は、コードが法律と同じように、あるいはそれ以上に強力な規制力を持つことを示唆しています。法律は破られる可能性がありますが、適切に設計されたコードは破ることが困難です。コードによって定められたルールは、自動的に、そして強制的に執行されます。そこには、人間の恣意的な解釈や例外は存在しません。
Web2.0の世界においても、プラットフォーム企業はコードによってルールを定めていました。しかし、そのコードは不透明であり、管理者によっていつでも変更可能でした。
web3は、この「Code is Law」の思想を、逆説的に利用しようとします。すなわち、透明で、誰にも改竄できないコードによってルールを定めることで、中央集権的な管理者を排除し、真に自由で公平なデジタル社会を実現しようとするのです。
スマートコントラクト=破れない約束、透明なルール。
web3において「Code is Law」を体現する技術が、「スマートコントラクト」です。スマートコントラクトとは、ブロックチェーン上で実行されるプログラムであり、あらかじめ定められた条件が満たされると、自動的に契約内容を実行する仕組みです。
従来の契約は、法律に基づいて行われます。もし契約が破られれば、裁判所に訴えて強制執行を求める必要があり、時間とコストがかかります。
一方、スマートコントラクトは、コードによって契約内容が記述され、その実行はブロックチェーンネットワークによって保証されます。
例えば、「AさんがBさんに1ETHを送金したら、Bさんが所有するデジタルアート(NFT)の所有権をAさんに移転する」という契約をスマートコントラクトで記述したとします。Aさんが送金を行うと、その事実がブロックチェーンに記録され、スマートコントラクトが自動的に実行されます。そして、NFTの所有権がAさんに移転します。
このプロセスには、第三者の仲介は必要ありません。契約の実行は、コードに従って自動的に行われるため、契約不履行のリスクはありません。スマートコントラクトは、まさに「破れない約束」を実現する技術です。
スマートコントラクトのもう一つの重要な特徴は、その透明性と改竄不可能性です。
ブロックチェーン上にデプロイされたスマートコントラクトのコードは、原則として誰でも閲覧することができます。どのようなルールに基づいて動作するのかが、すべての人に公開されているのです。
また、一度ブロックチェーンに記録されたスマートコントラクトは、後から改竄することが極めて困難です。ブロックチェーンは、世界中の多数の参加者によって分散的に管理されている「分散型台帳」であるため、一部の管理者が不正を働いたり、ルールを恣意的に変更したりすることはできません。
この透明性と改竄不可能性によって、スマートコントラクトは、中央集権的な管理者がいなくても、公正で信頼できるルールを実現することができるのです。
コードに「信じる」を預けるとはどういうことか。
web3が目指すのは、「トラストレス」なシステムの実現です。これは、「信頼が不要」という意味ではありません。「特定の誰か(個人や組織)を信頼する必要がない」という意味です。
Web2.0の世界では、私たちはプラットフォーム企業を信頼する必要がありました。しかし、web3の世界では、私たちは「コード」と、それを支える「ブロックチェーンネットワーク全体の合意形成システム(コンセンサスアルゴリズム)」を信頼すればよいのです。
web3の世界では、「In God We Trust(我々は神を信じる)」をもじって、「In Code We Trust(我々はコードを信じる)」と言われることがあります。
これは、盲目的にテクノロジーを信奉するということではありません。web3の重要な特徴は、「検証可能性」です。ブロックチェーン上のデータやスマートコントラクトのコードは、原則として誰でも閲覧・検証することができます。
私たちは、特定の企業や管理者の「意図」を信じる必要はありません。その代わりに、公開されているコードを読み解き、そのシステムがどのように機能するのかを自ら検証することができるのです。もちろん、すべての人がコードを読めるわけではありませんが、専門家やコミュニティによる監査が行われることで、システムの透明性と信頼性が担保されます。
「信じるな、検証せよ(Don't Trust, Verify)」。これこそが、web3の基本的なスタンスです。
「コードを信じる」という態度は、人間の不完全性に対する深い洞察に基づいています。人間は間違いを犯し、欲望に流され、権力を濫用する存在である。だからこそ、重要なルールは、人間の手を離れた、透明で強制力のあるコードに委ねるべきだ。これが、web3の根底にある哲学なのです。
4. トークンと共同幻想
ブロックチェーン技術は、トラストレスなシステムを実現するための基盤を提供しました。しかし、それだけでは、人々が参加し、協力し合う動機は生まれません。web3が新しい社会システムとして機能するためには、人々を結びつけ、価値を共有するための新しい「信仰装置」が必要です。それが「トークン」です。
トークン=価値を共有するための新しい信仰装置。
トークンとは、ブロックチェーン上で発行されるデジタルな権利証や引換券のようなものです。暗号資産もトークンの一種ですが、それだけではありません。株式、会員権、投票権、デジタルアート(NFT)など、あらゆる「価値」をトークン化することができます。
トークンの重要な役割は、これまで可視化・移転が困難だった価値をデジタル化し、インターネット上で自由に取引できるようにすることです。これにより、新しい経済圏、「トークンエコノミー」が誕生します。
しかし、トークンの本質的な機能は、それ以上に「共通の信仰」を生み出すことにあります。トークンは、特定の価値観や目的に対する「信仰」を表明し、その信仰に基づいて行動を促すための強力なツールなのです。
トークンが優れている点は、共同体の維持・発展に貢献した人に対して、適切なインセンティブを与える仕組みを設計できることです。
ビットコインのマイニングはその典型例です。マイナーは、ネットワークのセキュリティ維持に貢献することで、報酬として新規発行されるビットコインを受け取ります。これは、個人の利益追求(ビットコインを得ること)が、そのまま全体の利益(ネットワークの維持)に繋がる、非常によくできた仕組みです。
Web2.0のプラットフォームでは、ユーザーがコンテンツを投稿してネットワークの価値を高めても、その利益の大部分はプラットフォーム企業に吸収されていました。
しかし、web3のプロジェクトでは、初期の段階から貢献してくれたユーザーに対してトークンを配布することで、その貢献に報いることができます。ユーザーは単なる顧客ではなく、トークンを保有することで、そのプロジェクトの「共同所有者」となります。トークンの価値が上がれば自分も利益を得られるため、プロジェクトの成長に積極的に関わろうという動機が生まれます。
このように、トークンは、見知らぬ人々が共通の目的のために協力し合うことを可能にする、強力な調整メカニズムとして機能します。
貨幣や国家と同じく、トークンも「共同幻想」で支えられる。
前編で述べたように、貨幣は「皆がそれを価値あるものとして信じる」ことによって機能する共同幻想です。国家が発行する法定通貨は、国家への信頼によってその価値が担保されています。
では、トークンの価値は何によって担保されるのでしょうか。ビットコインのように明確な発行主体が存在しない場合、その価値を保証してくれる中央銀行は存在しません。
トークンの価値もまた、それを信じる人々の「共同幻想」によって支えられています。例えば、ビットコインの場合、「発行上限が2100万枚とプログラムで決められている」「非中央集権的で検閲耐性がある」「デジタル・ゴールドとしての価値保存手段になる」といった「物語(ナラティブ)」を信じる人々がいるからこそ、価格が形成されます。
これらの物語は、単なる思い込みではありません。コードによって裏付けられた客観的な事実(発行上限や技術的特性)と、将来への期待(利用の拡大や社会実装)が組み合わさって形成されます。そして、その物語に共感し、信じる人が増えれば増えるほど、トークンの価値は高まり、その共同幻想はより強固なものになっていくのです。
もちろん、トークンに基づく共同幻想には危うさも伴います。過剰な期待が先行し、実態が伴わないまま価格が高騰するバブルが発生しやすい傾向があります。詐欺的なプロジェクトや、ハッキング事件も後を絶ちません。
しかし、これは神話や国家が形成される過程でも同じでした。多くの試行錯誤を経て、より強固で信頼できる物語だけが生き残っていくのです。web3は、この共同幻想を、よりオープンで、透明で、民主的な方法で作り上げる可能性を秘めています。
DAOが作る新しい共同体のかたち。
トークンとスマートコントラクトを組み合わせることで、全く新しい組織形態、「DAO」が誕生しました。
DAOは、特定の経営者や取締役会を持たず、参加者が共同で所有・管理する組織です。組織の運営ルールはスマートコントラクト(コード)によって定められ、意思決定はトークン保有者による投票(ガバナンス投票)によって行われます。
株式会社では、株主が経営者を任命し、経営者が従業員を指揮命令するという階層構造になっています。しかし、DAOはフラットな構造を持ち、参加者が自律的に活動します。貢献に対する報酬も、コードによって自動的に分配されます。
DAOは、国家や企業といった従来の共同体とは異なる、より民主的で透明性の高い組織運営の可能性を示しています。共通の目的(例えば、特定のプロトコル開発、投資、慈善活動など)のために世界中の人々が集まり、協力し合う。これは、インターネット時代における新しい「共同体」の形と言えるでしょう。
私たちは、生まれた場所によって自動的に属する国家を選ぶことはできませんでしたが、自らの価値観に基づいて属するDAOを選ぶことができるようになるかもしれません。トークンは、この新しい「くに」を支える「信仰」の装置であり、DAOは、その信仰を実践するための「共同体」の形です。
5. 信じるものの未来 ― web3が示す方向性
神から法へ、法から市場へ、そして市場からコードへ。人類の「信じるもの」の歴史は、絶え間ない進化のプロセスでした。web3は、この歴史の最先端に位置する、新しい信頼の形を提示しています。しかし、それは決して万能な解決策ではありません。
神や法や市場と同じく、web3も「絶対ではない」。
まず認識しなければならないのは、web3もまた、完璧なシステムではないということです。神、法、市場がそれぞれ限界と課題を抱えていたように、web3にも乗り越えるべき課題が多く存在します。
第一に、技術的な課題です。ブロックチェーンは、「スケーラビリティ問題」を抱えています。社会基盤として広く普及するためには、さらなる技術革新が必要です。
第二に、コードの脆弱性とハッキングリスクです。「Code is Law」の思想は、コードの完璧性を前提としていますが、コードを書くのは人間である以上、バグや設計ミスが存在する可能性があります。コードに絶対的な信頼を置くことの危険性も認識しなければなりません。
第三に、参加の障壁とデジタルデバイドです。web3のサービスを利用するためには、ウォレットの設定や秘密鍵の管理など、専門的な知識が必要となります。一般の人々が当たり前に使えるようになるためには、UXの向上が不可欠です。
第四に、法規制との摩擦です。非中央集権的なシステムは、既存の法律や規制の枠組みに収まらない側面があります。イノベーションを阻害することなく、利用者を保護するための適切な規制のあり方が模索されています。
web3は、これらの課題を一つずつ解決していくことによって、初めて社会に広く受け入れられていくでしょう。私たちは、web3を過度に理想化することなく、その可能性と限界を冷静に見極める必要があります。
しかし、透明性・分散性・コードによる実行という点で新しい地平を切り拓く。
多くの課題があるにもかかわらず、web3が提示する方向性は、私たちがこれまで築き上げてきた信頼のあり方を根本から変える可能性を秘めています。その核心は、「透明性」「分散性」「コードによる実行」という三つの要素にあります。
透明性: すべての取引履歴とコードが公開され、誰でも検証可能です。これにより、権力の濫用や不正行為を防ぐことができます。Web2.0のプラットフォームのようなアルゴリズムのブラックボックス化は起こり得ません。「Don't Trust, Verify(信頼するな、検証せよ)」の精神です。
分散性: 特定の管理者に依存せず、参加者全員でシステムを維持します。これにより、検閲耐性が高まり、システムダウンのリスクが低減されます。また、データの主権がユーザーの手に戻ります(自己主権性)。
コードによる実行: スマートコントラクトによって契約が自動執行され、第三者の介入を必要としません。これにより、人間の恣意性を排除し、効率的で摩擦のない取引が可能になります。
これらの特徴は、私たちが直面している現代社会の課題、特に権力の集中や信頼の危機に対する、一つの有効な解法となりうるのです。
「信じるものを選べる時代」における人類の挑戦。
web3の登場は、私たちが「何を信じるか」を選ぶことができる時代が到来したことを意味します。
これまでは、私たちは生まれた場所によって自動的に属する国家や、社会的に定められた法や市場システムを、選択の余地なく受け入れるしかありませんでした。
しかし、web3の世界では、様々な価値観やルールに基づいて設計された多様なシステム(プロトコル、DAO、トークンエコノミーなど)が並列的に存在します。私たちは、自らの価値観に最も合致するシステムを選び、自由に参加・脱退することができます。
もちろん、web3が既存のシステムを完全に置き換えるわけではないでしょう。国家や法律、市場は今後も重要な役割を果たし続けるはずです。web3は、それらを補完し、時には競争を促すことで、既存のシステムに変革を迫る存在となるでしょう。私たちは、中央集権的なシステムと分散型システムを、目的に応じて使い分ける時代を生きていくことになります。
この「信じるものを選べる」時代は、私たち一人ひとりに、自らの価値観に基づいて社会を選択し、創造していく主体性を与えてくれます。しかし同時に、それは私たちに重い責任を課すことにもなります。
何を信じるべきか、どのシステムに参加すべきか、自らの頭で考え、判断しなければなりません。リテラシーを高め、リスクを理解し、自らの選択の結果に責任を持たなければなりません。
web3は、人類が自らの社会のあり方を自らデザインするための強力なツールを与えてくれました。このツールをどう使いこなすかは、私たち自身の手に委ねられているのです。これは、人類にとっての新たな挑戦と言えるでしょう。
6. 結論
本連載「神からコードへ:信仰と信頼の進化史」では、人類が「信じてきたもの」の歴史を辿りながら、web3の本質に迫ってきました。
web3は宗教や国家に匹敵する「新しい信仰システム」になりうる。
人類社会は常に、人々が共有する「共同幻想」を信じることによって成立してきました。その対象は、時代とともに「神」から「法」へ、そして「市場」へと移り変わってきました。これらのシステムは、それぞれが社会秩序を維持するための「信頼のOS」として機能してきましたが、同時に限界も抱えていました。
そして今、インターネット時代の新たな信頼の形として「コード」が登場しました。ブロックチェーン技術を基盤とするweb3は、中央集権的な管理者を必要としない、トラストレスなシステムを実現します。スマートコントラクトは「Code is Law」を体現し、トークンは価値を共有するための新しい「信仰装置」として機能します。
web3は、単なる技術革新ではありません。それは、社会の「信頼」のあり方そのものを再定義しようとする、思想的なムーブメントです。web3は、宗教改革や近代国家の成立に匹敵する、新しい「信仰システム」として社会に根付く可能性を秘めています。
神からコードへ――これは「信頼の民主化」とも呼べる歴史の転換点である。
「神からコードへ」という流れは、信頼の主体が中央集権的な権威(神、国家、プラットフォーム企業)から、分散化されたプロトコル(コード、コミュニティ)へと移行する、歴史的な転換点を意味します。
これは、「信頼の民主化」とも呼べる変化です。私たちは、特定の権威に盲目的に従うのではなく、自ら検証し、何を信じるかを選択できる時代を迎えようとしています。
web3はまだ黎明期にあり、多くの課題を抱えています。しかし、その根底にある透明性、分散性、自律性という価値は、私たちが長年求めてきた、より自由で、より公平な社会を実現する可能性を秘めています。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら