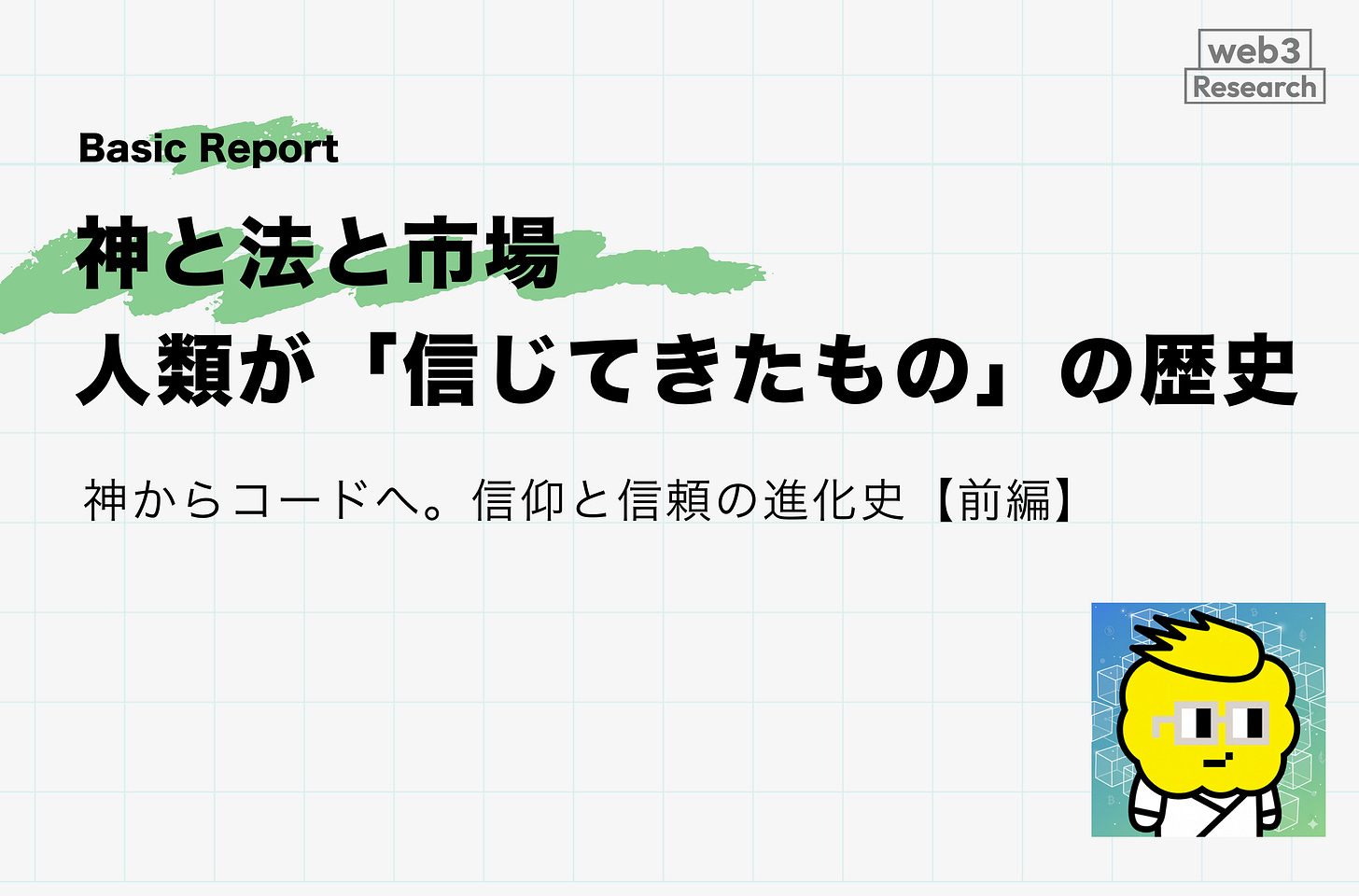おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎レポートを更新しています。今週は「神からコードへ。信仰と信頼の進化史」という少し抽象的ですが、人類が信じてきたものについて解説します。ぜひ最後までご覧ください!
1. はじめに
2. 神への信仰 ― 絶対的権威
3. 法の支配 ― 神から人間へ
4. 市場への信頼 ― 見えざる手
5. まとめ
1. はじめに
私たちの社会は、見知らぬ他人同士が協力し合うことによって成り立っています。朝、コンビニでコーヒーを買うとき、私たちは店員がレジを正しく操作することを信じ、支払ったお金が価値を持つことを信じています。電車に乗るときは、運行システムが正常に機能していることを信じています。
しかし、立ち止まって考えてみると、これは驚くべきことではないでしょうか。なぜ私たちは、顔も名前も知らない相手を、あるいは目に見えないシステムを、これほどまでに「信じる」ことができるのでしょう。
記事の狙い:「人はなぜ何かを信じるのか?」という普遍的テーマを軸に、web3の本質に近づく。
この前編後編を通して「神からコードへ:信仰と信頼の進化史」は、この根源的な問い――「人はなぜ何かを信じるのか?」を軸に、人類社会を形づくってきた「信仰」と「信頼」の歴史を紐解き、「web3」本質に迫ることを目的としています。
web3は、ブロックチェーン技術を基盤とした、新しいインターネットのあり方を示す概念です。しばしば「分散型インターネット」とも呼ばれ、特定の企業や政府に依存しない、自律的なデジタル社会の実現を目指しています。しかし、その技術的な側面ばかりが注目されがちで、「なぜ今、それが必要とされているのか」といった、思想的・社会的な背景については、まだ十分に理解されているとは言えません。
web3の中核にあるのは、「トラストレス(Trustless)」という思想です。これは「信頼が不要」という意味ではありません。むしろ、特定の誰か(個人や組織)への属人的な信頼に依存するのではなく、数学的な暗号やプログラムコード、そしてオープンなネットワーク参加者全体の合意形成システムによって、社会の信頼を担保しようとする試みなのです。
この「信頼のあり方を変革する」という視点に立ったとき、web3は単なるテクノロジーの進化ではなく、人類が長大な歴史の中で紡いできた「信じるもの」の系譜の最先端に位置づけられることが見えてきます。
「信仰・信頼」が人類社会を形づくってきた背景を振り返る。
人類が他の動物と決定的に異なる点の一つは、大規模な集団を形成し、柔軟に協力できる能力を持っていることです。進化心理学や文化人類学の研究によれば、この能力の基盤には「何かを共同で信じる力」があるとされています。
例えば、ユヴァル・ノア・ハラリは著書『サピエンス全史』の中で、人類が繁栄できたのは、神話、宗教、国家、貨幣、法律といった「虚構(フィクション)」を信じる能力、すなわち「共同幻想」を持つことができたからだと指摘しました。
「私たちは同じ神を信じている」「私たちは同じ国の国民である」「この紙切れには1万円の価値がある」といった共通の物語を信じることによって、数万人、数億人という規模での協力を可能にしてきました。
この「共同幻想」こそが、本連載で扱う「信仰」や「信頼」の正体です。私たちは社会を維持するために、常に「信じるに足る何か」を必要としてきました。そして、その対象は歴史と共に移り変わってきました。
太古の昔、人々が信じたのは「神」でした。やがて近代に入ると、「法」や「国家」が信頼の対象となりました。そして現代、私たちが最も強く信じているのは「市場」かもしれません。
神、法、市場。これらは形こそ違えど、いずれも人類が社会を維持するために生み出した「信頼の装置」であると言えます。
前編では、まず「神」「法」「市場」という三つの時代を概観し、人類が何を信じ、どのように社会秩序を維持してきたのかを詳しく見ていきます。この歴史的な変遷を知ることで、後編で扱うweb3が、なぜ「新しい信頼の形」として登場したのか、その必然性を深く理解することができるはずです。
2. 神への信仰 ― 絶対的権威
人類史の大部分において、社会秩序の根幹を支えてきたのは「神」への信仰でした。現代の私たちから見ると、宗教は個人的な信条の問題として捉えられがちですが、かつて宗教は、法律であり、政治であり、経済であり、社会のすべてでした。
古代文明における神の存在:宗教と社会秩序の関係。
人類が狩猟採集生活から農耕牧畜生活へと移行し、定住を始めた頃、共同体の規模は飛躍的に拡大しました。血縁や顔見知りの関係を超えた数百人、数千人規模の集団を維持するためには、全員が共有できる強力な物語が必要となりました。それが「神」の誕生です。
古代文明において、神々は自然現象を司り、人々の運命を左右する絶対的な存在として畏怖されました。豊作を祈る儀式、疫病を鎮めるための生贄。これらすべてが神々の意志と結びつけられ、人々の行動規範を規定しました。
古代社会において、宗教施設である神殿は、単なる祈りの場所以上の重要な役割を果たしていました。
第一に、神殿は「富の集積と再分配のセンター」でした。人々は収穫物の一部を神への供物として神殿に納めました。これは現代における税金のような機能を果たします。集められた富は、神官や王の生活を支えるだけでなく、飢饉の際の備蓄や、公共事業の原資として再分配されました。人々は、神への供物が共同体全体の利益のために使われると信じていたからこそ、供物を捧げたのです。
第二に、神殿は「情報の記録と管理のセンター」でした。メソポタミアで発見された最古の文字記録の多くは、神殿に納められた穀物や家畜の数を記録した会計簿でした。誰がどれだけ納めたか、誰にどれだけ貸し付けたかを正確に記録することは、共同体内部の信頼を維持する上で不可欠でした。そして、その記録の正しさを保証したのは、他ならぬ神の権威でした。「神が見ている」からこそ、人々は記録を偽ることができず、約束を守ろうとしたのです。
このように、古代社会における宗教は、現代の政府や銀行、裁判所が果たしているような機能を一手に担っていました。そして、そのすべての中心に「神」という絶対的な信頼のアンカー(錨)が存在していたのです。
王権神授説や宗教裁判など、「神を信じること」が共同体のルールを支えた。
共同体がさらに大規模化し、国家という形態をとるようになると、統治者である王や皇帝は、自らの権力の正当性を神に求めました。これが「王権神授説」の基本的な考え方です。
王は神によって選ばれた特別な存在であり、地上における神の代理人である。このような物語を人々に信じさせることによって、王は絶対的な権力を手にしました。王の命令はすなわち神の命令であり、それに逆らうことは神への冒涜と見なされました。
例えば、古代エジプトのファラオは神として崇拝されました。ヨーロッパの絶対王政においても、国王の権力は神から授けられた神聖不可侵なものであるとされ、教会の権威と結びつくことで強固な支配体制を築きました。
法律や裁判もまた、神の権威によって支えられていました。近代的な法治国家が成立する以前、何が正義で何が悪かを判断する最終的な基準は、神の教え、すなわち宗教的な戒律でした。
有名なハンムラビ法典も、その序文で、太陽神シャマシュからハンムラビ王が法を授けられたと記されています。これは、法が単なる人間の王が決めたルールではなく、「神から与えられた正義の法」であることを宣言することで、人々にその法を遵守させるための強力な正当性を与えたのです。
中世ヨーロッパにおいては、教会法が人々の生活を隅々まで規定していました。争いごとはしばしば宗教裁判によって裁かれ、破門や異端宣告といった罰則が下されました。これらの罰則は、社会的な死をも意味するほど重いものでした。
また、証拠が不十分な場合に行われた「神明裁判」というものもあります。例えば、熱湯の中に手を入れて火傷の治り具合で有罪か無罪かを判断したりするものです。一見すると不合理な方法ですが、当時は「神が正しい者に奇跡を起こし、守ってくださる」と真剣に信じられていました。人々がその結果を受け入れたのは、神の審判という絶対的な権威を信じていたからに他なりません。
このように、「神を信じること」は、共同体のルール(法)を機能させるための大前提でした。神という超越的な存在を設定することで、人々は利害対立を超えた客観的な基準を持つことができ、社会の秩序を維持することができたのです。
神の名において鋳造された貨幣、聖書に基づく誓い。
信仰の力は、政治や法律だけでなく、経済活動の基盤となる「信頼」をも支えていました。貨幣と契約は、その代表例です。
貨幣が価値を持つためには、誰もがその価値を信じている必要があります。歴史的に見ると、貨幣の信用はしばしば神や宗教的権威と結びついていました。
古代のコインには、しばしば神々の肖像や宗教的なシンボルが刻印されました。統治者は、自らの権威と神の権威を結びつけることによって、貨幣の価値を保証しようとしたのです。中世ヨーロッパにおいても、貨幣にはしばしば十字架や聖人の肖像が刻まれました。これは、貨幣の価値が神によって保証されていることを示すシンボルでした。
人々は、貨幣に刻まれた神聖なシンボルを信じることによって、見知らぬ相手との取引を安心して行うことができたのです。
また、経済活動は、契約(約束)が守られるという信頼があって初めて成り立ちます。しかし、強制力を持った近代的な司法制度が存在しない時代において、どうやって契約の履行を保証したのでしょうか。その答えもまた、「神」でした。
古代から中世にかけて、重要な契約はしばしば神殿や教会で行われ、神の名において誓いを立てる形で行われました。キリスト教社会においては、聖書に手を置いて宣誓することが一般的でした。これは、「もし私がこの誓いを破れば、神の罰を受けても構わない」という意思表示です。神の罰は、死後の地獄での永遠の苦しみをも意味するため、信仰心の篤い人々にとっては、この世のいかなる罰則よりも恐ろしいものでした。
この「神が見ている」という感覚、そして「神罰への恐れ」が、契約を守らせる強力なインセンティブとして機能したのです。この内面化された監視の目が、人々の行動を律し、社会全体の信頼を支えていました。
しかし、この「神への信仰」に基づく社会システムは、永遠には続きませんでした。中世から近代にかけて、社会構造の変化や知の進化によって、神の絶対的な権威は揺らぎ始めます。そして人類は、神に代わる新しい「信じるもの」を求めて模索することになります。それが、次に見ていく「法の支配」です。
3. 法の支配 ― 神から人間へ
「神」が絶対的な権威として君臨した時代は長く続きましたが、中世後期から近代にかけて、その権威は徐々に揺らぎ始めます。神の意志ではなく、人間の理性と合意に基づいて社会秩序を築こうとする動きが生まれました。
中世から近代への移行:宗教改革と世俗権力の台頭。
神の権威が揺らぎ始めた大きな要因の一つが、16世紀に始まった宗教改革です。
それまで、西ヨーロッパ世界においては、ローマ教皇を頂点とするカトリック教会が唯一絶対の権威を持っていました。しかし、ルターやカルヴァンといった宗教改革者たちは、教会の腐敗や形骸化を批判し、「信仰の拠り所は教会ではなく、聖書そのものである」と主張しました。グーテンベルクの活版印刷技術によって聖書が広く普及したことも、この動きを後押ししました。
宗教改革は、社会全体に大きな変化をもたらしました。第一に、カトリック教会の絶対的な権威が崩れ、宗教的な権威が分散化しました。唯一の真理を独占する存在がいなくなったことで、人々は自らの頭で考え、判断する必要に迫られました。
第二に、宗教改革に伴う混乱と宗教戦争を経て、人々は宗教的な信念に基づいて争うことの悲惨さを痛感しました。その結果、「宗教的な事柄と政治的な事柄は分離すべきである」という政教分離の考え方が広まりました。
また、17世紀の科学革命も大きな影響を与えました。コペルニクス、ガリレオ、ニュートンといった科学者たちは、観察と実験に基づいて自然界の法則を解き明かしていきました。世界は神の意志によって動いているのではなく、合理的な法則に従って動いているという新しい世界観が生まれたのです。
宗教的な権威が後退する一方で、国王や諸侯といった世俗権力が力を増していきました。彼らは、教会からの独立を目指し、自らの領土内における支配権を強化していきました。こうして、明確な国境を持ち、独立した統治権(主権)を持つ「主権国家」という新しい政治単位が誕生しました。
主権国家は、国内の秩序を維持するために、神に代わる新しい「信じるもの」が必要となりました。それが「法」であり、そして「国家」そのものでした。
ルソーの社会契約論、「人々の合意」に基づく秩序形成。
神の権威が絶対的であった時代、社会の秩序は神によって定められたものであり、人々はそれに従うしかないと考えられていました(王権神授説)。しかし、17世紀から18世紀にかけての啓蒙思想の時代、この考え方は根本から覆されます。その中心となったのが「社会契約論」です。
ホッブズ、ロック、ルソーといった思想家たちは、「そもそも国家や法律はなぜ存在するのか?」という問いに対して、社会契約という概念を用いて答えようとしました。
彼らはまず、国家や法律が存在しない状態、すなわち「自然状態」を想定しました。そして、この自然状態の不都合から逃れるために、人々は自らの自由や権利の一部を自発的に譲り渡し、共通の権力(政府や国家)を設立する契約を結ぶと考えたのです。
この思想の革新的な点は、国家や法律の根拠を、神の命令や伝統ではなく、「人々の合意」に求めたことです。社会秩序は天から与えられるものではなく、自由で平等な個人が自らの意志で作り上げるものである、という考え方への大転換でした。
特にルソーは『社会契約論』の中で、社会契約によって設立された国家は、「一般意志」と呼ばれる、公共の利益を目指す共同体全体の意志に基づいて統治されるべきであると主張しました。そして、法律とは、この一般意志の表明であるとされました。
人々が法律に従うのは、それが神の命令だからでも、王の命令だからでもありません。自分たちが自ら定めたルールだからこそ、それに従う義務があるのです。これが「法の支配」の基本的な考え方です。
社会契約論は、あくまで思考実験であり、歴史的な事実ではありません。しかし、この強力な物語は、人々の意識を大きく変えました。「私たちは契約によって結ばれた平等な市民である」という共同幻想が生まれたことで、近代的な国民国家が成立する基盤が築かれたのです。
国家と法律の登場 → 信じる対象は「神」から「制度・法」へ。
社会契約論という思想的な裏付けを得て、近代国家は「法」を社会秩序の基盤として整備していきました。この流れは、アメリカ独立革命やフランス革命といった市民革命を経て、確固たるものとなりました。
その象徴が「憲法」です。憲法は、国家の基本的な枠組みを定め、国民の権利を保障し、権力の乱用を防ぐための最高法規です。人々は、憲法という文書化されたルールを信じることによって、国家権力が恣意的に行使されることを防ぎ、自らの自由と安全を守ることができると考えました。
法が成文化されたことによって、誰が読んでも同じように解釈できる客観的なルールが確立されました。これにより、人々の行動の予測可能性が高まり、社会の安定性が増しました。
しかし、法律を作っただけでは、それが守られる保証はありません。法律が実効性を持つためには、その違反を取り締まり、罰則を執行するための強制力が必要です。近代国家は、そのための精緻な制度的装置(警察、検察、裁判所など)を整備しました。また、立法、行政、司法の三権を分離し、相互に抑制と均衡を図ることで、権力の濫用を防ぎ、法の支配を貫徹しようとしました(三権分立)。
人々は、これらの制度が正しく機能していると信じているからこそ、法律を信頼し、それに従います。たとえ個々の警察官や裁判官を個人的に知らなくても、「制度」が公平性を担保してくれると信じているのです。
このようにして、信頼の対象は、超自然的な「神」から、人間が理性に基づいて設計した「制度」や「法」へと移行しました。神への信仰が内面的な規律によって社会秩序を支えていたのに対し、法の支配は、外部的な強制力と制度的な仕組みによって社会秩序を支えるシステムであると言えます。
しかし、社会がさらに複雑化し、グローバル化が進む中で、国家の枠組みだけでは解決できない問題が増えてきました。そこで、人々の信頼を集めるようになったのが、次に見ていく「市場」です。
4. 市場への信頼 ― 見えざる手
「法」と「国家」が近代社会の骨格を形成した一方で、社会の血肉となり、人々の生活を豊かにしたのは「市場」でした。市場経済は、個人の自由な経済活動を通じて、社会全体の富を増大させる強力なエンジンとなりました。
アダム・スミスと「市場が秩序をもたらす」という考え方。
近代以前の社会において、経済活動はしばしば道徳や宗教的な観点から否定的に見られていました。富を蓄積することは貪欲な行為として戒められ、経済活動は共同体のルールやギルドの規制によって厳しく制限されていました。
この考え方を大きく変えたのが、18世紀の経済学者アダム・スミスです。彼は著書『国富論』(1776年)の中で、市場経済が持つ驚くべき調整能力について論じました。
アダム・スミスは、個人が自由に自己の利益を追求することが、結果として社会全体の利益につながると主張しました。パン屋がパンを焼くのは、慈悲心からではなく、自らの利益のためです。しかし、各人が自由に自らの利益を追求することが、市場メカニズム(価格メカニズム)を通じて調整されることで、需要と供給が一致し、資源が効率的に配分され、社会全体が豊かになるというのです。
スミスは、この市場の調整機能を「(神の)見えざる手」と呼びました。重要なのは、誰も全体のことを考えて計画したり、命令したりする必要はないということです。各人がバラバラに自分の利益だけを考えて行動しているにもかかわらず、市場というシステム全体で見ると、あたかも誰かが調整しているかのように秩序が生まれるのです。
この思想は、国家による経済活動への介入を最小限に抑えるべきだという「自由放任主義(レッセ・フェール)」の考え方につながりました。人々は、「市場に任せておけば、すべてうまくいく」という物語を信じるようになりました。市場がもたらす「秩序」と「豊かさ」への信頼は、神や国家への信頼に匹敵するほど強力なものとなっていきました。
金本位制・中央銀行制度 → 貨幣の信用は「市場と国家」によって担保される。
市場経済が機能するためには、取引の手段である貨幣の価値が安定していることが不可欠です。近代以降、貨幣の信用を担保する仕組みは、どのように進化してきたのでしょうか。
19世紀から20世紀初頭にかけて、多くの国が採用したのが「金本位制」です。これは、貨幣の価値を金(ゴールド)という実物資産と結びつける制度です。中央銀行は、保有する金の量に応じて貨幣を発行し、いつでも貨幣と金との交換(兌換)を保証しました。
金本位制の下では、貨幣の信用は「金と交換できる」という事実によって担保されていました。人々は、国家や政府を完全に信用していなくても、金という普遍的な価値を持つ資産を信じていたからこそ、貨幣を安心して使うことができたのです。
しかし、第一次世界大戦や世界恐慌を経て、多くの国が金本位制を放棄しました。そして、金との兌換を停止し、中央銀行が自らの判断で貨幣の発行量を調節する「管理通貨制度」へと移行しました。
管理通貨制度の下では、貨幣の価値は金という実物資産によっては裏付けられていません。では、何が貨幣の信用を担保しているのでしょうか。
それは、「国家の信用力」と「市場の信任」です。
中央銀行は、物価の安定と経済成長を実現するために、金融政策を通じて貨幣の価値を維持する役割を担っています。人々は、中央銀行が適切な政策運営を行う能力と意志があると信じているからこそ、その貨幣を使います。また、その国の経済力や政治的な安定性も、貨幣の信用に影響を与えます。
このように、現代の貨幣システムは、「国家(中央銀行)」が制度的な枠組みを提供し、「市場」がその国の経済力や政策運営を評価することによって成り立っています。私たちは、この複雑なシステム全体が機能していることを信じているからこそ、福沢諭吉が印刷された単なる紙切れに1万円の価値があると信じることができるのです。
グローバル化と市場万能主義が広がる現代。
20世紀後半、特に冷戦終結以降、市場経済は世界中を席巻しました。グローバル化の進展とともに、ヒト、モノ、カネが国境を越えて自由に行き交うようになり、世界は一つの巨大な市場として統合されていきました。
この流れの中で、「市場メカニズムこそが最も効率的で公正な資源配分の方法である」という考え方、すなわち「市場万能主義(マーケット・ファンダメンタリズム)」が大きな影響力を持つようになりました。1980年代以降、規制緩和、民営化、小さな政府を目指す「新自由主義」的な政策が推進されました。
人々は、市場がもたらす経済成長と豊かさを享受し、市場への信頼をますます強めていきました。「市場は常に正しい」「市場に任せればすべて解決する」という神話が生まれたのです。
しかし、市場への信頼は、決して盤石なものではありません。2008年のリーマン・ショックは、市場万能主義の限界と、金融システムの脆さを露呈させました。複雑化しすぎた金融商品は、リスクを適切に評価することを困難にし、一部の市場参加者の貪欲な行動が、システム全体を崩壊の危機に陥れました。結局、市場の失敗を救済するために、国家による大規模な公的資金の投入が必要となりました。
また、市場経済は効率性を追求する一方で、格差の拡大や環境問題といった負の側面ももたらしました。私たちは今、「市場」という巨大なシステムを信じつつも、その限界と脆さにも気づき始めているのです。
5. まとめ
前編では、人類が社会を維持するために「信じてきたもの」が、歴史と共にどのように移り変わってきたのかを概観してきました。
神 → 法 → 市場、と「信じるもの」は変化してきた。
太古の昔、人々は「神」を信じました。絶対的な権威を持つ神の存在が、共同体のルールを定め、秩序を維持する上で不可欠でした。「神が見ている」という感覚が、人々の行動を律し、社会全体の信頼を支えていたのです。
近代に入ると、神に代わって「法」と「国家」が信頼の対象となりました。社会契約論に基づき、人々は自らの合意によってルールを定め、制度的な仕組みによってその履行を担保しようとしました。「法の支配」は、人間の理性への信頼に基づく新しい社会秩序の形でした。
そして現代、私たちが最も強く信じているのは「市場」です。市場メカニズムがもたらす効率性と豊かさへの信頼が、グローバルな社会を動かす原動力となりました。
しかし、依然として「誰か/何かを信じること」が共同体の前提であることは変わらない。
「信じるもの」の対象は変化してきましたが、一つだけ変わらないことがあります。それは、私たちが社会を維持するためには、依然として「誰か/何かを信じること」が必要であるということです。
神、法、市場。これらはいずれも、見知らぬ他人同士が協力し合うための「信頼の装置」であり、私たちが共有する「共同幻想」です。この共同幻想がなければ、社会は成り立ちません。
そして、これらの信頼の装置は、いずれも完璧ではありませんでした。神の名の下に異端者が弾圧され、法の名の下に不正が行われ、市場の名の下に格差が拡大してきました。私たちは、これらの失敗と限界を経験するたびに、信頼のあり方をアップデートしてきたのです。
次回は、この流れを踏まえて「コード」が信頼の対象になりうるのかを考える。
そして今、私たちは新たな時代の入り口に立っています。インターネットとデジタル技術の進化は、既存の信頼の枠組み(国家、市場、そしてWeb2.0時代の巨大プラットフォーム企業)の限界を露呈させると同時に、新しい信頼の形を生み出しつつあります。
それが「コード」への信頼、すなわちweb3の世界観です。
プログラムコードによって記述され、ブロックチェーン技術によって実行されるルールは、人間の恣意的な解釈や改竄を許しません。それは、透明で、公平で、自動的に執行される新しい「法」の形とも言えます。
後編では、この歴史的な流れを踏まえ、なぜ今「コード」が新しい信頼の対象として注目されているのか、そしてweb3が私たちの社会をどのように変えうるのかについて、深く掘り下げていきます。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら