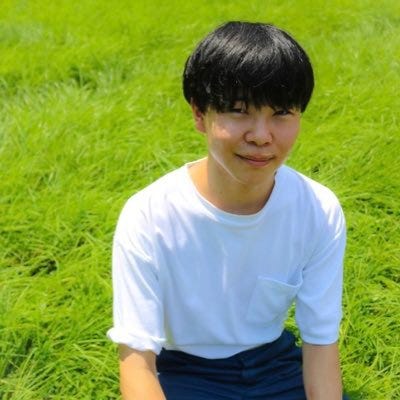【TicketMe(チケミー)】日本初NFTチケット販売プラットフォームのファウンダーへ直接インタビュー!!
「TicketMe」とは、日本初のNFTチケット販売プラットフォームです。
おはようございます。
web3researcherの三井です。
今日は「TicketMe」というNFTチケット販売プラットフォームについてリサーチしました。ファウンダーの宮下さんに直接インタビューさせていただき、その内容も踏まえて概要から展望までを解説していきます。
«目次»
1、TicketMe(チケミー)とは?
2、なぜTicketMeを立ち上げたのか?(ファウンダー宮下さんの経歴)
3、物流や不動産に進出する!?(今後の展望)
4、戦略的な参入と展望(感想)
※1)インタビューでの回答と一言一句同じではなく、わかりやすいよう少し加筆修正をしています。ただ、本人に確認いただいているので内容に相違はありません。
※2)細かい技術的な説明は省き、概要が理解できるように意識して書かれた記事となっています。
アドレス登録で、web3に関するリサーチが平日毎朝届きます。登録無料。
TicketMe(チケミー)とは?
「TicketMe」とは、日本初のNFTチケット販売プラットフォームです。
■“NFTチケット”とは
NFTチケットはその名の通り、NFTによるチケットです。従来の紙チケットや電子チケットに代わるWeb3.0時代の新しいチケットとして注目を集め始めています。
海外ではすでにNFTチケットは普及し始めており、アメリカNFLでは最も盛り上がる試合”スーパーボウル”の試合で7万枚のNFTチケットを配布しました。
■メリットは?
では、NFTでチケットを販売する又は購入するメリットはどこにあるのでしょうか?販売側(イベント主催側)と購入側(イベント参加側)に分かれて解説します。
○販売側(イベント主催側)
二次流通を見越したチケット販売ができる!
今までチケットの転売は主催者の大きな課題でしたが、公式で二次流通を許可することが可能となり、その際の転売手数料の一部が運営に入るような設計もできます。チケット購入者(NFTチケット保有者)限定コミュニティーの作成やアプローチが容易となる!
例えば、NFTチケット保有者限定のオフ会の開催や、先行チケット販売等が可能となります。ファンの把握と優先的なアプローチが可能となります。
○参加側(イベント参加側)
イベントの参加証明が残り続ける!
自分が参加したイベント証明がNFTとして残るので、記念品としても残し続けることができる。その参加証明を持っていることで限定コミュニティーに参加できたり、今後のチケット販売にて優先される可能性もあります。参加できなくなった場合、すぐに転売ができる!
行こうと思っていたイベントに急遽いけなくなった場合の転売が容易になります。加えて、裏ルートではなく公式の目が届く範囲での転売なので、安心して活用できます。(転売で購入する側も安心です)
NFTであるメリットが存分に活用できるのがNFTチケットです。そして、そんなNFTチケットを発行できるプラットフォームが「TicketMe(チケミー)」です。
■TicketMeのメリットは?
TicketMeでは、誰でも簡単にNFTチケットを発行・販売することができます。加えて、参加者も興味を持ったイベントに参加し、NFTチケットを受け取ることができます。
その中で、TicketMeのメリットがこちらです。
NFTについての理解が薄い人でも通常のチケット販売と同じように利用できます。また、日本円での販売にも対応しています。
加えて、購入者(参加側)はMetaMask等のウォレット作成をしなくてもNFTチケットの購入や保管をすることができます。
正直、今までもOpenSea等を使えばNFTでチケットを発行すること自体はできましたが、仮想通貨決済のみであったり、参加者側がMetaMask等のウォレット作成をする必要があったりと、かなりハードルが高い作業でした。
TicketMeはこのハードルを下げ、「日本円での決済(クレカ決済)」&「ウォレット作成の手間なし」を実現しました。
ウォレット作成の手間なしとはいえ、NFTとしてきちんと保管はされており、購入したNFTチケットはOpenSea等のマーケットプレイスで二次流通に載せることが可能となっています。
また、二次流通の設計に関して主催者側があらかじめ設定することができます。まだ実装されていない機能もあるそうですが、その詳細も説明資料の中に載っていました。今後、二次流通を禁止したり、収益の分配を変えたり等の細かい設定ができるようになるようです。
この機能だけでもイベントの体験が大きく変わりそうで、とてもワクワクしますね。
なぜTicketMeを立ち上げたのか?(ファウンダー宮下さんの経歴)
CEOでありファウンダーは「宮下 大佑 (MIYASHITA Daisuke)」さん。
Twitterはこちら。
インタビューでお聞きしたこれまでの経歴やTicketMe設立までの経緯を簡単に箇条書きで解説します。
■経歴
早稲田政治経済学部の2年生。
1年生の時にアパレル系のECサイトを半年ほど運用し、売却した。
その後、EastVenturesでリサーチャーの業務をした後にチケミー設立。
■起業を志す経緯
祖父が二人とも経営者で会社作りたいなと元々思っていた。
ただ、起業家への想いはいつの間にか忘れ、高校の時は建築家を目指していた。
結局、大学受験があまりうまく行かず、建築家の目標は諦め、挫折した。
東大や京大に行った同級生がキャンパスライフを送っている中で、その子たちに勝つには起業するしかないと思った。
■なぜTicketMeだったのか
ブロックチェーンの技術自体は高校生の時から元々面白いなと思って注目していた。
DeFiやDEX作るのもいいなと思ったが、日本で僕が今やるのはハードルが高いと思った。
なぜなら、トークンエコノミクスによって、サービスの構想から実現が圧倒的に速くなったから。
今までの会社と違い、協力できる部分だけ世界中から集まった人が瞬時に協力し、解散するチームのあり方が可能になった。
これを見た時に、最先端技術を追い求める領域は株式会社では戦えないと感じた。
そこで、”労働集約型”と”地域密着型”が組み込まれたNFTチケットのプラットフォームサービスに目をつけた。
チケット販売プラットフォームはC向けのように思えるけど、実はB向けで、これは時間をかけないといけないからチャンスがある。
実際に事前リサーチをしている中で、海外のそこそこ大きなNFTチケット販売プラットフォームに問い合わせをしたら、翌日に英語で電話がかかってきた。
そんなアナログな営業をしているということは、やっぱり労働集約型と地域密着型の側面があると感じた。
あとは、NFTが今までPFPとかアートの文脈で語られていたので、その延長線上にあり、ある程度理解されやすい”チケット”から始めることにした。
■リリース後の反響等
大企業の方からの問い合わせが多いことにびっくりした。意外に興味を持ってる企業が多くあるんだと感じた。
あとは、エンジニアが少なすぎて探すことに苦労してます、、。
物流や不動産に進出する!?(今後の展望)
こちらもインタビューの内容を箇条書きで解説します。
今後は物流や不動産に進出していきたい。
チケミーグッズ(TicketMe Goods)やチケミーリアルテステート(TicketMe RealEstate)のリリースを準備している。
これはフィジカルなモノに紐づいたNFTを発行し、二次流通できるようになるイメージ。
実際のフィジカルなモノはTicketMeが所有する倉庫に保管され、その所有権がNFTによって売買される。
そのNFTの保有者は実際のモノが欲しいとなったら、住所入力等の一連の手続きを行えば、実際の手元に届く。
一度フィジカルなモノが手元に配送されたら、以降はそのNFTの売買ができない。
これは商品購入後の”配送先の権利(住所)”をNFTで売買しているようなもの。
これによって、フィジカルなモノ(不動産含め)の売買が一気に活性化される。今まではモノの移動や各種契約込みで一回の売買が成立していたが、NFTの売買だけでそれが終了するようになる。
流動性が増えればあらゆる物が購入しやすくなるので、日本の伝統工芸品を海外の投資家が購入する機会も増えていくはず。
そして、不動産もNFTで販売し、1分や1時間単位で配当ができるようになれば、リアルタイムで値動きが生まれ、より流動性が高い資産になる。
■個人的解説
チケミーの構想を聞いた時は、僕個人的にめちゃくちゃワクワクしましたが、少し難しいかもしれないので、僕なりの解釈込みで解説します。
チケミーの構想を簡単に言えば「フィジカルなモノの所有権を気軽にNFTで売買できるようにする」です。グッズ、絵画、不動産等々、リアルに存在するもの全てです。
「それがどうした?」
「今でもメルカリとかで出来るよ?」
そう感じる方も多いかもしれませんが、実は既存の仕組みとは異なっており、所有の概念すら変えてしまう可能性がある大きな構想だと僕は思っています。
例えば、僕が作った「三井ぬいぐるみ」をチケミーグッズでNFTを活用しながら販売したとします。
製作者の三井がチケミーグッズに出品。二次流通の手数料等を設定。
チケミーの倉庫に出品したモノを送付。以降はチケミーの倉庫で保管。
三井ぬいぐるみが欲しい人がNFTで購入!
実際のモノがいますぐ欲しい場合は、住所入力し、手元に置く。※この時点で所有権が確定するので、以降そのNFTによる所有権の売買はできない。
まだ手元になくても良い人は、そのまま権利をNFTで保有しておく。※この時点では実際の商品はチケミーの倉庫にある。
(3-bの続き)やっぱりグッズが要らないと思った人は、その権利をNFTで販売し、売却する。
3に戻り、3-aか3-bに進み4にいく。
最終的に実際のモノが欲しい人が生まれるまで所有権の売買だけがNFT(デジタル上)で続いていく。
このプロセスの中で製作者の僕は、最初の販売売上の他に、二次流通の度に売買手数料が入ってくるようになります。
つまり、モノが欲しくて購入する人が、実際に手元にモノが届く前であれば、その所有権を他人に売買できるようになるわけです。
これによって、
購入後にやっぱり要らないと思った人が気軽に転売できるようになる。
海外に住む人が国外(日本)のリアルなものを気軽に購入できるようになる。
この結果、一連のプロセスにおける売買の手間が大幅に短縮されるので、フィジカルなモノの流動性が上がり、販売が容易になり、値上がりする可能性も増えます。
細かい説明は省きますが、経済学の世界において、そしてモノの値段が決定するプロセスにおいて、流動性が高い商品ほど価値が高まります。シンプルに言えば、売りやすい商品の方が価値が高いということです。
例えば、グッチ等の高級ブランドも二次流通の転売マーケットが充実していますよね。最近ブームとなったスニーカーも二次流通のアプリが同じく流行しています。要らなくなったらすぐに転売できるので、高価なモノでも買いやすくなるわけです。
このインパクトはとても大きいです。
不動産の売買もリアルタイムで値動きが起こるようになり、地方にある土地の売買も容易になります。例えば、1年の中で大きな祭りの時だけ賑わう地方の土地や物件もそのタイミングで売買できるようになれば、そこを見越してそれ以外の時期に購入し、値上がりのタイミングで売却もできるようになります。このように、流動性が高まれば、売買が活発になり、今まで価値がつきづらかったものにも値段がつきやすくなります。
という感じで、今あるモノの価値が再定義される可能性があるほどの大きな可能性を秘めた市場と言えます。
戦略的な参入と展望(感想)
以上が、TicketMeの概要とファウンダーの経歴、そして展望でした。30~40分ほどお話しさせていただきましたが、そもそもこの領域に参入した理由と、事業展開のステップがかなり戦略的に考えられており、とても勉強になりました。
また、NFTプロジェクトをリサーチしているだけでは見えてこないNFTの新しい可能性についても気付かされたインタビュー(リサーチ)でした。
このweb3領域では、市場の理解と技術の成熟が追いついてきていない部分が多く、本当にやりたいことがあっても、それをどの順序で進めていくのかが求められます。
ただ、市場が追いついた時に始めても既に遅いです。今からNFTのマーケットプレイスを始めるみたいなものですね。なので、来るその時まで地道にコツコツとできる範囲でプロダクトを作り、影響力とチームと資金を貯めていく必要が求められます。
OpenSeaの創業も5年前で、各チェーンのファウンダーも数年以上前からブロックチェーンにコミットして今ここにいます。やはり、そういった長期的な視点と運営が必要なのだと改めて感じました。そう考えると、そこまで会社を持続させ続けるための経営力も必要となってくる戦いですね。
インタビューの中でも、その経営戦略にも触れ「長期的な成長には良いメンバーを集めることが必須だと考えていて、今のメンバーは本当に良い方ばかりでありがたい、、。」とも仰っていました。
多くの観点で刺激になり、勉強になりました!改めましてインタビューにご協力いただいたチケミーの宮下さん、どうもありがとうございました!
僕もチケミーでイベントさせていただきます。
■イベント運営者として興味がある方は、HPもしくはTwitterからお問い合わせしてみてください!
「TicketMe」
・HP:https://event.ticketme.io/
・Twitter:https://twitter.com/TicketMe_yeah
・ファウンダー宮下さんのTwitter:https://twitter.com/dd_TicketMe
以上、記事が面白いなと思った方はぜひ「アドレス登録」と「SNSでシェア」をしていただけると嬉しいです。引き続きweb3をリサーチしていきます。
おわり。
アドレス登録で、web3に関するリサーチが平日毎朝届きます。登録無料。
🔗mitsui@web3
・Twitter:https://twitter.com/koheimitsui_