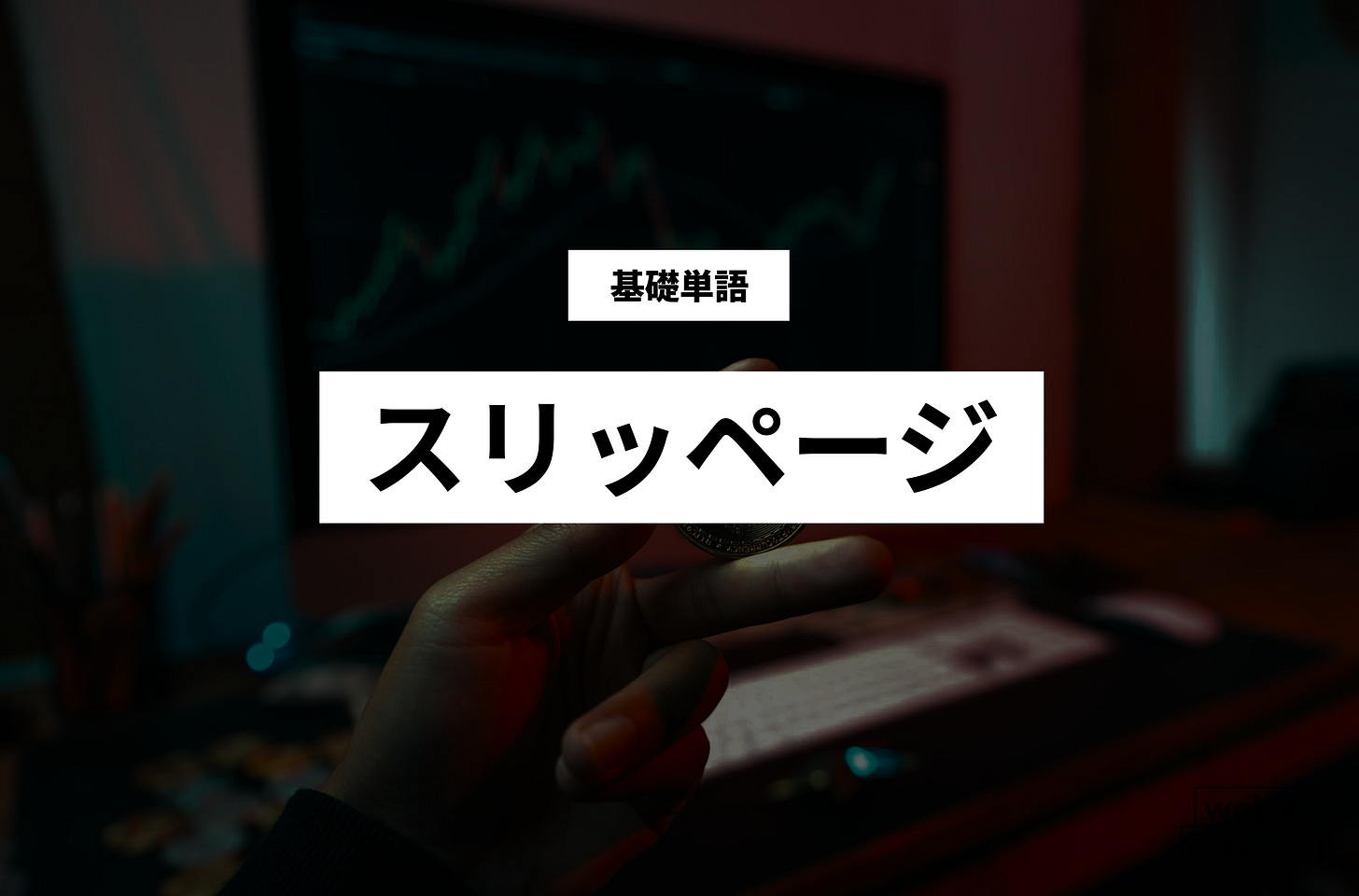おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日の昼にはweb3の基礎レポートをお送りしていましたが、少し派生して1つ1つの「単語」解説記事を更新してみます。各記事をサクッと読めるような文量にして、改めて振り返れる、また勉強できるような記事を目指していきます。
本日は「スリッページ」です。
ぜひ最後までご覧ください!
導入:DEX取引で感じる「わずかな損」の正体
UniswapなどのDEXでトークンをスワップした際、「あれ、見積もりより少し受け取る量が少ないな」と感じた経験はないでしょうか。例えば、1ETHを2,000USDCに交換しようとしたのに、実際には1,995USDCしか手元に残らなかった、といった具合です。この見積もりと実際の約定価格との「差額」こそが、「スリッページ(Slippage)」と呼ばれる現象です。
スリッページは、単なる手数料(ガス代)とは異なる、AMM特有の価格変動メカニズムによって発生します。この概念を理解することは、なぜ大口の取引が市場価格に影響を与えるのか、AMMがどのように価格を自動調整しているのかを理解する鍵となります。
さらに言えば、この仕組みを理解しない限り、流動性提供(LP)の報酬やインパーマネントロスの本質を掴むことはできません。この記事では、価格が「ずれる」理由とその対策について解説します。
スリッページの基本構造:「ずれ」はなぜ起こるのか
スリッページとは、トランザクションを送信した時点で見積もった価格と、その取引が実際にブロックチェーン上で成立(約定)した価格との間に生じる「差」として定義されます。この価格のずれは、主に以下の3つの要因によって引き起こされます。
プールの流動性量(深さ): 流動性プール内の資産総量が少ない(流動性が「薄い」)場合、少額の取引でも価格が大きく変動します。逆に、潤沢な資産(流動性が「深い」)があれば、価格変動は抑制されます。
トランザクションの競合: 人気のトークンでは、同時に多くのユーザーが注文を出します。自分の注文が処理される直前に他の誰かの取引が成立すれば、プールの状態が変わり、結果として約定価格も変化します。
ブロック確定までの時間差: 取引を送信してから、それがブロックチェーンに取り込まれて確定するまでにはタイムラグがあります。その間にも市場全体の価格は変動し続けるため、ずれが生じます。
この価格変動のメカニズムを、Uniswap v2などで採用されている基本的なAMMモデル「x * y = k(定数積モデル)」で具体的に見てみましょう。
例:USDC/ETHプールがあり、現在「x(ETHの量)= 100ETH」「y(USDCの量)= 200,000USDC」だとします。この時、k(定数)は 100 * 200,000 = 20,000,000 です。現在の価格は 200,000 / 100 = 2,000 USDC/ETH です。
ここで、あるトレーダーが1ETHを買う(USDCを支払って1ETHを得る)場合を考えます。 トレーダーは1ETHをプールから引き出すため、ETHの残量は x’ = 100 - 1 = 99ETH となります。 「k」は一定であるため、新しいUSDCの量(y’)は k / x’ = 20,000,000 / 99 ≒ 202,020USDC となります。 トレーダーが支払ったUSDCは 202,020 - 200,000 = 2,020USDC です。
つまり、このトレーダーは1ETHを平均2,020USDCで買ったことになります。取引前の価格(2,000USDC)との差額が、流動性量に起因する「スリッページ」の正体です。
トレード設定における「スリッページ許容度」とMEVのリスク
DEXやウォレットのスワップ画面には、必ず「Slippage Tolerance(スリッページ許容度)」という設定項目があります。これは、取引が成立する際に、見積価格からどの程度の価格変動までを許容するかをパーセンテージで指定するものです。
例えば、許容度を「0.5%」に設定した場合。約定価格が見積価格より0.5%以上不利になると、その取引は自動的に失敗(Revert)します。これは、予期せぬ大きな価格変動から資産を守る安全装置です。
一方で、許容度を「5%」のように高く設定するとどうなるでしょうか。価格変動が激しい相場でも取引が通りやすくなりますが、同時に大きなリスクを抱えることになります。その最たる例が、MEV(Miner/Maximal Extractable Value:マイナー/バリデーターが抽出可能な最大価値)を利用した「サンドイッチ攻撃」です。
MEVとは、ブロック生成者や専門のBotが、トランザクションの順序を操作することで利益を得る行為を指します。
サンドイッチ攻撃の流れはこうです。
Botは、ユーザーがスリッページ許容度を高く設定して大きな取引を出したことを検知します。すると、Botはその取引の直前(フロントラン)に自身の買い注文を挿入し、意図的に価格を吊り上げます。ユーザーの取引は高い価格で約定し(許容度が高いため失敗しない)、その直後(バックラン)にBotは売り注文を挿入して利益を確定させます。結果として、ユーザーは許容範囲ギリギリの不利な価格で取引させられてしまうのです。
こうした攻撃や不利な約定を避けるためには、いくつかの対策があります。
スワップ量を小さく分割する: 大口取引は価格への影響が大きいため、複数回に分けて取引する。
流動性の深いプールを選ぶ: Uniswap v3、Curve、Balancerなど、取引量が多く、預け入れ資産が多いDEXやペアを選択する。
安定ペアの特徴を理解する: USDC/USDTのようなステーブルコイン同士のペアでは、価格変動が極めて小さいため、スリッページも発生しにくい。
価格形成の「摩擦」としての意味
スリッページは、単にトレーダーが被る「損」として捉えられがちですが、市場メカニズムの観点からは「市場の摩擦コスト」として重要な意味を持っています。
実世界の金融市場、例えば株式取引やFXにおいても、似たような現象は存在します。株式市場では、特定の価格でどれだけの注文が出ているかを示す「板情報」があり、一度に大量の注文を出すと、板が薄い価格帯まで約定が進み、平均取得価格が不利になることがあります。また、FXでは買い価格と売り価格の差である「スプレッド」が取引コストとなります。
DEXにおけるスリッページも、これらと同様に、市場で資産を交換するために必要な「摩擦」であり「コスト」です。分散化された市場では、流動性プールという限られた資源を使って取引を行うため、その資源量に応じたコスト(価格変動)が発生するのは当然の帰結なのです。
近年主流となっている集中流動性AMM(Uniswap v3など)は、この「摩擦コスト」の概念を進化させたモデルといえます。従来のAMM(v2)では流動性が全価格帯に均等に分散されていたのに対し、v3では流動性供給者が特定の価格範囲に資本を集中させることができます。
これは、取引が頻繁に行われる価格帯に資本を集中させ、その範囲内でのスリッページを劇的に小さく抑える試みです。スリッページを可視化し、より合理的な価格帯に資本を誘導する設計思想がそこにはあります。
web3の価格形成を理解する上で、「スリッページ=分散市場における流動性コスト」という視点は欠かせません。
まとめ
スリッページは、DEXを利用する上で避けて通れない現象ですが、それは「避けるべき悪」ではなく、AMMの価格決定メカニズムを反映した「理解してコントロールすべきもの」です。
価格変動の構造(流動性の深さ、x*y=kモデル、MEVのリスク)を知ることで、トレーダーはスリッページ許容度の設定を最適化し、リスクを定量的に管理できるようになります。また、LP戦略を設計する上でも不可欠な知識です。
今回解説したスリッページは、市場価格の「ずれ」や「歪み」の発生源とも言えます。次回テーマである「アービトラージ(裁定取引)」は、まさにこの“ずれ”を利用して利益を上げつつ、市場価格を均衡させる存在として繋がっていきます。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら