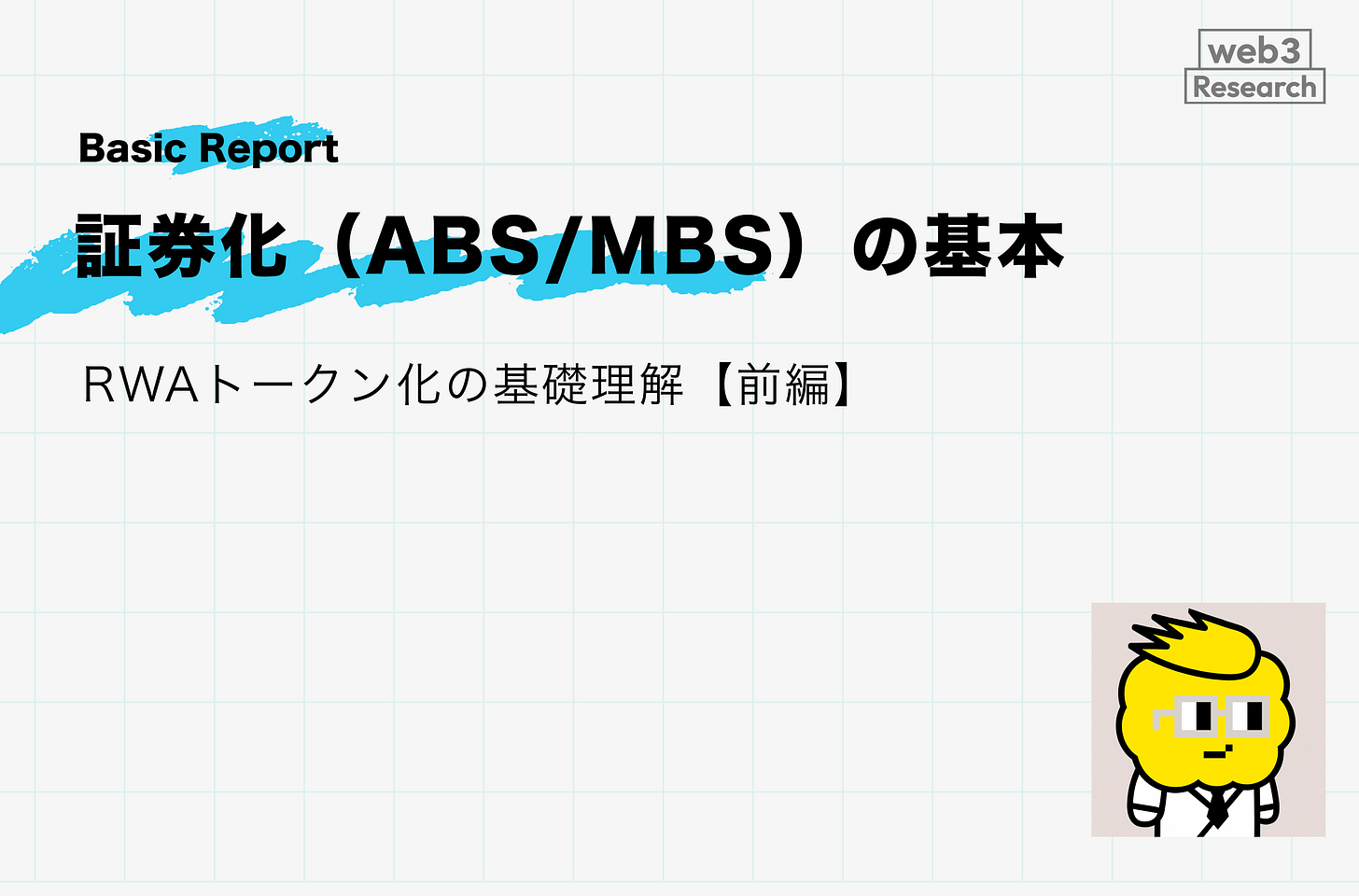おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎レポートを更新しています。今週は「RWAトークン化の基礎」について解説します。ぜひ最後までご覧ください!
1. はじめに
2. プレイヤーと基本構造
3. SPVの役割
4. ウォーターフォール(資金配分ルール)
5. クレジットエンハンス(信用補完)
6. まとめ
1. はじめに
なぜRWAトークンを理解する前に「証券化」を学ぶべきか
近年、web3の分野でRWA(Real World Assets)トークンへの関心が急速に高まっています。従来の金融資産をブロックチェーン上でトークン化し、新たな流動性や投資機会を創出する取り組みが活発化しているのです。しかし、RWAトークンの本質を理解するためには、その土台となる伝統的な「証券化」の仕組みを深く理解することが不可欠です。
証券化は、1970年代の米国住宅ローン市場で始まり、その後世界中に広がった金融技術です。資産を束ね、そこから生じるキャッシュフローを基に証券を発行し、リスクを細分化して投資家に分配する仕組みは、現代金融の根幹を成しています。
2008年の金融危機を経て様々な改革が行われましたが、その基本的な思想と技術は今日でも進化を続けており、RWAトークンはまさにこの証券化の思想をブロックチェーン技術によってコード化する試みと言えます。
資産を束ねて証券化し、リスクを見える化・分配する仕組み
証券化とは、銀行や金融機関が保有する貸付債権や不動産などの資産を束ね、それらから生み出されるキャッシュフローを裏付けとして証券を発行する金融技術です。
この仕組みの肝は、個別資産のリスクをプール化によって分散し、異なるリスク選好を持つ投資家のニーズに応じて、リスクとリターンの異なる複数の証券(トランシェ)に分割することにあります。
従来、銀行が住宅ローンを貸し出した場合、その信用リスクは銀行のバランスシート上に残り続けました。しかし証券化によって、銀行は貸付債権を第三者に売却し、リスクを移転できるようになりました。これにより銀行は新たな融資原資を確保でき、投資家は多様化されたポートフォリオへの投資機会を得ることができます。
この仕組みの画期的な点は、「リスクの見える化」と「契約による自動的な分配」にあります。従来は銀行内部に埋もれていた個別ローンのリスク情報が詳細に開示され、あらかじめ定められた契約条件に従って、回収された元利金が投資家に機械的に分配されます。この透明性と自動化の思想こそが、後のRWAトークンの基盤となる考え方と言えます。
2. プレイヤーと基本構造
証券化取引は複数の専門的なプレイヤーによって構成されるエコシステムです。それぞれが特定の役割を担い、全体として効率的なリスク分散と資金調達を実現しています。
オリジネーター(銀行・ノンバンク)
オリジネーターは、証券化の対象となる資産の最初の保有者です。住宅ローンを貸し出した銀行、オートローンを提供したノンバンク、クレジットカード会社、学生ローンを扱う教育金融機関などが該当します。オリジネーターは、顧客との直接的な関係を持ち、与信審査から資産の組成まで一連のプロセスを管理します。
オリジネーターの役割は単純な資産売却にとどまりません。証券化後も、多くの場合において資産の一部を保持する「リスク・リテンション」が求められ、資産の品質に対する継続的な責任を負います。また、借り手との関係維持や、証券化商品の投資家への情報提供においても重要な役割を果たします。
SPV
SPV(Special Purpose Vehicle)は、証券化取引の中核を成す法的な器です。オリジネーターから資産を買い取り、その資産を担保として投資家向けに証券を発行します。SPVの最も重要な特徴は「破産隔離」機能にあります。仮にオリジネーターが破綻したとしても、SPVに移転された資産は法的に保護され、投資家の利益が守られる仕組みになっています。
SPVは通常、証券化取引のためだけに設立される特別目的の法人で、その活動は厳格に制限されています。他の事業を行うことはできず、資産の保有と証券の発行、そこから生じるキャッシュフローの分配のみを行います。この制限により、SPV自体が破綻するリスクを最小化しているのです。
アレンジャー・サービサー・トラスティ
アレンジャーは証券化取引全体の設計と組成を担当する投資銀行や証券会社です。資産の選定、トランシェ構造の設計、投資家への販売戦略の策定など、取引の川上から川下まで総合的にコーディネートします。複雑な法的・税務的・規制的要件を満たしながら、市場のニーズに応える証券を設計する専門性が求められます。
サービサーは、証券化後の資産管理を担当します。借り手からの元利金回収、延滞債権の管理、必要に応じた法的手続きの実行などを行います。多くの場合、オリジネーター自身がサービサーを兼任しますが、専門的なサービシング会社に委託される場合もあります。サービサーの業務品質は、証券化商品の最終的なパフォーマンスに直結するため、その選定と監督は極めて重要です。
トラスティは、投資家の利益を代表してSPVの運営を監督する受託者です。契約条件の遵守状況をモニタリングし、必要に応じて投資家のために権利行使を行います。証券化取引における「番人」としての役割を担い、利益相反の防止と透明性の確保に貢献します。
投資家(シニア/メザニン/エクイティ)
証券化における核心的なイノベーションの一つが、単一の資産プールから、リスクとリターンの異なる複数の証券(トランシェ)を創出することです。証券化商品の投資家は、リスク選好に応じて異なるトランシェに投資します。
トランシェ設計の基本原理は、「リスクと利回りのトレードオフ」にあります。損失の吸収順序と利払いの優先順序を対応させることで、投資家の多様なニーズに応える証券を同時に供給できます。
損失吸収の順序は、通常、エクイティ(最劣後)、メザニン(中間)、シニア(最優先)の順番で設計されます。資産プールに損失が発生した場合、まずエクイティトランシェが全額を吸収し、それでも足りない場合にメザニントランシェが吸収し、最後にシニアトランシェに及ぶという構造です。
一方、利回りの順序は損失吸収順序と逆になります。最も高いリスクを負担するエクイティが最も高い利回りを得る権利を持ち、最も安全なシニアが最も低い利回りになります。この設計により、リスク回避的な投資家は安定した低利回りを、リスク選好的な投資家は高いリターンの可能性を得ることができます。
シニア投資家は、年金基金や保険会社など安定したリターンを求める機関投資家が中心です。これらの投資家は、元本の安全性を最優先とし、相対的に低いリターンで満足します。
メザニン投資家は、シニアよりも高いリターンを求める代わりに、より高いリスクを受け入れる投資家です。ヘッジファンドやプライベートエクイティファンド、一部の保険会社や資産運用会社が典型的な投資家層です。
エクイティ投資家は、最もリスクが高い代わりに最も高いリターンの可能性を持つ部分に投資します。多くの場合、オリジネーター自身がエクイティ部分を保有し、資産品質に対する継続的なインセンティブを維持します。
3. SPVの役割
真正売買(true sale)
証券化取引において「真正売買」は、法的・会計的に極めて重要な概念です。オリジネーターからSPVへの資産移転が法的に「真正売買」として認められることで、その資産はオリジネーターのバランスシートから完全に切り離されます。これにより、オリジネーターは会計上の資産圧縮効果を得るとともに、規制資本の節約も実現できます。
真正売買の認定には、複数の法的要件を満たす必要があります。まず、資産の所有権がSPVに完全に移転されなければなりません。次に、オリジネーターが移転後の資産に対して実質的な支配を継続してはいけません。さらに、移転対価が適正な市場価値に基づいて設定されている必要があります。
会計基準においても、真正売買の認定には厳格な要件があります。移転された資産に対するオリジネーターの継続的関与が限定的であること、移転に伴うリスクと経済価値がSPVに実質的に移転されることなどが求められます。2008年の金融危機後、これらの要件はより厳格化されており、オフバランス化の要件も強化されています。
破産隔離(bankruptcy remoteness)
破産隔離は、証券化取引の投資家保護における中核的な機能です。仮にオリジネーターが破綻したとしても、SPVに適切に移転された資産は、オリジネーターの債権者による追及から法的に保護されます。この保護により、投資家は発行体の信用リスクから隔離され、純粋に原資産の品質に基づいた投資判断を行うことができます。
破産隔離を実現するためには、SPVの設立と運営において細心の注意が必要です。SPVは独立した法的主体として設立され、その活動は証券化取引に関する業務に厳格に限定されなければなりません。また、SPVの意思決定において、オリジネーターが実質的な支配を行使できない仕組みを構築する必要があります。
実務上、破産隔離の強化のために、SPVには独立した取締役の選任、事業活動の制限条項の設定、分別管理の徹底など、様々な保護措置が講じられます。さらに、法的意見書(リーガルオピニオン)により、破産隔離の有効性について専門的な検証が行われることが一般的です。
4. ウォーターフォール(資金配分ルール)
費用 → シニア → メザ → エクイティの優先順位
ウォーターフォールは、証券化取引において資産プールから回収された資金をどのような順序で配分するかを定めた重要なルールです。この配分ルールは、取引開始時に詳細に契約で定められ、その後の運用期間中は機械的に適用されます。透明性と予測可能性を確保することで、投資家は自らの投資判断を適切に行うことができるのです。
典型的なウォーターフォールでは、まず取引に関わる各種費用が最優先で支払われます。サービサー手数料、トラスティー手数料、格付機関手数料、監査費用、法務費用など、取引の継続に必要な費用が確実に確保されることで、証券化商品の安定的な運営が担保されます。
費用の支払い後、残余資金は投資家への配分に向けられます。まず、シニアトランシェの利払いと元本償還が行われ、次にメザニントランシェ、最後にエクイティトランシェという順序で配分されます。各トランシェ内でも、利払いが元本償還に優先するのが一般的です。
トリガー(OC/ICテスト)による自動的な分配変更
ウォーターフォールには、資産プールの健全性を維持するための様々なトリガー条項が組み込まれています。最も重要なトリガーが、OC(Over-Collateralization)テストとIC(Interest Coverage)テストです。これらのテストに抵触した場合、通常のウォーターフォールは変更され、より保守的な資金配分が実行されます。
OCテストは、資産プール残高と発行済み証券残高の比率を監視します。この比率が事前に定められた水準を下回った場合、追加的な信用補完が必要と判断され、本来であればエクイティに配分される資金が元本償還の加速に振り向けられます。これにより、シニアとメザニンの保護水準を維持します。
ICテストは、利息収入と利払い費用の比率を監視します。資産プールからの利息収入が減少し、発行済み証券への利払いをカバーできない状況が生じた場合、エクイティへの配分が停止され、不足分の補填に充てられます。場合によっては、メザニンへの利払いも停止されることがあります。
これらのトリガーメカニズムは、証券化商品の「自己修復機能」として機能します。資産品質の悪化を早期に検知し、自動的により保守的な資金配分に切り替えることで、上位トランシェの投資家保護を強化するのです。投資家にとっては、人為的な判断の介入なしに、客観的な基準に基づいた保護が得られることを意味します。
5. クレジットエンハンス(信用補完)
内部補完(OC、RS、超過スプレッド)
証券化取引における信用補完は、発行される証券の信用度を高め、より良い格付けや低い資金調達コストを実現するための重要な仕組みです。内部補完は、取引構造内部で生み出される信用補完であり、外部からの保証や保険に依存しないという特徴があります。
オーバーコラテラリゼーション(OC)は、最も基本的な内部補完手法です。資産プールの価額を、発行される証券の総額よりも高く設定することで、信用補完効果を生み出します。例えば、100億円の資産プールに対して95億円の証券を発行した場合、5億円分のOCが提供されることになります。このOCは、実質的にエクイティトランシェとして機能し、最初の損失を吸収します。
リザーブファンド(RS)は、取引開始時または運用期間中に積み立てられる現金準備金です。資産プールからの回収金の一部を別途積み立てることで、将来の損失に備えます。リザーブファンドは通常、高格付けの短期証券や預金として運用され、必要時には即座に損失補填に充当できる流動性を保持します。
超過スプレッドは、資産プールから得られる利息収入と、証券保有者への利払い及び諸費用の差額として生じる余剰収益です。この超過スプレッドは、まず当期の信用損失をカバーし、残余があればリザーブファンドの積み立てやエクイティへの配分に充当されます。安定した超過スプレッドの存在は、証券化商品の持続的な信用補完能力を示す重要な指標となります。
外部補完(保証、保険、流動性供与)
外部補完は、第三者から提供される信用補完であり、取引の信用度をさらに向上させるために活用されます。ただし、外部補完提供者の信用力に依存するため、その選定と契約条件の設定が重要になります。
保証は、金融機関や保証会社が証券の元本や利息の支払いを保証する仕組みです。特に、政府系金融機関や高格付けの銀行による保証は、証券化商品の信用度を大幅に向上させる効果があります。住宅ローン証券化においては、政府住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)による保証制度が重要な役割を果たしています。
保険は、保険会社が証券化商品の信用損失をカバーする商品です。モノライン保険会社と呼ばれる専門保険会社が、かつて証券化商品の保険で大きな役割を果たしていましたが、2008年の金融危機で多くが破綻し、現在はその役割が大幅に縮小しています。
流動性供与は、短期的なキャッシュフロー不一致に対応するための仕組みです。銀行がコミットメントラインを提供し、一時的な資金不足時に流動性を供給します。これにより、資産プールからの回収タイミングと証券の利払いタイミングのズレに対応できます。流動性供与は信用リスクをカバーするものではありませんが、証券化商品の安定的な運営に不可欠な機能です。
6. まとめ
証券化の本質=「器 × リスク分配 × 規則」
本稿で詳しく解説してきた証券化の仕組みを一言で表現するならば、「器 × リスク分配 × 規則」の組み合わせと言えます。
この三つの要素が相互に作用することで、伝統的な融資では実現できない柔軟で効率的な資金調達と投資の仕組みが生まれるのです。
「器」であるSPVは、破産隔離機能により投資家を保護し、真の売却により資産移転を確実にします。この法的な器があることで、オリジネーターの信用力に依存することなく、純粋に資産の品質に基づいた投資が可能になります。
「リスク分配」は、トランシェ構造により実現されます。単一の資産プールから、リスクとリターンの異なる複数の証券を創出することで、多様な投資家ニーズに対応できます。シニア、メザニン、エクイティそれぞれの特性を理解し、適切な信用補完措置を講じることで、効率的なリスク配分が可能になるのです。
「規則」は、ウォーターフォールに代表される詳細な契約条項により具現化されます。資金の配分順序、トリガー条項、早期償還条件など、あらゆる場面での行動規則を事前に明確化することで、透明性と予測可能性が確保されます。この規則の機械的な適用により、人為的な判断の介入を最小化し、公平で効率的な運営が実現されます。
リスクを見える化し、契約に従って自動的に配分する仕組み
証券化が金融市場に与えた最大の革新は、「リスクの見える化」にあります。
従来は銀行のバランスシートに埋もれて見えなかった個別資産のリスクが、詳細な開示により投資家に明示されるようになりました。借り手属性、担保特性、地理的分散、ヴィンテージ情報など、膨大なデータが体系的に整理され、投資家の分析に供されます。
さらに重要なのが、「契約に従った自動的な配分」です。ウォーターフォールやトリガー条項により、資産プールから回収された資金は、人為的な判断を介さずに機械的に分配されます。この自動化により、利益相反の排除、処理効率の向上、透明性の確保が実現されます。投資家は、複雑な人間関係や政治的判断に左右されることなく、純粋に契約条件に基づいたリターンを得ることができるのです。
金融危機後の改革により、この透明性と自動化はさらに高度化されました。標準化されたデータフォーマット、機械可読な開示資料、継続的なモニタリング体制の整備により、投資家は高度な分析を効率的に実行できるようになっています。リスク・リテンション要件により、オリジネーターの継続的な関与も確保され、市場全体の品質向上が図られています。
この思想はブロックチェーンと非常に相性が良い
証券化の基本的な思想である「透明性」「自動化」「規則に基づく機械的処理」は、実はブロックチェーン技術やスマートコントラクトの特性と極めて親和性が高いことが分かります。契約条件の事前明確化、実行の自動化、処理の透明性確保といった要素は、まさにコード化によって実現される価値そのものです。
従来の証券化では、複雑な契約書類と多数の仲介者により、透明性と効率性を実現してきました。しかし、これらの仕組みをコード化することで、さらなる透明性の向上、処理コストの削減、リアルタイム処理の実現が期待できます。ウォーターフォールの自動実行、トリガー条項の即座な発動、投資家への瞬時の情報提供など、デジタル技術ならではの付加価値を創出できる可能性があります。
また、従来の証券化では困難だった小口化や24時間取引、グローバルアクセスなども、ブロックチェーン技術により実現可能になります。適格投資家の確認、取引履歴の記録、所有権の移転などの処理も、スマートコントラクトにより効率化できるでしょう。
このように、証券化の基本的な思想とブロックチェーン技術の組み合わせは、単なる既存業務のIT化にとどまらず、資本市場の構造的な革新をもたらす可能性を秘めています。後編では、この証券化の思想がどのようにRWAトークンとして具現化されていくのか、詳しく解説していきます。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら