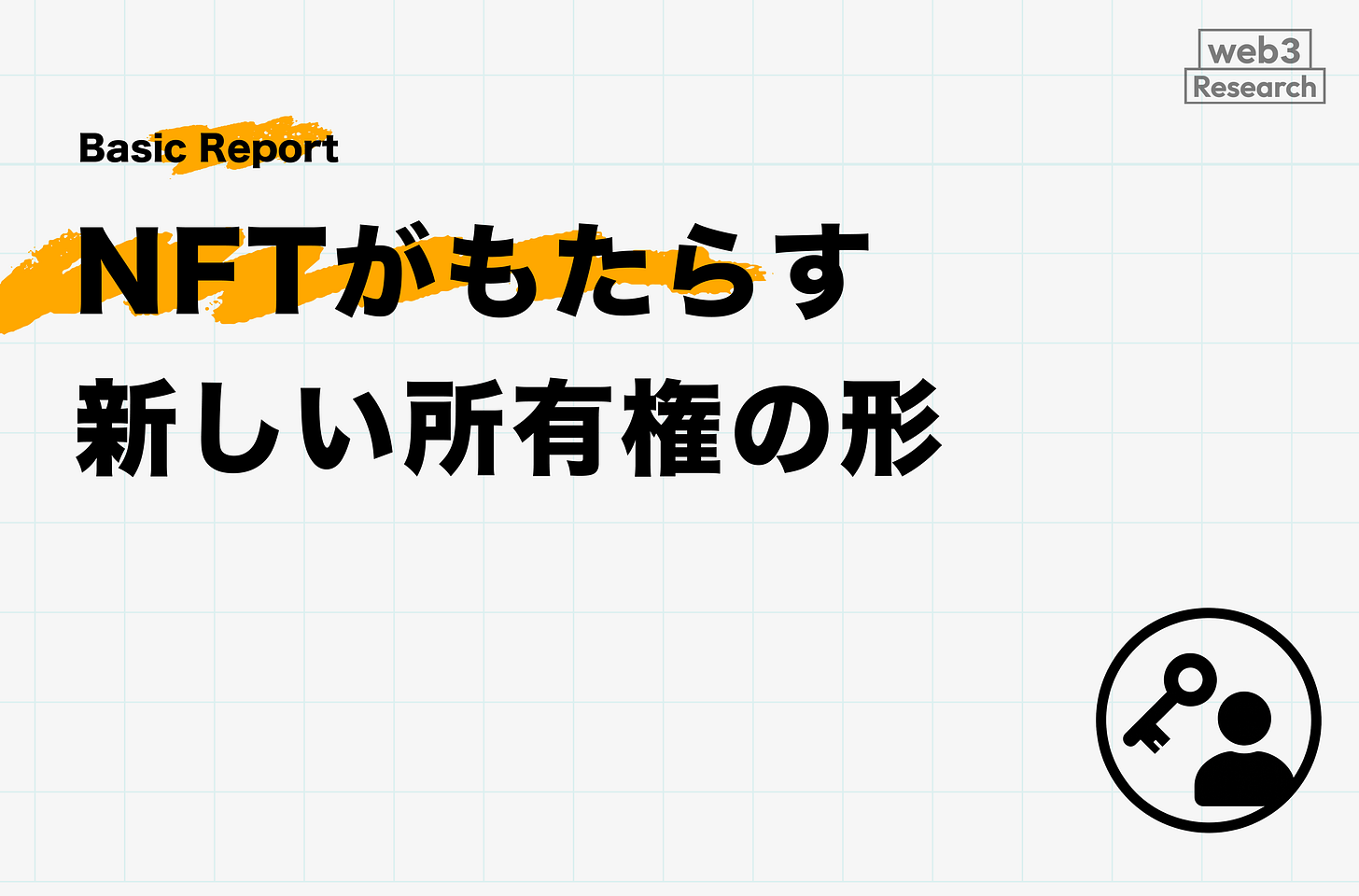おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎レポートを更新しています。今週は「所有権の利用権」について解説します。
NFTとは?技術的な仕組み
NFTと著作権の誤解(作品自体の権利ではなく所有証明)
NFTの課題(コピー可能性、法的整理の未成熟さ)
利用権(ライセンス)とNFTのハイブリッドモデル
今後の展望:「所有する」から「関与する」へのシフト
NFTとは?技術的な仕組み
前編では、物理的な「モノ」に対する所有権が社会の安定と経済発展の基盤となってきた一方で、デジタル「データ」に対しては明確な所有権が確立されず、プラットフォームが提供する「利用権」が主流となっている現状を確認しました。
この課題に対し、新たな解決策として登場したのがNFTです。後編では、まずNFTの基本的な概念と、それを支える技術的な仕組みについて詳しく解説します。
NFTは「非代替性トークン」です。これは、個々のトークンが固有の価値や情報を持ち、他と区別される唯一無二のものであるという性質を指します。例えば、私が持っている1ビットコイン(代替性トークン)と、あなたが持っている1ビットコインは全く同じ価値を持ち、交換可能ですが、私たちが持つNFTはそれぞれが固有の価値を持つため、代替不可能です。
では、NFTは具体的にどのようにして唯一性を実現しているのでしょうか。
その鍵は、個々のNFTに割り当てられる「トークンID」と、NFTの発行・管理を司る「スマートコントラクト」にあります。
NFTの場合、スマートコントラクトには、そのNFTコレクションの名称、総発行数、そして個々のトークンを識別するための固有の番号であるトークンIDに関する情報が定義されています。
このトークンIDこそが、NFTの唯一性の源泉です。NFTが取引される際、「トークンID 1番の所有者はAさんからBさんに変更された」という情報がブロックチェーン上に記録されます。この記録は、ブロックチェーンの特性により、誰にも改ざんすることができず、誰でも閲覧することが可能です。これにより、以下の重要な機能が実現されます。
真正性の証明: そのNFTが特定の作成者によって発行された真正なものであることを証明できます。
所有権の証明: 現在誰がそのNFTを所有しているかを明確に証明できます。ブロックチェーン上の記録が、不動産登記簿のような役割を果たします。
取引履歴の追跡可能性: そのNFTが発行されてから現在に至るまで、誰から誰へと移転してきたかという履歴を完全に追跡できます。
さらに、NFTは「相互運用性(Interoperability)」という重要な特徴も持っています。多くのNFTは、特定のプラットフォームに縛られることなく、様々なウォレットやマーケットプレイスで取り扱うことが可能です。これは、従来のデジタルコンテンツのあり方とは決定的に異なります。
このように、NFTは、ブロックチェーン技術とスマートコントラクトを組み合わせることで、デジタルデータに対して、これまで不可能であった「唯一性」「真正性」「所有可能性」「相互運用性」を付与する画期的な仕組みです。
NFTと著作権の誤解(作品自体の権利ではなく所有証明)
NFTが急速に普及する中で、最も多く見られる誤解の一つが、「NFTを購入すれば、そのデジタルコンテンツの著作権も手に入る」というものです。しかし、これは原則として誤りです。NFTの所有権と、そのNFTに紐づくコンテンツの著作権は、全く別個の権利として扱われるべきです。
著作権は、文学、音楽、美術、プログラムといった創作的な表現(著作物)を保護するための知的財産権です。著作権は、著作物を創作した時点で、創作者に自動的に発生します。
一方、NFTの所有権とは、ブロックチェーン上に記録された特定の「トークンID」に対する排他的な支配権のことです。NFTは、デジタルコンテンツの真正性や所有履歴を証明する「デジタル証明書」のような役割を果たします。
この関係性は、物理的なアート作品の取引と比較すると理解しやすいでしょう。
ある画家が描いた絵画(原画)を購入した場合、購入者はその絵画という有体物の所有権を得ますが、その絵画の著作権は、原則として画家に残ります。購入者が勝手に絵画をコピーして販売したり、インターネットに公開したりすることはできません。
NFTの取引も、これと基本的に同じ構造になっています。
NFTアートを購入した場合、購入者が得るは、そのアート作品に紐づくNFTの所有権です。これは、ブロックチェーン上で証明された、その真正なデジタルアートのオーナーであることを意味します。しかし、特別な合意がない限り、そのデジタルアートの著作権は、作成者であるアーティストが保持し続けます。したがって、NFTの所有者が、そのアート作品をTシャツにプリントして販売したり、広告に使用したりといった商用利用を行うことは、著作権侵害となる可能性が高いのです。
この点が、NFTに関する多くの混乱とトラブルの原因となっています。NFTの所有者は、購入したコンテンツを具体的にどのように利用できるのでしょうか。これは、個々のNFTプロジェクトやマーケットプレイスが定める「利用規約(ライセンス)」によって異なります。
多くのNFTプロジェクトでは、所有者に対して「個人的・非商用的な利用」を許可しています。一方で、商用利用については、プロジェクトによって対応が大きく異なります。Bored Ape Yacht Club (BAYC)のように、所有者に対して商用利用を比較的広範に許可しているプロジェクトもあれば、CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)を採用し、誰でも自由に利用できるようにしているプロジェクトもあります。
NFTは、デジタルコンテンツの所有を証明する強力なツールですが、それだけではコンテンツの利用方法を規定することはできません。所有権(NFT)と利用権(ライセンス)を適切に組み合わせることで、初めてデジタルコンテンツの価値を最大化することができるのです。
NFTの課題(コピー可能性、法的整理の未成熟さ)
NFTは画期的な技術ですが、その急速な発展に伴い、様々な課題やリスクも浮き彫りになっています。
コピー可能性(右クリック保存問題)
「デジタルデータは簡単にコピーできるのに、なぜ所有できると言えるのか?」という疑問は、NFTに関して最も頻繁に投げかけられる批判の一つです。この問いに対する答えは、NFTが証明するのは「データの所有」ではなく、「真正なデータに紐づくトークンの所有」であるという点にあります。
コピーされたデータは、このブロックチェーン上の証明とは紐付いていないため、オリジナルとは明確に区別されます。NFTの価値は、そのデータが持つ真正性や希少性、そして所有者であることのステータスにあります。
法的整理の未成熟さ
NFTが直面するもう一つの大きな課題は、関連する法制度の整備が追いついていないという点です。NFTの法的性質(所有権の対象となるのか、金融商品に該当するのかなど)が不明確であり、紛争が生じた場合に、所有者がどのような法的保護を受けられるのかが不透明な状況にあります。また、著作権侵害やマネーロンダリング対策といった面でも、既存の法律との整合性を図る必要があります。
これらの法的な課題は、NFT市場の健全な発展を阻害する要因となりかねません。技術の進化に合わせて、各国で法制度の整備やガイドラインの策定が急がれています。
利用権(ライセンス)とNFTのハイブリッドモデル
NFTがもたらす「デジタル所有権」は画期的ですが、それだけではデジタルコンテンツの価値を最大化することはできません。NFTの所有権は、あくまでトークンの所有を証明するものであり、紐づくコンテンツをどのように利用できるかを規定するものではないからです。
コンテンツの利用方法を規定するのは、著作権とそれに基づく「利用権(ライセンス)」です。したがって、NFTの可能性を最大限に引き出すためには、所有権(NFT)と利用権(ライセンス)を適切に組み合わせた「ハイブリッドモデル」を構築することが重要となります。
NFTを活用することで、クリエイターは自らの作品に対して、多様な利用条件を設定し、それを所有者に対して直接的かつ透明な形で付与することができます。例えば、同じアート作品であっても、異なるライセンスを付与した複数のNFTを発行することが可能です。
また、NFTとスマートコントラクトを組み合わせることで、ライセンス契約の条件を自動的に執行する「スマートライセンス」の実現も期待されています。
例えば、二次創作NFTが売買されるたびに、その売上の一部が自動的に原作者のウォレットにロイヤリティとして支払われる仕組みを構築できます。これにより、権利処理が透明化・自動化され、クリエイターエコノミーの発展につながります。
今後の展望:「所有する」から「関与する」へのシフト
NFTがもたらす未来は、単なるデジタル資産の所有と取引に留まるものではありません。その先には、「所有」の概念自体がさらに拡張され、「所有する」から「関与する」ことへと重点がシフトしていく、新しい社会経済システムの姿が見えてきます。
その代表例が「DAO」です。DAOは、特定の管理者を持たず、参加者全員が共同で所有・管理する組織です。DAOにおいて、NFTやトークンは、単なる資産としてだけでなく、「メンバーシップ(会員権)」や「ガバナンストークン(議決権)」としての役割を果たします。特定のNFTを保有することが、DAOへの参加資格となり、保有量に応じてプロジェクトの方向性に関する提案や投票に参加する権利が付与されます。
これは、「所有」が「関与」に直結する新しいモデルです。
web3の世界では、「所有者」は単なる消費者や投資家ではなく、プロジェクトの成長に貢献する「参加者」としての役割を担うようになります。所有することによって得られるのは、資産価値の上昇だけでなく、コミュニティへの帰属意識、意思決定への参加権、そしてプロジェクトの成長への貢献といった、より多面的な価値です。
web3が目指す分散型社会の中心にあるのは、この「所有」の再定義という大きな潮流です。物理的なモノの所有権から始まり、知的財産権、デジタルデータの利用権を経て、デジタル資産の所有権へと進化し、今や所有は、単なる排他的な支配権という意味を超えて、コミュニティへの参加権や貢献に対する証明といった、より社会的な意味合いを持つものへと拡張されつつあります。
以上が、所有と著作権の説明、そしてNFTの誤解に対しての説明でした。NFTバブル期から成熟期に入りましたが、可能性がなくなったわけではないので改めて解説してみました。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら