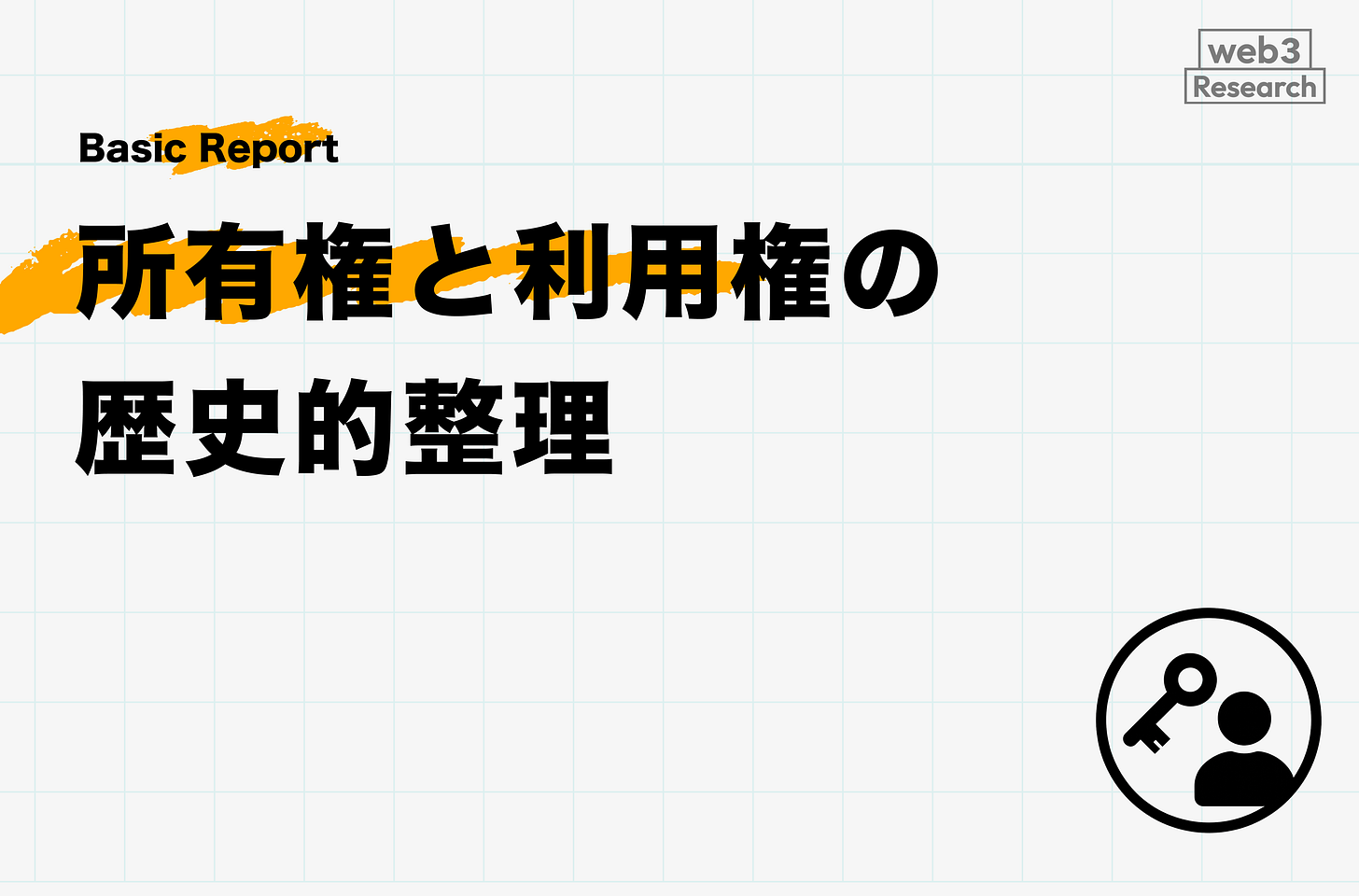おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎レポートを更新しています。今週は「所有権の利用権」について解説します。
はじめに:なぜ所有権と利用権の理解がNFTに不可欠か
古代〜近代:土地・不動産の所有権の確立
産業革命以降:特許・著作権・ライセンスの仕組み
デジタル時代:音楽CDと配信サービス、DRM、サブスクモデル
「モノ」と「データ」の所有権の違い
所有権が社会に与える信頼と安定性
はじめに:なぜ所有権と利用権の理解がNFTに不可欠か
現代社会において、インターネットとデジタル技術は私たちの生活の基盤となり、物理的な現実とデジタルの世界がシームレスに融合しつつあります。
近年、特に注目を集めているのがNFTです。デジタルアートが高額で取引されたり、メタバース上の土地が売買されたりといった現象は、単なる一過性のブームではなく、デジタル時代における「所有」という概念を根本から変える可能性を持ちます。
しかし、NFTを巡る議論はしばしば混乱をもたらします。
「NFTアートを買ったのだから、著作権も手に入るはずだ」「デジタルデータは簡単にコピーできるのに、なぜ所有できると言えるのか」といった誤解が後を絶ちません。この混乱の最大の原因は、私たちが長年慣れ親しんできた物理的な「モノ」に対する所有権と、デジタルコンテンツの利用を許諾する利用権(ライセンス)、そして創作物を保護する著作権という、異なる権利の概念が混同されている点にあります。
例えば、書店で物理的な本を購入するとき、私たちはその本の所有権を得ます。この本は私たちの所有物であり、読み返すことも、友人に貸すことも、中古書店に売却することも自由です。しかし、本の内容、すなわち著者が創造した物語や知識に対する著作権は、依然として著者や出版社が保持しています。購入者が勝手に本の内容をコピーして販売したり、インターネットに公開したりすることは許されません。ここには、物理的な媒体の所有権と、情報としての内容の著作権という二つの異なる権利が存在します。
一方、電子書籍をダウンロード購入した場合、状況はより複雑です。私たちは対価を支払って「購入」したと感じますが、法的に得ているのは、特定のプラットフォーム上でコンテンツを閲覧するための利用権に過ぎません。プラットフォームがサービスを終了すれば、購入したはずの電子書籍が読めなくなる可能性がありますし、他人に貸与したり売却したりすることも通常はできません。ここでの「購入」は、物理的な所有権の移転とは根本的に異なる契約なのです。
NFTは、このデジタル時代特有の曖昧な「所有」の状況に対し、ブロックチェーン技術を用いて一つの解を提示しようとする試みです。NFTは、デジタルデータに対して唯一無二の証明書を発行し、誰がその真正なデータを所有しているかを明確に記録します。これにより、これまで困難だったデジタルアイテムの希少性や真正性を証明し、物理的なモノと同じように取引や移転が可能になる道を開きました。
しかし、NFTがもたらす「デジタル所有権」は、従来の物理的な所有権とも、単なる利用権とも異なります。NFTを購入しても、必ずしもそのデジタルコンテンツの著作権が移転するわけではありません。この新しい所有の形を正しく理解するためには、まず「所有権」と「利用権」が歴史的にどのように形成され、どのように区別されてきたのか、そしてデジタル技術の進化がそれらの概念にどのような影響を与えてきたのかを紐解く必要があります。
前編では、人類がどのように所有権という概念を獲得してきたのか、そして産業革命以降の著作権やライセンスといった無体財産権がどのように発展してきたのかを概観します。さらに、デジタル時代における「モノ」と「データ」の所有権の違いを明確にし、所有権が社会に果たす役割について考察します。後編では、これらの歴史的・概念的整理を踏まえた上で、NFTの技術、具体的なユースケース、そしてNFTが直面する課題と未来の展望について深く掘り下げていきます。
古代〜近代:土地・不動産の所有権の確立
所有権という概念は、今日私たちが当たり前のように享受している権利ですが、決して普遍的なものではありません。それは人類の長い歴史の中で、社会の変遷、経済活動の発展、そして政治的な闘争を経て徐々に形成され、確立されてきた社会的な合意であり、法的な制度です。
所有権の歴史を理解する上で最も重要な対象は「土地」です。土地は移動させることができず、生産活動の基盤であり、人類の生存に不可欠な資源であったため、これを誰がどのように支配し、利用するかが、社会秩序を形成する上で決定的な意味を持ちました。
古代社会において、土地や資源は特定の個人が排他的に所有する対象ではなく、部族や共同体が共有するものでした。しかし、農耕の開始と共に、人類は定住生活を営むようになります。自分が労力を投じて耕した土地から得られる収穫は自分のものであり、他者にそれを奪われないようにしたいという欲求が、所有権を生み出しました。
近代的な所有権の基礎を築いたのは、古代ローマでした。ローマ法は、所有権(dominium)を「物に対する完全な支配権」として定義しました。これには、物を使用する権利、物から収益を得る権利、そして物を処分する権利が含まれます。
重要なのは、ローマ法が所有権を個人に帰属する絶対的かつ排他的な権利として捉えた点です。この概念は後のヨーロッパ諸国の法制度に多大な影響を与えることになります。
中世ヨーロッパの封建社会では、所有権は再び複雑化しました。全ての土地は理論上国王に帰属し、国王が諸侯に土地を与え、最下層の農民が土地を耕作するという階層構造が形成されました。これは、一つの土地に対して複数の主体が異なる権利を重層的に持ち合う「分裂した所有権」と呼べる状態でした。
この封建的な土地所有のあり方が大きく変容し、近代的な所有権が確立される契機となったのは、近世から近代にかけての市民革命でした。啓蒙思想家たちは、所有権を人間の生まれながらの自然権であり、自由と平等の基盤であると主張しました。
フランス革命で採択された「人間と市民の権利の宣言」(1789年)は、「所有権は、神聖かつ不可侵の権利である」と宣言しました。これは、封建的な特権を打破し、個人が自由に財産を所有・取引できる権利を保障するものでした。
その後、近代的な所有権は、特定の対象(主に土地や動産といった有体物)に対する排他的かつ絶対的な支配権として確立されました。そして、この権利を社会全体で保証するために、登記制度という重要なシステムが整備されました。
不動産登記は、どの土地を誰が所有しているかという情報を公の帳簿に記録し、公開する制度です。これにより、所有権の移転が安全かつ円滑に行われるようになり、市場経済が機能するための不可欠なインフラとなりました。
産業革命以降:特許・著作権・ライセンスの仕組み
近代的な所有権は、主に有体物を対象としていましたが、産業革命はこれまでの枠組みでは捉えきれない、新しい形の財産を生み出しました。それは、人間の知的な創造活動から生み出される無体物、すなわちアイデア、技術、芸術作品といったものです。これらの無体財産は、物理的な形態を持たないため、従来の所有権の概念をそのまま適用することが困難でした。
もし、こうした無体財産が何の保護も受けられなければ、発明家や作家が努力を投じても、すぐに他者に模倣されてしまい、創作活動の意欲は失われるでしょう。これは、社会全体の技術進歩や文化の発展を阻害することにつながりかねません。
そこで、こうした知的な創造活動を保護し、イノベーションを促進するために、知的財産権(Intellectual Property Rights)という新しい権利の体系が整備されることになりました。その代表格が特許権と著作権です。
特許権は、新しい技術的な発明を保護するための権利です。発明の内容を社会に公開することと引き換えに、一定期間の独占権が与えられます。これにより、発明者は投資を回収し利益を得る機会が保障されると同時に、公開された技術情報が社会全体の知識として蓄積されます。
一方、著作権は、文学、音楽、美術といった文化的・芸術的な創作物を保護するための権利です。1710年にイギリスで制定された「アン女王法」は、著作者に対して、その著作物を複製・出版する排他的な権利を一定期間与えることを定めました。これは、著作物を著者の財産として認め、その権利を保護する世界初の近代的な著作権法とされています。
特許権も著作権も、無体物に対する排他的な支配権という点で、有体物の所有権と類似しています。しかし、決定的に異なるのは、その権利が時間的に有限であるという点です。
知的財産権は一定の保護期間が経過すると消滅し、その発明や著作物は公共財産(パブリックドメイン)となり、誰もが自由に利用できるようになります。これは、創作者個人の利益と、社会全体の利益のバランスを取るための仕組みです。
そして、これらの知的財産権の確立は、ライセンス(利用許諾)という新しいビジネスモデルを生み出しました。
ライセンス契約とは、権利者(ライセンサー)が、特定の条件(期間、地域、利用方法、対価など)のもとで、他者(ライセンシー)に対してその知的財産の利用を許可する契約のことです。これにより、知的財産の流通が促進され、多様な製品やサービスが生み出されるようになりました。
デジタル時代:音楽CDと配信サービス、DRM、サブスクモデル
20世紀末から21世紀にかけてのデジタル技術の急速な発展とインターネットの普及は、情報の流通と消費のあり方を根底から変えました。この変化は、所有権と利用権の関係性にも大きな影響を与え、私たちが「モノ」や「コンテンツ」をどのように所有し、利用するのかという認識を大きく揺さぶりました。この変遷を理解する上で、音楽産業の事例は非常に学びとなります。
アナログ時代、音楽はレコードやカセットテープといった物理的な媒体に記録されて販売されていました。消費者がレコードを購入するという行為は、物理的な円盤の所有権を得ることを意味しました。所有者は、レコードを再生するだけでなく、友人に貸したり、中古店に売却したりすることも自由でした。
1980年代に登場したCDもまた物理的な媒体であり、その取引はレコードと同様、所有権の移転として扱われました。しかし、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、デジタル音声圧縮技術(MP3など)とインターネットが普及し、状況は一変します。デジタルデータは、品質を劣化させることなく、瞬時に無数のコピーを作成し、インターネットを通じて世界中に送信することが可能になりました。
この事態に対抗するため、音楽産業は二つの方向で対応を進めました。
一つは、デジタル著作権管理(DRM: Digital Rights Management)技術の導入です。DRMは、デジタルコンテンツの不正コピーを防止・制限するための技術ですが、正規に購入したはずのコンテンツの利用方法が過度に制限されるなど、消費者の利便性を著しく損なうという問題も引き起こしました。
もう一つの対応は、正規の音楽配信サービスの開始です。その先駆けとなったのがApple社のiTunes Music Storeです。しかし、このダウンロード販売モデルにおいても、消費者が得ている権利は、多くの場合、コンテンツを特定の条件の下で利用するための利用権(ライセンス)に過ぎませんでした。物理的なCDの所有権とは異なり、再販や譲渡は認められません。
そして、2010年代に入ると、音楽消費の主流はサブスクリプション(定額制)モデルへと移行しました。SpotifyやApple Musicといったサービスは、月額料金を支払うことで膨大な楽曲ライブラリに無制限にアクセスできるというものです。このモデルにおいて、消費者はもはやコンテンツを所有してはいません。得ているのは、サービスが提供されている期間中、プラットフォーム上のコンテンツにアクセスし、利用するためのアクセス権です。料金の支払いを止めれば、一切のコンテンツにアクセスできなくなります。
この流れは、音楽だけでなく、映画、書籍、ゲーム、ソフトウェアといった他のデジタルコンテンツ分野でも同様に進行しました。
多くの分野で「所有から利用へ」のシフトが加速しています。この変化は、多くの利便性をもたらした一方で、「デジタル所有」の概念を極めて曖昧なものにしました。
私たちの「所有感」と、法的な権利の実態との間には、大きな乖離が生じているのです。
「モノ」と「データ」の所有権の違い
NFTがもたらす「デジタル所有権」を考える前提として、従来の法制度における「モノ(有体物)」の所有権と、「データ(無体物)」の扱いの違いについて、改めて整理しておく必要があります。
日本の民法をはじめ、多くの国の法制度は、物理的な現実世界を前提として構築されてきました。民法上、所有権は「有体物」に対してのみ成立するものです。
有体物とは、空間の一部を占め、人間が五感で認識できるものを指します。これらの有体物は、以下の特徴を持っています。
排他性(Exclusivity): ある有体物は、同時に一つの場所にしか存在できません。
有限性・希少性(Scarcity): 有体物は有限であり、生産にはコストがかかります。
移転可能性(Transferability): 物理的な引き渡しや登記によって、所有権を他者に移転することができます。
一方、デジタルデータは、情報が電磁的に記録されたものであり、物理的な実体を持ちません。したがって、民法上の「物(有体物)」には該当せず、原則として所有権の対象とはなりません。データは、有体物とは対照的な特徴を持っています。
非排他性(Non-exclusivity): 無数の人々が同時に利用することが可能です。
複製容易性・無限性(Replicability): ほとんどコストをかけずに、品質を劣化させることなく、完璧な複製を作成することができます。
移転の曖昧さ: 他者に送信した場合、「移転」したのか「複製」したのかが曖昧になります。
このように、従来の枠組みでは、デジタルデータは「所有」の対象ではなく、「利用」の対象として扱われてきました。私たちがデジタルデータを「持っている」と感じるのは、多くの場合、データが記録されている物理的な媒体の所有権を持っているか、あるいはデータにアクセスするための利用権を持っているかのいずれかです。
この「モノ」と「データ」の法的な扱いの違いは、デジタル経済の発展において様々な課題を生み出してきました。
例えば、中古市場の不在です。物理的な本やCDは、所有権の移転として中古市場で売買できますが、デジタルコンテンツの場合、多くは利用権の取引であり、利用規約で再販や譲渡が禁止されているため、中古市場が成立しません。
所有権が社会に与える信頼と安定性
「所有権」という制度は、なぜ人類社会にとってこれほどまでに重要なのでしょうか。それは、社会秩序を維持し、経済活動を促進し、個人の自由と尊厳を保障するための、極めて重要な社会的・経済的インフラだからです。
第一に、所有権は社会の平和と秩序維持に貢献します。もし所有権が確立されていなければ、人々は常に他者から財産を奪われるリスクに晒されることになり、社会は混乱と暴力に支配されてしまうでしょう。所有権制度は、財産に対する排他的な支配権を法的に保障し、他者による侵害を禁止することで、紛争を抑制し、社会の安定をもたらします。
第二に、所有権は経済活動の効率性を高め、経済発展を促進します。人々が努力して得た成果が自分のものになることが保障されていれば、より多くの努力と投資を行う意欲が湧きます。もし所有権が不安定であれば、長期的な視野に立った投資は行われず、経済は停滞してしまうでしょう。
第三に、所有権は市場経済における取引の安全と円滑化を可能にします。市場は、財やサービスの交換によって成り立っていますが、取引の対象となる財が誰に帰属しているかが明確でなければ、安心して取引を行うことができません。所有権制度は、権利の所在を明確にし、取引の安全性を高めます。
このように、所有権制度は、私たちの社会と経済が機能するための根幹をなすシステムです。それは、長い歴史の中で洗練されてきた、信頼と安定性を生み出すための社会的な合意です。
しかし、デジタル時代への移行に伴い、この強固なはずの所有権の基盤が揺らぎ始めています。私たちの生活や経済活動において、デジタルデータの重要性が増大しているにもかかわらず、それに対する明確な所有権は確立されていません。私たちのデジタル資産やアイデンティティは、特定のプラットフォーム事業者の管理下にあり、与えられているのは利用権に過ぎません。
web3とNFTは、このデジタル時代における所有権の不在という課題に対して、ブロックチェーン技術を用いることで解決しようとする試みです。ブロックチェーンを用いることで、デジタルデータに対して、唯一性と真正性を証明し、誰がそれを排他的に「所有」しているかを明確に記録することが可能になります。
これは、物理的な世界において登記制度が果たしてきた役割を、デジタル空間において、中央集権的な権威に依存することなく実現しようとする試みと言えるでしょう。
後編ではこのNFTについて詳しく見ていきます。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら