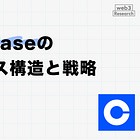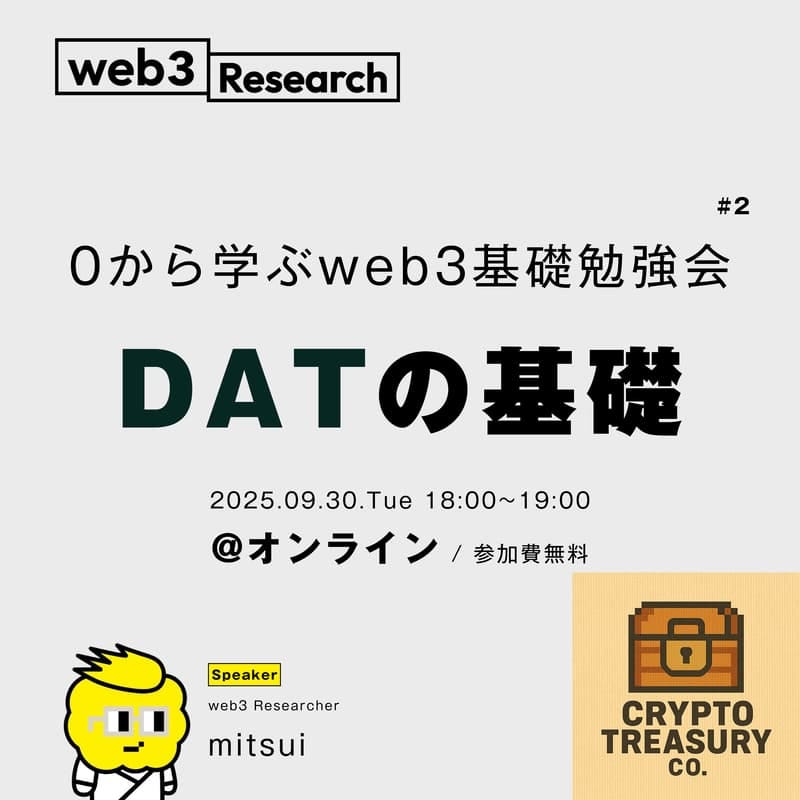【9/23(火)~24(水)のweb3ニュース10選】RainbowはRNBWトークンをリリースする予定 / Plasmaはステーブルコインに特化したネオバンクを立ち上げ / ヴィタリックはBaseの分散化を擁護 etc..
10の主要ニュースを解説。
こんにちは.
web3リサーチャーのmitsuiです。
平日18時は主要ニュース10個ピックアップして解説します。
Rainbowは第4四半期に非管理型暗号ウォレット向けRNBWトークンをリリースする予定
Rainbowは月曜日、年末までにネイティブRNBWトークンをウォレットに導入する予定であると発表
Consensysが支援するMetaMaskウォレットがネイティブトークンの発行に取り組んでいると発表したわずか数日後に行われた
Rainbowのトークン発表は、リアルタイム価格設定、即時残高更新、ウォレットアプリの価格チャート機能の改善など、一連の改善策の一環として行われた
CFTCはデリバティブ取引業者がステーブルコインを担保として差し入れることを可能にするトークン化イニシアチブを開始
商品先物取引委員会(CFTC)はデリバティブ市場でトークン化された担保(ステーブルコインを含む)を利用する取り組みを開始すると、キャロライン・D・ファム暫定委員長が火曜日に発表
リップル社のステーブルコイン担当SVP、ジャック・マクドナルド氏は、先物やスワップなどの金融契約においてトークン化された担保を利用することで、「効率性と透明性」を高め、新興金融技術への適応を図る可能性があると主張した
イーサリアムETFは現在、スポット市場の取引量の15%を占めており、ローンチ時の3%から増加している
ETF ベースのエクスポージャーへの移行は、トークンの直接所有ではなく、ETH への規制されたアクセスを好む機関投資家や個人投資家の増加を反映している
スポットイーサリアムETFの取引量は全体の15%に達した
セキュリタイズ、リップルのステーブルコインを使用してブラックロックのBUIDLとヴァンエックのVBILLトークン化ファンドのオフランプを開始
BUIDLおよびVBILLオンチェーンファンドの保有者は、Securitizedによる新しいオフランプの展開に伴い、トークン化された株式をRLUSDに交換できるようになる
RLUSDは、ニューヨーク州金融サービス局の信託憲章に基づいて2024年後半に開始され、「エンタープライズユーティリティ向けに特別に構築された」ステーブルコイン
FoldはStripeとVisaと提携し、ビットコインクレジットカード報酬をレジに導入
Fold は、Stripe Issuing を活用した、購入ごとにビットコイン報酬を支払う Visa クレジットカードを発表
このカードは購入金額に対して最大3.5%のキャッシュバックを提供する
Plasmaブロックチェーン、ステーブルコインに特化したネオバンクを立ち上げ
Plasma は Plasma One を発表し、これをステーブルコイン専用にネイティブに構築された初のネオバンクと呼んだ
ローンチ時には、Plasmaネットワーク内での手数料無料のUSDT送金、カード利用によるポイント還元、そして数分でバーチャルカードを発行できるオンボーディング機能を提供する
コインベースがUSDCレンディングサービス開始、年10.8%の利回り提供
コインベースが、米ドル建てステーブルコインUSDCのレンディングサービス開始を9月18日に発表
同サービスは年10.8%の利回りを提供するという
これまでもコインベースでは、USDC保有時に年4.1%(コインベースワン会員は4.5%)の利回りを得られる「パッシブ報酬」を提供していたが、今回発表の新サービスではこれを大幅に上回る利回りとなる
ユーザーがコインベース上でUSDCを預け入れると、コインベースがスマートコントラクトウォレットを自動で作成し、ステーキハウス・ファイナンシャルが管理するオンチェーン金庫(vault)を介してモルフォに接続される
TISとgC Labsのヒノデテクノロジーズ、L1チェーン「Plasma」と戦略パートナー契約
ヒノデテクノロジーズ(Hinode Technologies)とレイヤー1ブロックチェーン「Plasma」の日本市場における戦略パートナー契約締結が9月16日に発表された
ヒノデテクノロジーズは今回の締結を通じて、プラズマの日本における啓蒙活動や事業提携を積極的に支援していくという
Clankerの創設者は、RainbowのBaseトークンローンチパッド買収の申し出を拒否した
Clankerの創設者Jack Dishman氏は、イーサリアムウォレットRainbowからの買収提案を拒否した
レインボーは、今後供給予定のRNBWトークンの4%を提供することでClankerを買収することを提案していた
おすすめ記事2012年創業の上場企業Coinbaseは、現物取引に加えCustody・ステーキング・USDC連携・デリバティブ・自社L2「Base」で“Everything Exchange”化を推進。
収益は「取引(高ボラ)」と「サブスク&サービス(USDC利息・ステーキング・Custody等の安定収益)」の二本柱へ転換し、2022年の市況悪化・レイオフを機に非取引収益を強化。
ユーザー体験を起点にオンチェーン経済を拡大し、取引依存を下げつつ高収益プロダクト(デリバティブ等)と新アセットのトークン化で長期の成長フライホイールを回す。
ヴィタリック・ブテリン氏はBaseの分散化を擁護し、レイヤー2ネットワークは「資金を盗むことはできない」と述べている
🌱 ニュースの概要
Ethereum共同創設者のヴィタリック・ブテリン氏は、Coinbaseが開発を主導するL2「Base」に関して、分散化への懸念に対して擁護の姿勢を示しました。彼は「レイヤー2ネットワークは資金を盗むことはできない」と述べ、ユーザー資産の安全性と、EthereumのL1に依存した設計上の制約を強調しました。
📗 前提知識
Base:Coinbaseが育成したEthereumレイヤー2ネットワーク。OP Stackを基盤に構築。
レイヤー2:Ethereum L1の上で動作し、スケーラビリティや手数料削減を目的とするネットワーク。
分散化の懸念:開発主体や運営権限が特定企業に偏る場合、検閲や資金リスクが議論される。
Vitalikの立場:Ethereumエコシステム全体の分散化とセキュリティを長年強調。
👀 注目すべき点・詳細解説
ブテリン氏は、BaseのようなL2はEthereum L1のセキュリティに依存しているため、資金を持ち逃げする能力を本質的に持たないと説明。
ただし「検閲の可能性」や「アップグレード権限の集中」など、分散化の度合いには注意が必要と認めている。
Coinbaseが商業的にBaseを拡大する中で、分散化への取り組みと透明性が重要な論点に。
L2の分散化設計(Sequencerの多様化、ガバナンスの移行など)が引き続き業界で議論されている。
📈 今後の展望
Baseは今後Sequencerの分散化やガバナンスの民主化を進めるかが注目される。
Ethereumコミュニティ全体では、L2のセキュリティ保証と分散化基準をどう評価するかが課題。
Coinbaseの影響力が強まる一方で、Vitalikの発言は「L2は根本的に安全」という安心材料を提供。
今後の規制環境下で、中央集権的運営 vs 分散化の実装のバランスがますます重要になる見込み。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
🗓️イベント日程
DAT(Digital Asset Treasury)について、0から解説するウェビナーです。
DATは端的に言えば、メタプラネットのようなクリプトをとにかく購入しまくる上場企業で、BTCトレジャリーカンパニーやクリプトトレジャリーカンパニーとも言われます。最近は”DAT”という名称が定着しつつあるので、それを使いました。
・なぜ流行っているのか?
・どうやって資金調達しているのか?
・事業スキームとは?
・BTC以外のSOL、ETHの盛り上がりは?
・さらにそれ以外のENA、IP、HYPE等の盛り上がりは?
etc...
0から理解できるような勉強会を想定しています。
参加費無料でオンライン開催ですので、ぜひお気軽にご参加ください!
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら