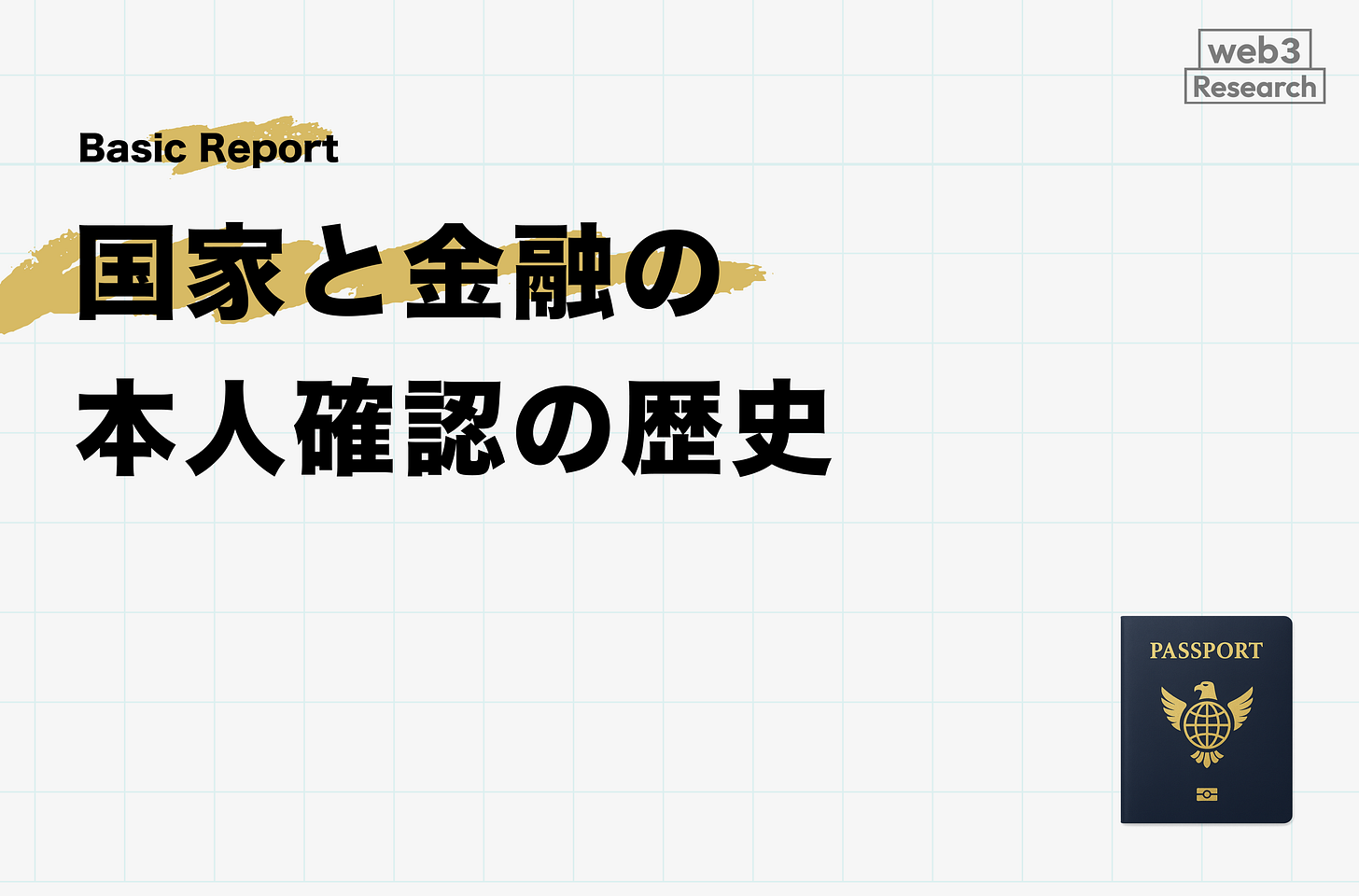おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎レポートを更新しています。今週は「パスポートとKYC」について解説します。
「あなたは誰か」を証明することの重み
パスポートの歴史
金融における本人確認の進化
KYCの実務
国境を越える際の不便さ
問題点:国家独占・排除される人々・国際金融の壁
前編のまとめ
「あなたは誰か」を証明することの重み
私たちが社会生活を営む上で、最も基礎的かつ重要な問いの一つは「あなたは誰か」ということです。この問いに対する答え、すなわち個人のアイデンティティを証明することは、想像以上に重い意味を持っています。
銀行口座の開設、携帯電話の契約、病院での受診、不動産の賃貸、そして国境を越えた移動。これら日常的な活動のほぼ全てにおいて、私たちは公的な身分証明書の提示を求められます。これは、私たちが社会システムの中で確かに存在し、権利を行使し、義務を負う主体であることを確認するための手続きです。
この「身分証明」のプロセスは、社会の信頼と秩序を維持するために不可欠な役割を果たしてきました。特に金融の世界では、取引相手が誰であるかを正確に把握すること(KYC: Know Your Customer)が、不正行為の防止や健全な市場の維持に直結します。もし誰もが匿名で自由に高額な取引を行えるとしたら、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与といった犯罪行為を抑制することは極めて困難になるでしょう。
一方で、この身分証明システムは、国家という中央集権的な管理者に強く依存しています。私たちが持つパスポートや運転免許証は、国家がその真正性を保証することによって初めて効力を持ちます。この構造は、効率的である反面、いくつかの根本的な課題を抱えています。
第一に、国家による管理は、個人のプライバシーや自由に対するリスクを孕んでいます。個人の情報が一元的に管理されることで、意図しない監視や情報漏洩の危険性が高まります。また、国家の都合によって個人のIDが剥奪されたり、移動が制限されたりする可能性も否定できません。
第二に、現在のIDシステムは、世界中のすべての人々を包摂しているわけではありません。世界銀行のデータによれば、世界には依然として約10億人が公的な身分証明書を持たずに生活していると推定されています。これらの人々は、基本的な社会サービスや金融サービスから排除され、経済的な自立の機会を奪われています。彼らにとって、「あなたは誰か」を証明できないことは、社会からの疎外を意味します。
第三に、グローバル化が進む現代において、国家ごとに分断されたID管理システムは大きな摩擦を生んでいます。国境を越えて活動する際、私たちはその都度、異なる国の基準に基づいた煩雑な本人確認手続きを強いられます。海外での銀行口座開設や国際送金には、多大な時間とコストがかかります。これは、シームレスな国際経済活動を阻害する大きな要因となっています。
こうした中央集権的なID管理システムの限界が認識される中、新たな解決策として注目を集めているのが、ブロックチェーン技術を基盤としたweb3の思想です。
web3は、特定の管理者やプラットフォームに依存しない、分散化されたインターネットの世界を目指しています。この思想をアイデンティティ管理に応用することで、個人が自らの情報を主体的にコントロールできる「自己主権型ID(SSI: Self-Sovereign Identity)」の実現が期待されています。
今回の連載は、前後編の二部構成で、パスポートとKYCの歴史を紐解きながら、現在のIDシステムが抱える課題と、web3がもたらす未来のアイデンティティ像について考察します。
前編では、国家がどのようにして個人の身元を管理するようになったのか、そして金融の世界でKYCがどのように進化してきたのかを概観し、現行システムの問題点を明らかにします。
パスポートの歴史
私たちが海外へ渡航する際に必ず携帯するパスポート(旅券)。これは単なる旅行書類ではなく、国際社会において個人が持つ「国籍」と「身元」を証明する、最も強力な公的文書です。しかし、パスポートが現在のような形になるまでには、長い歴史的な変遷がありました。その歴史は、国民国家の成立、戦争、そして技術の進化と密接に関わっています。
国際社会での登場
パスポートの起源は、古くは古代エジプトやローマ帝国時代にまで遡ることができると言われています。当時の支配者たちは、使者や商人が安全に領土を通過できるよう、通行許可証や身分を保証する文書を発行していました。
中世ヨーロッパにおいても、君主や領主が発行する「保護状」や「安全通行証(Safe-conduct)」が存在しました。これらは、保有者が敵対勢力から攻撃を受けずに移動できるよう保証するものであり、現代のパスポートの原型と言えます。
「パスポート(Passport)」という言葉自体は、文字通り「港(Port)を通過(Pass)する」という意味から来ており、元々は都市の城門や港を出入りするための許可証を指していました。しかし、この時代の通行証は、体系的に発行されたものではなく、発行者の権威に依存した属人的なものでした。
近代的なパスポート制度への転換点は、19世紀から20世紀初頭にかけての国民国家の成立と、それに伴う国境管理の強化です。フランス革命以降、ヨーロッパでは「国民」という概念が生まれ、国家は自国民を把握し、管理する必要性に迫られました。
そして、パスポートの歴史において決定的な出来事となったのが、第一次世界大戦(1914年~1918年)です。
戦争が始まると、各国は安全保障上の理由から、スパイの潜入や敵国人の移動を防ぐため、厳格な出入国管理体制を敷きました。それまで比較的自由であった国境間の移動は制限され、パスポートの携帯が義務付けられるようになりました。この時期に導入されたパスポート制度は、戦争が終わった後も「一時的な措置」として継続され、やがて恒久的な制度として定着していきました。
第一次世界大戦後、国際連盟はパスポート制度の標準化に取り組みました。1920年に開催された会議では、パスポートの様式や記載事項に関する国際的な基準が定められました。これにより、各国が発行するパスポートが国際的に通用する基盤が整いました。
この時期にもう一つ重要な進化がありました。それは、写真付き身分証明書の導入です。初期のパスポートには、保有者の身体的特徴が文章で記載されていましたが、これでは正確な本人確認が困難でした。写真技術の普及に伴い、パスポートに顔写真を貼付することが一般的となり、本人確認の精度が飛躍的に向上しました。
国境管理の役割
パスポートの最も本質的な役割は、国境管理です。国家は、自国の領域に出入りする人々を管理し、誰が自国民であり、誰が外国人であるかを区別する主権を有しています。パスポートは、この国家主権を行使するための最も基本的なツールとして機能します。
国境管理の目的は多岐にわたります。
第一に、安全保障です。テロリスト、犯罪者、スパイといった危険人物の入国を防ぎ、国内の治安を維持することは、国家にとって最優先の課題です。パスポートによる身元確認は、そのための第一関門となります。
第二に、移民管理です。国家は、自国の労働市場や社会福祉制度への影響を考慮し、外国人の入国や滞在を管理する必要があります。パスポートと連携して機能するのが、ビザ(査証)制度です。パスポートは、その審査の前提となる国籍や身元を証明する役割を果たします。
第三に、自国民の保護です。パスポートには、発行国が保有者に対して「支障なく旅行させ、かつ、必要な保護扶助を与えるよう」関係諸官に要請する文言が記載されています。これは、海外でトラブルに巻き込まれた際に、自国の外交機関による保護を受ける権利を保証するものです。
20世紀後半以降、航空機による大量輸送が一般化し、国際的な人の移動は爆発的に増加しました。これに伴い、国境管理の効率化とセキュリティ強化が喫緊の課題となりました。
国際民間航空機関(ICAO)は、パスポートの国際標準化を推進し、偽造防止技術の開発を主導してきました。1980年代には、機械読み取り式パスポート(MRP)が導入され、出入国審査の自動化が進みました。
そして、21世紀に入り、特に2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降、セキュリティ強化の要請は一層強まりました。これに応える形で登場したのが、ICチップを搭載した「eパスポート(バイオメトリック・パスポート)」です。ICチップには、顔画像や指紋といった生体情報が記録されており、より厳格な本人確認が可能となりました。これにより、他人へのなりすましやパスポートの偽造は極めて困難になりました。
パスポートが持つ「信用」の本質は、発行国に対する信頼にあります。私たちが他国のパスポートを受け入れるのは、その発行国が適切な手続きを経て身元を確認し、その真正性を保証していると信頼しているからです。パスポートの歴史は、国家が国民を管理し、国境を守るための絶え間ない努力の歴史でもあるのです。
金融における本人確認の進化
金融の世界は、信頼と信用によって成り立っています。この信頼の基盤を築く上で、取引相手が誰であるかを正確に把握することは極めて重要です。金融における本人確認の歴史は、古くからの対面取引における属人的な信用から、グローバルな金融システムを支える厳格な規制へと進化してきました。
銀行口座開設の初期
近代的な銀行制度が始まった当初、本人確認は極めて属人的なものでした。地域社会に根ざした銀行は、顧客との対面取引を原則としていました。銀行員は、顧客の顔や名前、職業、評判を知っており、それに基づいて取引の可否を判断していました。新規に口座を開設する際には、既存の顧客からの紹介や、地域の名士による保証が求められることもありました。
この時代の本人確認は、形式的な書類よりも、人間関係や社会的信用に重きを置いていました。これは、取引の規模が比較的小さく、地域コミュニティが緊密であった時代には有効な方法でした。
しかし、経済活動が活発化し、取引の範囲が拡大するにつれて、属人的な信用だけに頼ることは難しくなっていきました。19世紀から20世紀にかけて、各国で中央銀行制度が整備され、銀行業に対する規制が強化されていく中で、銀行は顧客の情報を記録し、管理するようになりました。口座開設時に氏名、住所、職業などを記載させ、公的な身分証明書の提示を求めることが一般的になっていきました。
それでも、20世紀半ばまでの金融取引における本人確認は、現在ほど厳格なものではありませんでした。匿名や仮名での口座開設が可能な国も存在し、特にスイスの銀行秘密法は、顧客のプライバシーを強力に保護することで知られていましたが、同時に不正な資金の隠蔽場所としても利用されることになりました。
マネーロンダリング対策の登場
金融における本人確認の歴史が大きく転換したのは、1970年代以降、国際的な組織犯罪、特に麻薬取引による収益の増大が深刻な社会問題となったことでした。犯罪組織は、不正に得た膨大な資金を合法的な経済活動に紛れ込ませることで、その出所を隠蔽しようとしました。これがいわゆるマネーロンダリング(資金洗浄)です。
マネーロンダリングは、金融システムの健全性や国家の安全保障をも脅かす重大な脅威となります。これに対抗するため、各国政府は金融機関に対する規制を強化し始めました。
1970年、アメリカでは銀行秘密法(BSA)が制定され、一定額以上の現金取引の報告が義務付けられました。これが、現代的なマネーロンダリング対策(AML: Anti-Money Laundering)の始まりと言われています。
そして、国際的な協力体制を構築するために、1989年にFATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)が設立されました。FATFは、マネーロンダリング対策及びテロ資金供与対策(CFT: Combating the Financing of Terrorism)に関する国際基準を策定し、各国にその実施を勧告する政府間機関です。
FATFが提唱した最も重要な概念の一つが、KYC(Know Your Customer:顧客を知る)です。KYCは、金融機関が顧客の身元を正確に特定し、その顧客が行う取引の性質や目的を理解することを求めるものです。これにより、金融機関は不正な取引を検知し、防止する責任を負うことになりました。
FATFの勧告に基づき、各国は次々と法律を整備し、金融機関に対するKYCの義務化を進めました。日本においても、本人確認法(現在の犯罪収益移転防止法)が制定され、厳格な本人確認が求められるようになりました。
2001年のアメリカ同時多発テロ事件は、KYCの重要性を再認識させる出来事となりました。テロリストが金融システムを利用して資金を調達していたことが明らかになり、テロ資金供与対策の強化が国際的な急務となりました。FATFの役割はAMLからAML/CFTへと拡大され、KYCは単なる犯罪対策だけでなく、安全保障上の重要な柱として位置づけられるようになりました。
こうして、かつては属人的な信用に基づいていた金融取引は、厳格な法規制に基づくシステマティックな本人確認プロセスへと変貌を遂げました。KYCは、グローバルな金融システムが機能するための不可欠なインフラとなったのです。
KYCの実務
KYCは単なるスローガンではなく、金融機関が日々実践しなければならない具体的な業務プロセスです。その内容は多岐にわたり、技術の進化や規制の強化に伴って常にアップデートされています。ここでは、現代の金融機関で行われているKYCの実務について具体的に見ていきます。
本人確認書類
KYCプロセスの第一歩は、顧客の身元を特定し、検証することです。これを「本人特定事項の確認」と呼びます。具体的には、氏名、住所、生年月日を確認します。
この確認のために最も重要な役割を果たすのが、公的な本人確認書類です。日本では、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カードなどが主要な本人確認書類として認められています。これらの書類は、国家機関が発行し、偽造防止技術が施されているため、高い信頼性を持っています。
金融機関は、これらの書類の提示を受け、記載内容を確認するだけでなく、その真正性を検証する義務があります。特に重要なのが、顔写真による本人確認です。提示された書類の顔写真と、目の前にいる顧客が同一人物であることを確認します。
近年、オンラインで完結する金融サービスが普及する中で、eKYC(electronic KYC:電子的本人確認)の重要性が高まっています。eKYCでは、スマートフォンで本人確認書類と自身の顔写真を撮影し、送信することで本人確認を行います。この際、書類の厚みやホログラムの反射を確認したり、リアルタイムでの動画撮影を求めたりすることで、不正ななりすましを防ぐ工夫が凝らされています。
また、本人確認書類の真贋判定も重要なプロセスです。偽造された身分証明書を見破るため、金融機関の窓口担当者は専門的な研修を受けたり、専用の鑑定機器を使用したりしています。
住所・職業・取引目的の確認
KYCは、単に顧客の身元を特定するだけでは終わりません。FATFの勧告では、「リスクベース・アプローチ」が推奨されています。これは、顧客のリスクに応じて、適切な管理措置を講じるという考え方です。そのために行われるのが、CDD(Customer Due Diligence:顧客デューデリジェンス)です。
CDDでは、本人特定事項に加えて、顧客の属性に関する様々な情報を収集し、リスク評価を行います。
住所の確認: 住所は、顧客の居住実態を把握し、地理的なリスク(例:紛争地域や規制の緩い国との関連性)を評価するために重要です。本人確認書類に記載された住所が最新のものであるかを確認します。
職業・事業内容の確認: 顧客の職業や事業内容は、その収入源や取引の性質を理解するために不可欠です。例えば、現金取引が多い業種は、マネーロンダリングのリスクが高いと判断されることがあります。また、政治的に重要な地位にある人物(PEPs: Politically Exposed Persons)は、汚職や贈収賄のリスクがあるため、より厳格な審査(EDD: Enhanced Due Diligence)が求められます。
取引目的の確認: なぜ口座を開設するのか、どのような取引を行う予定なのかを確認します。もし、申告された目的と実際の取引内容が大きく乖離している場合は、不正な取引の兆候として警戒する必要があります。
これらの情報は、口座開設時に収集されるだけでなく、定期的に見直され、最新の状態に保たれなければなりません。これを「継続的な顧客管理」と呼びます。
マイナンバー(日本の場合)
日本では、2016年からマイナンバー(個人番号)制度が導入されました。マイナンバーは、国民一人ひとりに割り当てられた固有の番号であり、社会保障、税、災害対策の分野で情報連携を行うために利用されています。
金融分野においても、マイナンバーの利用が進められています。現在、銀行口座や証券口座の開設時には、マイナンバーの届け出が求められます。これにより、金融機関は顧客の情報をより正確に把握し、税務当局への報告などを効率的に行うことができます。
マイナンバーは、究極の本人確認情報とも言えます。もしマイナンバーの利用が完全に義務化されれば、複数の金融機関に分散している個人の資産状況を把握することが容易になり、脱税や不正受給の防止に役立つと期待されています。
しかし、マイナンバー制度には、プライバシー保護の観点からの懸念も根強く存在します。個人の情報が一元的に管理されることによる監視社会化のリスクや、情報漏洩が発生した場合の被害の大きさなどが指摘されています。そのため、金融機関はマイナンバー情報を極めて機密性の高い情報として扱い、厳重なセキュリティ対策を講じることが求められています。
国境を越える際の不便さ
グローバル化が進み、人、物、金が国境を越えて移動することが当たり前になった現代社会。しかし、こと金融取引に関しては、依然として大きな壁が存在します。その主な原因の一つが、国家ごとに分断されたKYCシステムです。国際的な活動を行う個人や企業は、この分断によって生じる様々な不便さや摩擦に直面しています。
再認証の手間
私たちが直面する最も明白な不便さは、国境を越えるたびに、あるいは新しい国で生活を始めるたびに、自身のアイデンティティを繰り返し証明しなければならない「再認証」の手間です。
最大の問題は、KYCの要件が国ごとに異なることです。ある国で有効な本人確認書類が、別の国では認められないことがあります。パスポートが最も汎用性の高い書類ですが、それに加えて、現地の住所を証明する書類(公共料金の請求書や賃貸契約書など)の提出が求められることが多く、これが大きなハードルとなります。
また、書類の言語の問題もあります。自国の言語で書かれた書類を提出する場合、公的な翻訳証明(アポスティーユなど)が必要になることがあり、これには多大な時間とコストがかかります。
その結果、海外で銀行口座を開設することは、多くの人にとって非常に困難な作業となります。留学生や海外赴任者が現地で生活を始める際、最初の関門となるのがこの口座開設です。
この「再認証の手間」は、個人だけでなく企業にとっても大きな負担です。グローバルに事業を展開する企業は、各国の子会社や支店で現地の銀行口座を開設する必要がありますが、そのたびに複雑な法人確認手続き(KYB: Know Your Business)を強いられます。
一度完了したKYC情報を、他の金融機関や他の国で再利用できないことが、この問題の根本にあります。A銀行で厳格な本人確認を終えたとしても、B銀行で口座を開設する際には、またゼロから同じ手続きを繰り返さなければなりません。
これは、非常に非効率であり、ユーザー体験を大きく損なう要因となっています。これは、金融機関同士が顧客情報を共有することに対するプライバシー保護の壁や、各国の規制の壁が存在するからです。
送金時の摩擦
国境を越える際のもう一つの大きな不便さが、国際送金における摩擦です。国際送金は依然として複雑で、コストも時間もかかります。
現在、国際送金の多くは、SWIFT(国際銀行間通信協会)というネットワークを通じて行われています。SWIFTは、世界中の銀行をつなぐメッセージングシステムであり、送金指示を安全に伝達する役割を果たしています。しかし、実際の資金の移動は、コルレス銀行(中継銀行)と呼ばれる銀行間の決済ネットワークを通じて行われます。
この仕組みは、複数の銀行を経由するため、送金に数日から1週間程度の時間がかかることがあります。また、各銀行が手数料を徴収するため、様々なコストが発生し、特に少額の送金の場合、手数料の割合が非常に高くなります。
さらに、近年のAML/CFT規制の強化により、国際送金に対するコンプライアンスチェックはますます厳格になっています。金融機関は、送金者と受取人の身元を確認し、取引が制裁対象者や不正な目的に関連していないかを慎重に審査する必要があります。もし少しでも疑わしい点があれば、送金は停止され、詳細な調査が行われます。これにより、送金の遅延や、場合によっては送金が拒否されることもあります。
この送金時の摩擦は、国際貿易や個人の経済活動にとって大きな足かせとなっています。近年、この問題を解決するために、FinTech企業による新しい国際送金サービスや、ブロックチェーン技術を利用した暗号資産による送金も注目されています。
しかし、暗号資産による送金も新たな課題に直面しています。それが「トラベルルール」です。FATFは、暗号資産交換業者に対し、送金者と受取人の情報を収集し、送金先に通知することを義務付けました。これにより、暗号資産の匿名性は制限され、従来の金融システムと同様のKYC要件が求められるようになっています。
このように、国境を越える際の不便さは、国家主権、規制、既存の金融インフラが複雑に絡み合った結果として生じています。
問題点:国家独占・排除される人々・国際金融の壁
これまで見てきたように、パスポートとKYCは、現代社会の秩序と安全を維持するために不可欠な役割を果たしてきました。しかし、国家と既存の金融機関が中心となって築き上げてきたこのID管理システムは、いくつかの根本的な問題点を抱えています。
国家によるID管理の独占
現在のIDシステムは、国家がIDの発行と管理を独占しているという点に最大の特徴があります。この中央集権的な構造は、効率的である反面、いくつかの深刻なリスクを孕んでいます。
第一に、情報漏洩とプライバシー侵害のリスクです。個人の情報が中央集権的なデータベースに集約されることで、サイバー攻撃の標的となりやすくなります。もし、国家が管理するIDデータベースがハッキングされれば、膨大な数の国民の個人情報が流出し、深刻な被害をもたらす可能性があります。
第二に、監視社会化のリスクです。国家が国民のID情報を一元的に管理し、様々な行政サービスや民間サービスと連携させることで、個人の行動履歴や資産状況が容易に把握されるようになります。これは、国家による過度な監視や統制を招く危険性も指摘されています。
第三に、IDの剥奪リスクです。IDが国家によって発行されるものである以上、国家の都合によってその効力が停止されたり、剥奪されたりする可能性があります。政治的な理由による国籍の剥奪や、紛争による国家機能の停止によって、人々が突如として無国籍状態に陥り、基本的な人権が脅かされる事態が発生しています。
このように、国家によるID管理の独占は、個人の権利と自由に対する潜在的な脅威となり得ます。私たちは、利便性と引き換えに、自らの情報の管理権を国家に委ねているのだということを認識する必要があります。
排除される人々(銀行口座を持てない人々)
現在のIDシステムが抱えるもう一つの深刻な問題は、システムから排除される人々の存在です。世界銀行の推計によれば、世界には約10億人が公的な身分証明書を持っておらず、約17億人の成人が銀行口座を持っていません(アンバンクト層)。
IDを持たないことは、社会経済活動からの排除を意味します。銀行口座を開設できないため、安全に貯蓄をすることができず、融資を受けることもできません。教育や医療といった基本的な社会サービスへのアクセスも制限されます。経済的な自立や貧困からの脱却が極めて困難になります。
皮肉なことに、貧困から抜け出すために最も金融サービスを必要としている人々が、IDがないために金融サービスから排除されているのです。
この「金融包摂(Financial Inclusion)」の欠如は、貧困の連鎖を生み出し、経済成長の大きな阻害要因となっています。既存の金融機関は、厳格なKYC要件を満たせない人々に対してサービスを提供することに消極的であり、現在のIDシステムと金融システムは、意図せずして社会的な格差を拡大させる構造的な問題を抱えています。
国際金融の壁
グローバル化が進展する一方で、国際金融の世界は依然として深く分断されています。国家間の対立や規制の違いが、自由な資本の移動を妨げる壁となっています。
その最たる例が、経済制裁です。ある国が特定の国や個人に対して経済制裁を課すと、その対象者は国際的な金融システムから締め出されます。
また、AML/CFT規制の強化も、意図せざる結果として国際金融の分断を深めることがあります。金融機関は、リスクの高い国や地域との取引に慎重になり、場合によっては取引関係を解消することもあります(デリスキング)。これにより、途上国や新興国が国際金融システムから孤立し、経済発展が阻害されるという問題が指摘されています。
さらに、国家間の情報共有の壁も存在します。各国の規制当局は、自国の法律に基づいて金融機関を監督していますが、プライバシー保護法制の違いや、政治的な対立によって、円滑な情報共有が妨げられることがあります。
このように、現在の国際金融システムは、国家主権という概念に基づいて構築されているがゆえに、本質的に分断を孕んでいます。グローバルな課題解決や経済発展を目指す上で、この国家間の壁を乗り越える新しい信頼のネットワークが求められています。
前編のまとめ
前編では、パスポートとKYCの歴史を振り返りながら、国家と金融機関がどのようにして個人のアイデンティティを管理し、信頼と秩序を維持してきたのかを見てきました。
中央集権的なID管理システムは、多くの限界と課題を抱えています。国家によるID管理の独占は、プライバシー侵害や監視社会化のリスクを孕んでいます。また、世界には依然としてIDを持てず、金融サービスから排除されている膨大な数の人々が存在します。さらに、国家ごとに分断されたKYCシステムは、国境を越える際の再認証の手間や送金時の摩擦を生み出し、シームレスなグローバル経済活動を阻害しています。
これらの課題は、既存のシステムを部分的に改善するだけでは解決が困難です。根本的な解決には、アイデンティティ管理のあり方そのものを再考する必要があります。中央集権的な管理者への依存から脱却し、個人が自らの情報を主体的にコントロールできる新しい仕組みが求められています。
後編では、この課題に対する答えとして登場したweb3の技術と思想について詳しく解説します。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら