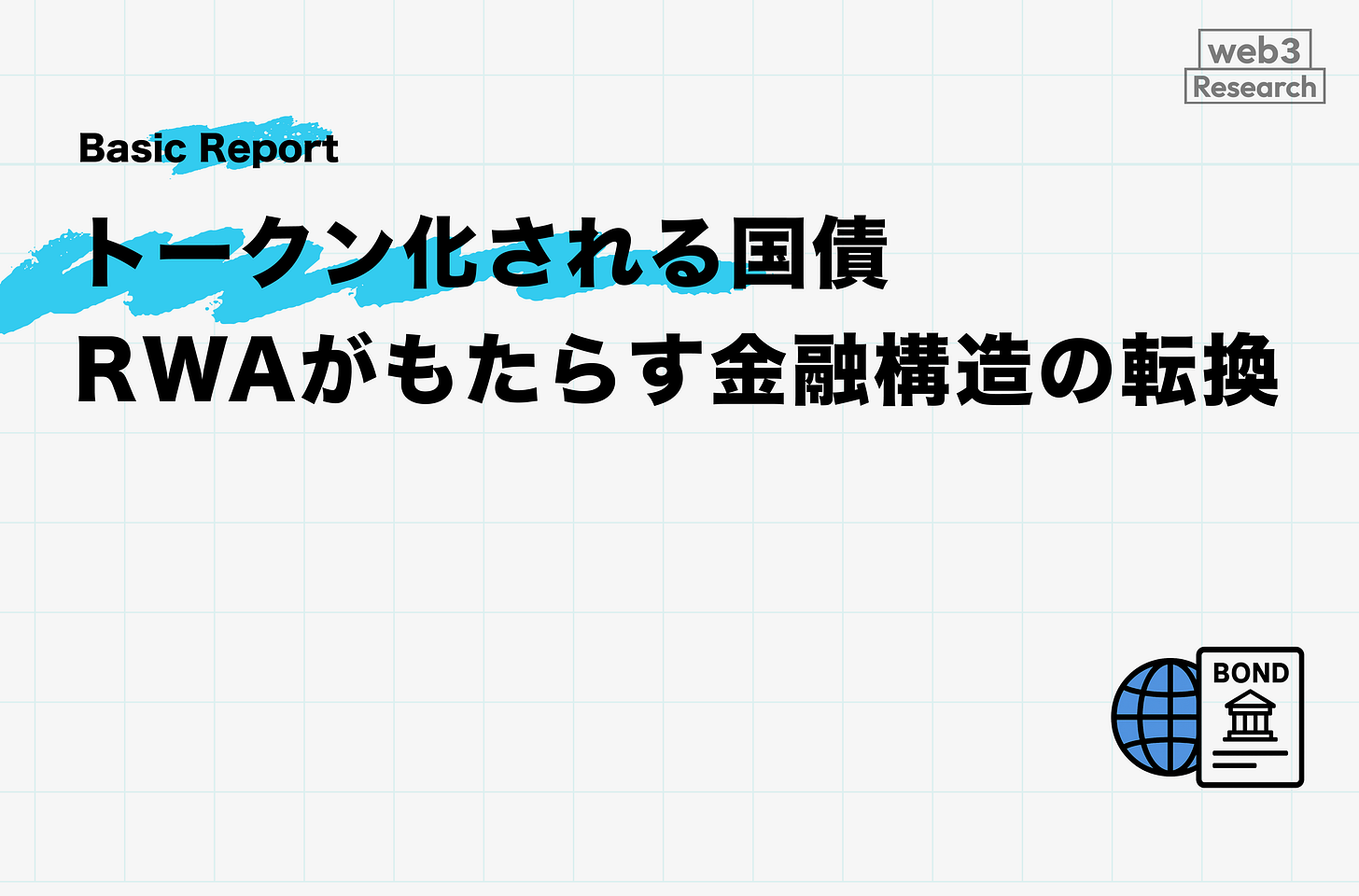おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎レポートを更新しています。今週は「国債」について解説します。
導入|国家の信用が“コード”になる
前編では、国債が近代国家における「信用のOS」として機能してきたメカニズムと、そのシステムが直面する限界について解説しました。後編では、この金融システムの根幹が、ブロックチェーン技術によってどのように再構築されようとしているのかを掘り下げます。その中心的な動きが、RWAとしての国債のトークン化です。
国債のトークン化は、単なるデジタル証券化(デジタイゼーション)ではありません。既存のデジタル化は、中央集権的なデータベース上での電子記録に過ぎず、システムの非効率性や不透明性は温存されていました。
対して、ブロックチェーン上でのトークン化は、「国家の信用をプログラム化する」という、はるかに根本的な変化を意味する行為です。
国債がブロックチェーン上にトークンとして発行されるということは、国家の信用が「スマートコントラクト」という形でコード化されることを意味します。
つまり、ブロックチェーン上に国債が載るということは、“国家の債務”がリアルタイムで、改ざんが極めて困難な分散型台帳上で、誰でも検証可能になるということです。
所有権の移転、利払いの実行、担保としての利用といったプロセスが、人間の仲介者を必要とせず、「コード」によって自動的に執行されるようになります。
この変化が、金融の構造を根本から変えようとしています。国家の信用が「人」や「制度」の管理下から「コード」による自動執行へと移行する、「インターネット国債」の時代が始まろうとしています。
第5章|RWAとは ― 現実資産をスマートコントラクトに結びつける仕組み
国債のトークン化を理解するためには、まずRWAという概念を理解する必要があります。RWAは、現実世界の資産をブロックチェーン上のデジタルトークンとして表現する技術であり、暗号資産の世界と伝統的金融の世界を繋ぐ架け橋となります。
RWAの重要性と国債トークン化の位置づけ
web3の世界は、ビットコインやイーサリアムといったブロックチェーンネイティブな資産を中心に発展してきましたが、これらの資産は価格変動が大きく、安定した価値の基盤を欠いていました。一方、世界の金融資産の大部分はRWA(債券・不動産・株式など)であり、その規模は数百兆ドルに上ります。
RWAトークン化は、この巨大な市場をブロックチェーン技術と接続し、効率性と透明性を高めることを目指します。その中でも、国債トークン化は最も重要な領域です。なぜなら、国債は「信用の源泉」であり「リスクフリー資産」だからです。国債をオンチェーンに取り込むことで、DeFiに安定した利回りと信頼できる担保を提供し、デジタル経済の規模を飛躍的に拡大させることが可能になります。
トークン化の仕組み:オフチェーンとオンチェーンの連携
現実世界の資産をトークン化するには、オフチェーン(ブロックチェーンの外側)の世界と、オンチェーン(ブロックチェーンの内側)の世界を確実に結びつける必要があります。国債トークン化(間接保有モデル)の一般的な仕組みは以下のようになります。
オフチェーンの構造:資産の確保と保全
SPV(特別目的会社)の設立: トークン発行体は、現実世界で国債を保有するための法人格として、SPVや信託を設立します。これは、発行体の倒産リスクから投資家の資産を保護する(倒産隔離)ために重要です。
資産の購入とカストディ: SPVは、投資家から集めた資金で実際の国債(主に米国短期国債など)を購入し、信頼できるカストディアン(保管機関、例:大手銀行)に預託します。
法的な紐付け: SPVが保有する国債の経済的権利と、これから発行されるトークンを法的に結びつけます。
オンチェーンの構造:トークンの発行と管理
トークンの発行: オフチェーンの資産を裏付けとして、ブロックチェーン上でトークンが発行されます。証券としての性質を持つため、KYC(顧客確認)/AML(マネーロンダリング対策)の要件を満たした投資家のみが取引できるよう、スマートコントラクトで制限がかけられるのが一般的です。
所有権と利回りの表現: トークン保有者は、原資産に対する権利を有し、国債から生じる利回りを受け取ります。
スマートコントラクトによる自動処理のインパクト
RWAトークン化の核心は、スマートコントラクトによる自動化と効率化にあります。
利息・償還の自動処理: 利息計算、分配、償還といったバックオフィス業務がスマートコントラクトで自動処理されます。これにより、運用コストが大幅に削減されます。
決済の高速化(アトミック・セトルメント): 従来の証券決済は数日(T+1やT+2)かかりましたが、ブロックチェーン上では数分から数秒で完了します。これにより、カウンターパーティリスクが低減し、資本効率が向上します。
監査と透明性(Proof of Reserve): オフチェーンの資産状況をオンチェーンに証明するために、第三者の監査法人や「オラクル」(外部データをブロックチェーンに提供するサービス)が重要な役割を果たします。これにより、トークンが常に実際の資産によって裏付けられていることの透明性が確保されます。
「法」から「コード」へ:信用構造の変化
国債のトークン化は、国家の信用を裏付けるメカニズムが、従来の「法制度」や「契約」への依存から、ブロックチェーン上の「コード(スマートコントラクト)」による自動執行へと移行することを意味します。
伝統的な金融では、契約不履行が発生した場合、最終的には裁判所などの法執行機関に頼る必要がありました。しかし、スマートコントラクトでは、コード自体が契約であり、その実行はブロックチェーンネットワークによって自動的に強制されます(Code is Law)。
もちろん、現時点では法制度が不要になるわけではありません。オフチェーンでの資産管理や規制遵守は依然として不可欠です。しかし、日々の取引や権利の執行において、コードが果たす役割は決定的に重要になります。
第6章|トークン化国債の台頭 ― インターネット国債の誕生
RWAの理論的な可能性は、ここ数年で急速に現実のものとなりつつあります。特に2023年以降、伝統的金融大手の参入と、金利上昇による安定利回りへの需要の高まりを背景に、トークン化国債市場は急成長を遂げています。これは、「インターネット国債」と呼ぶべき新しい資産クラスの誕生です。
市場規模の拡大と現状(2025年現在)
2025年現在、ブロックチェーン上でトークン化された米国債の市場規模は急速に拡大しています。暗号資産データ分析サイトDefiLlamaのデータによれば、その規模は約150億ドル(約2兆円強)に達していると推定されます。2023年初頭にはわずか1億ドル程度だった市場が、わずか2年で150倍に成長したことになります。
この急成長の背景には、世界的な金利上昇があります。米国債が魅力的な利回り(短期債で5%前後)を提供するようになった一方で、DeFi市場の利回りは低下傾向にありました。その結果、安定したドル建ての利回りをオンチェーンで得たいという需要が、暗号資産投資家、DAO、そして機関投資家から急速に高まりました。
主な事例:伝統金融とweb3の融合
トークン化国債市場の発展を牽引している主要な事例を見てみましょう。伝統的金融機関とweb3ネイティブ企業の双方が参入しています。
1. BlackRock「BUIDL」:Ethereum上のトークン化T-Billファンド
世界最大の資産運用会社であるブラックロックが2024年3月に発表した「BUIDL(BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund)」は、業界に決定的な衝撃を与えました。
概要: イーサリアムのパブリックブロックチェーン上で発行される、トークン化されたT-Bill(米国短期国債)ファンドです。
特徴: トークン価格は1ドルに固定され、利回りは毎日計算され、毎月新たなトークンとして投資家のアドレスに直接分配されます。Securitize社がトークン化プラットフォームを、Bank of New York Mellonが原資産のカストディを担当しています。
意義: ブラックロックの参入は、トークン化国債が単なる実験ではなく、現実の金融インフラとして機能し始めたことを象徴する出来事です。伝統的金融の巨人がパブリックチェーンを採用したことは、RWAの歴史における転換点となりました。
2. Franklin Templeton「BENJI」:米国初の完全オンチェーン投資信託
大手資産運用会社のフランクリン・テンプルトンは、この分野の先駆者です。「BENJI(Franklin OnChain U.S. Government Money Fund)」は、米国政府証券などで運用される投資信託(MMF)の持分をトークン化したものです。
特徴: 米国で初めて規制当局(SEC)に登録された、ブロックチェーンを利用する投資信託であり、トークンの保有記録がファンドの公式な台帳として機能します。
意義: 規制に準拠した形でパブリックブロックチェーンを活用する先駆的な事例となりました。
3. Ondo Finance「USDY」:米国債を担保に安定トークンを発行
web3ネイティブな企業も市場をリードしています。Ondo Financeは、幅広い投資家へのアクセス提供を目指しています。「USDY(USD Yield Token)」は、米国債や銀行預金を担保に発行される、利回り付きの安定トークン(ステーブルノート)です。
特徴: ステーブルコインのように価格が安定していながら、保有するだけで米国債に準ずる利回りを得られる点が特徴です。
意義: 伝統的金融商品をweb3の技術で包み込み(ラッピング)、オンチェーンでの利用価値(コンポーザビリティ)を高めるアプローチを示しています。
国債を「プログラム」として発行・償還する実験
これらの事例は、「国債をプログラムとして発行・管理・償還する」壮大な実験です。スマートコントラクトにより、国債は単なる静的な資産から、動的で機能的なプログラムへと進化しています。自動化された利回り分配、リアルタイムの決済、そして他のデジタル資産とのシームレスな連携が可能になっています。
国債の存在が“リアルタイム・透明・アクセスフリー”になることで、信用のインターネット化(Internetization of Credit)が進みます。
これまで、特定の金融機関や国のシステムに閉ざされていた国家の信用が、インターネットのプロトコル(例:TCP/IP)と同様に、開かれたネットワーク上で利用可能になるのです。情報がインターネットによって民主化されたように、信用もまた、ブロックチェーンによってそのあり方を変えようとしているのです。
第7章|トークン化がもたらす構造変化 ― 流動性・透明性・アクセスの革命
インターネット国債の台頭は、既存の金融市場の構造に大きな変化をもたらします。それは単なる効率化に留まらず、流動性、透明性、アクセスという金融の根幹に関わる要素において、革命的な変化を引き起こします。
① 流動性の再定義:24時間取引・国境を超えるアクセス
従来の国債市場は、取引時間や地理的な制約、そして複雑な決済プロセスによって流動性が制限されてきました。トークン化は、これらの制約を取り払います。
24時間365日の取引: ブロックチェーンは停止しません。トークン化国債は、いつでも、世界のどこからでも取引可能です。これにより、時差や祝日に関係なく、市場リスクに対応できるようになります。
アトミック・セトルメント(即時・不可分決済): スマートコントラクトにより、資産の移転と代金の支払いが同時に、不可分に実行されます。決済ラグがなくなることで、カウンターパーティリスクが劇的に削減され、資本効率が向上します。資金の回転率が上がり、より少ない資金でより多くの経済活動を支えることが可能になります。
グローバルな流動性プール: トークンは国境を越えて瞬時に移転できるため、世界中の需要と供給が一つの流動性プールに統合されます。これにより、価格発見機能が高まり、取引コストが低下します。
② 透明性の拡張:ブロックチェーン上で保有・償還・金利情報が可視化
伝統的な金融システムは、多くの仲介機関が介在し、それぞれが独自の台帳を管理しているため、全体像を把握することが困難でした。これがシステミックリスクの温床となることがありました(例:リーマンショック時のデリバティブ市場)。
トークン化は、透明性を新たな次元へと拡張します。
共有された台帳とリアルタイム監査: すべての取引記録は、分散型台帳に記録され、リアルタイムで検証可能です。データの不整合や不正行為のリスクが低減します。
保有・償還・金利情報の可視化: 誰が(どのアドレスが)どれだけのトークンを保有しているか、発行と償還のプロセス、そして利回りの分配状況がブロックチェーン上で可視化されます。
Proof of Reserve: 原資産の裏付けがオンチェーンで証明されるため、発行体の信頼性が高まります。
この透明性の向上は、市場参加者の信頼を高め、規制当局による監督の効率化にも貢献する可能性があります。
③ アクセスの民主化:個人でも国債投資に直接アクセス可能
従来の国債市場は、主に大手金融機関や機関投資家が参加する市場であり、個人投資家や新興国の企業がアクセスするには高いハードルがありました。
トークン化は、このアクセス格差を解消し、金融包摂を促進します。
小口化(フラクショナリゼーション): トークンは細かく分割できるため、少額から国債に投資することが可能になります。これにより、個人投資家でも容易にポートフォリオに安全資産を組み入れることができます。
金融包摂の促進: インターネット環境さえあれば、銀行口座を持たない人々や、自国通貨が不安定な新興国の人々が、安全な資産(例:米国債)にアクセスし、富を保全する手段を得ることができます。
DeFiとの統合: トークン化国債は、DeFiプロトコルの構成要素として利用可能になります。これにより、誰もが国債を担保にしたローンや、国債利回りを活用した運用商品を利用できるようになります。
これまで政府・銀行・機関投資家が独占していた国債市場が、開かれたネットワークに置き換わります。
これらの変化は、金融市場の構造そのものを転換させます。国債という“国家の信用装置”が、特定の機関だけでなく、市民、企業、DeFiプロトコル、さらにはAIまでもが参加する、分散的な信用市場へと進化していくのです。これは、金融における権力の分散と民主化を促す、歴史的な構造変化です。
第8章|“インターネット国債”が変える金融秩序
トークン化国債は、単なる新しい金融商品ではありません。それは、これからの金融秩序のあり方を根本から変える可能性を持つ、構造的なイノベーションです。最終章では、インターネット国債がもたらす未来の金融像と、それが持つより深い意味について考察します。
トークン化国債は、国家の信用をAPI化する
トークン化国債がもたらす最も本質的な変化は、「国家の信用をAPI化する」ことです。
国債がスマートコントラクトとしてブロックチェーン上に表現されることで、その機能(金利、利回り、担保価値)は、他のアプリケーションから自由に呼び出し、組み合わせることが可能になります(コンポーザビリティ)。
プログラム可能な金利: リスクフリーレートがオンチェーンでリアルタイムに利用可能になります。これにより、国債金利に連動したデリバティブや変動金利ローンなどを、スマートコントラクトで自動的に組成できます。
プログラム可能な担保: トークン化国債は、オンチェーンで最も信頼できる担保となります。担保評価、証拠金管理、デフォルト時の清算といったプロセスを自動化し、透明で効率的なレンディング市場やレポ市場をオンチェーンで構築できます。
国家の信用がAPIとして開放されることで、開発者はこれまでにない革新的な金融サービスを創出できるようになります。
オンチェーンで統合される金融機能
インターネット国債を基盤として、様々な金融機能がオンチェーンで統合されていきます。
金利データ・利回り分配・担保流通が、オンチェーンで統合。これまで分断されていた金利市場、資産運用市場、担保市場が、ブロックチェーンという共通基盤の上で統合され、シームレスに連携するようになります。新しい金融スタック(階層構造)が形成され、トークン化国債がその基層となるでしょう。
DeFiやステーブルコインの変容
DeFiやステーブルコインは、インターネット国債の登場によって大きく変容します。
これまでDeFiは、暗号資産という不安定な資産を担保として発展してきたため、システミックリスクを抱えていました。しかし、トークン化国債という安定した価値の基盤が導入されることで、DeFiはより堅牢でスケーラブルな金融システムへと進化します。
ステーブルコインも、その裏付け資産としてトークン化国債を利用することで、透明性と安全性を高めることができます。「利回り付きステーブルコイン」が主流になる可能性もあります。
トークン化国債がオンチェーン金融の基盤となり、DeFiやステーブルコインはその上に構築されるアプリケーションレイヤーとして機能するようになるのです。
国家信用の共用資産化と主権の変容
この変化が持つ最も深い意味は、国家の信用のあり方が変わるということです。
もちろん、国債を発行し、その信用を裏付けるのは依然として国家です。しかし、その信用がブロックチェーンというオープンソースのプロトコル上で流通するようになると、それは一種の「共用資産(コモンズ)」としての性質を帯び始めます。世界中の誰もが、その信用を利用して、新しい価値を創造できるようになるのです。
国家の信用が、オープンソースのプロトコルによって共用資産化する。
これは金融の再分配であり、国家主権の一部が、スマートコントラクトという「コード」によって規定される領域、すなわち“コード主権”に移行する出来事でもあると言えます。金融のルール決定権が、国家からネットワークへと部分的に移譲されていくのかもしれません。
後編まとめ|RWA=国家信用の再構築装置
国債のトークン化とは、国家が発行してきた信用の“仕組み”を再設計することです。それは、単なる技術的なアップデートではなく、近代国家が数百年にわたって機能させてきた信用の仕組みそのものを、デジタル時代に合わせて再設計する試みです。
ブロックチェーンは、国家の財政・債務・信用をリアルタイムで反映する新しい台帳になります。国家の信用をプログラム化し、スマートコントラクトによって自動執行することで、流動性、透明性、アクセスにおいて革命的な変化が起ころうとしています。
“インターネット国債”とは、国家信用のデジタル移植であり、中央集権的なシステムと分散型ネットワークが融合する接点です。
それは、21世紀のマネー・ガバナンスを再構築する起点です。このRWAという国家信用の再構築装置がもたらす衝撃は、これから本格的に金融の世界を揺り動かしていくことになるかもしれません。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら