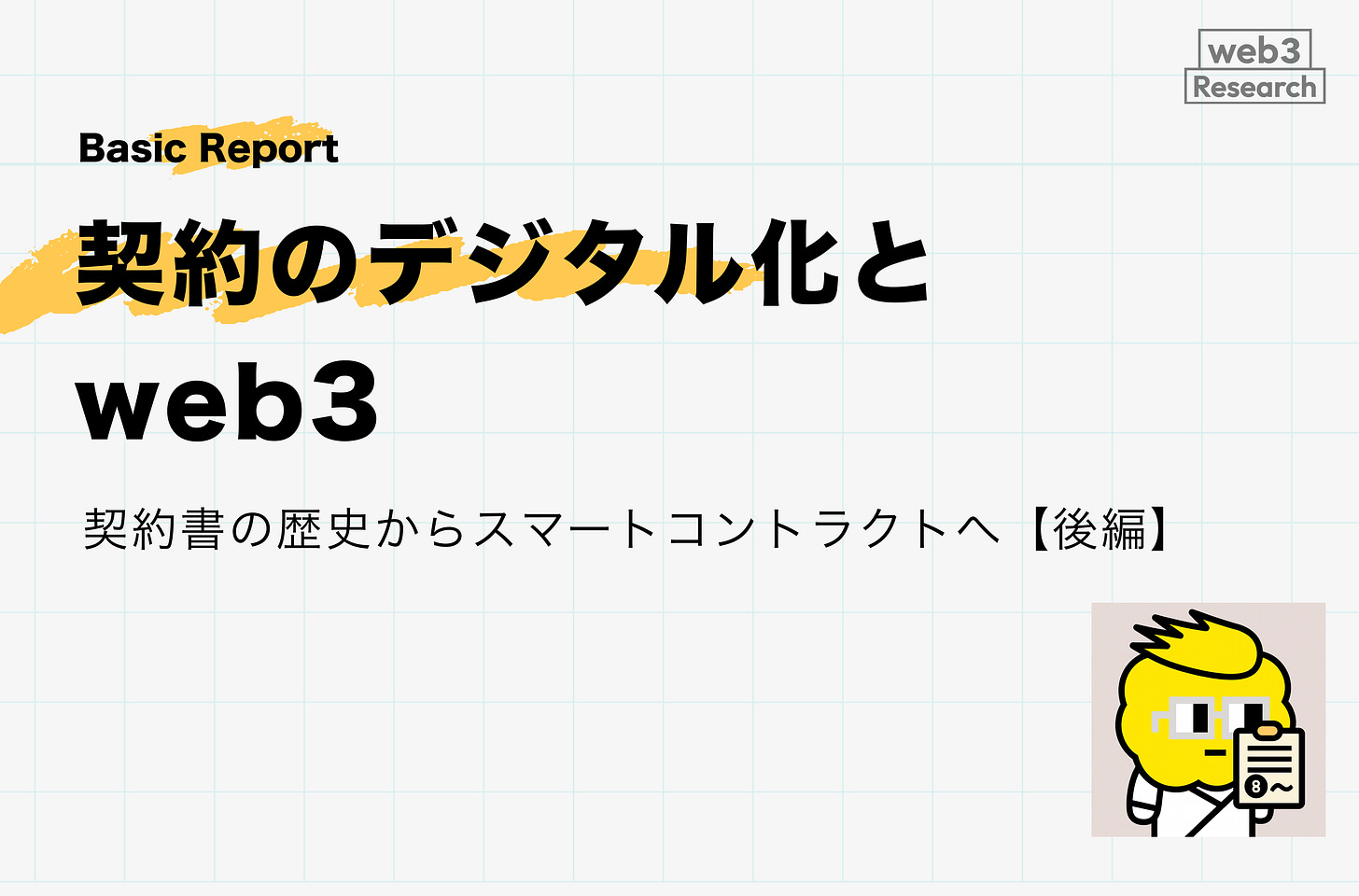おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎の基礎レポートを更新しています。今週は「契約」について解説します。ぜひ最後までご覧ください!
電子署名とデジタル契約の時代
スマートコントラクトとは?
強みと課題
まとめ:信頼の進化と新たなパラダイム
電子署名とデジタル契約の時代
インターネット革命が契約に与えた衝撃
21世紀の幕開けとともに、インターネット技術の爆発的普及は契約制度にも根本的な変革をもたらしました。それまで紙と印鑑が支配していた契約の世界に、デジタルという新たな次元が加わったのです。この変化は単なる媒体の置き換えではなく、契約そのものの概念を拡張する革命的な出来事でした。
1990年代後半から2000年代にかけて、企業のデジタル化が本格化すると、契約業務の非効率性が深刻な問題として浮上しました。グローバル企業では、世界各地の拠点間で契約書を郵送するだけで数週間を要し、緊急性の高い取引では航空便やファックスに頼らざるを得ませんでした。この物理的制約が、デジタル時代のビジネススピードに対応できない大きなボトルネックとなっていました。
電子署名技術の理論的基盤となる公開鍵暗号方式は、1976年にディフィーとヘルマンによって発明されていましたが、実用化には20年以上の歳月を要しました。1990年代後半になってようやく、RSA暗号やデジタル署名アルゴリズム(DSA)の実装が安定し、商用利用に耐える電子署名システムが登場しました。
電子署名の法的有効性を確立する動きも同時期に加速しました。2000年のアメリカ電子署名法(ESIGN Act)は画期的でした。「電子署名で締結された契約は、それが電子的なものであることを理由として、その有効性や執行可能性を否定されることはない」という明確な法的保護を与えたのです。続いて2001年のEU電子署名指令、日本の電子署名法など、世界各国で電子署名の法的地位が確立されていきました。
DocuSignの登場とデジタル契約の民主化
2003年に設立されたDocuSignは、電子契約分野の先駆者として重要な役割を果たしました。同社の創立者らは、従来の複雑で高価な電子署名システムを、誰でも簡単に使えるクラウドサービスとして提供するという革新的なアプローチを採用しました。
DocuSignの成功要因は、技術的優秀性だけでなく、ユーザーエクスペリエンスの徹底的な改善にありました。従来の電子署名システムでは、専用ソフトウェアのインストール、デジタル証明書の取得、複雑な設定作業が必要でした。しかし、DocuSignはウェブブラウザ上で完結する直感的なインターフェースを提供し、技術的な知識がないユーザーでも数分で契約書に署名できるようにしました。
2010年代に入ると、クラウドコンピューティングの普及とスマートフォンの浸透により、電子契約の利用シーンが急速に拡大しました。不動産売買、自動車購入、保険契約、雇用契約など、従来は対面での署名が当然とされていた分野でも電子契約が受け入れられるようになりました。
新型コロナウイルスパンデミックは、この流れを決定的に加速させました。2020年3月以降、世界中で外出制限が実施され、対面での契約締結が物理的に不可能になったのです。DocuSignの株価は2020年だけで2倍以上に急騰し、同社の月間アクティブユーザー数は前年比300%増を記録しました。パンデミックは、電子契約を「選択肢の一つ」から「必要不可欠なインフラ」へと押し上げたのです。
日本市場におけるクラウドサインの革新
日本市場では、弁護士ドットコムが2015年に開始したクラウドサインが成功を収めました。日本の契約慣行には、欧米とは異なる特殊性があります。手書き署名よりも印鑑(特に実印)を重視する文化、厳格な本人確認プロセス、複雑な稟議制度などです。
クラウドサインは、これらの日本特有の要件に対応した設計思想で差別化を図りました。印鑑の代わりとなる「電子印鑑」機能、日本の商法に準拠した契約書フォーマット、複数人による順次承認ワークフローなど、日本企業のニーズに最適化された機能を提供しました。
特に注目すべきは、法的効力に関する日本独自のアプローチです。欧米の電子署名は厳格な本人確認(PKI:公開鍵基盤)を前提としていますが、クラウドサインは「当事者型署名」という日本の電子署名法の特例を活用しました。これにより、デジタル証明書を必要とせず、メールアドレスでの本人確認だけで法的に有効な電子契約を実現したのです。
この戦略は大成功を収め、2023年時点でクラウドサインの導入企業数は20万社を突破しています。中小企業から大企業まで幅広い層に浸透し、日本の契約業務のデジタル化を牽引しました。
電子契約がもたらした変革の意味
電子契約の普及は、単なる効率化を超えた構造的変化をもたらしました。最も重要なのは、契約締結のスピード革命です。従来は数日から数週間を要していた契約プロセスが、数時間から数日に短縮されました。これにより、ビジネスの意思決定サイクルが劇的に加速し、市場変化への対応力が向上しました。
コスト削減効果も顕著でした。印刷費、郵送費、保管費用などの直接コストに加え、契約書の作成、送付、回収、ファイリング作業にかかる人件費も大幅に削減されました。ある大手商社の試算では、電子契約の導入により年間5億円のコスト削減を実現したと報告されています。
環境負荷の削減も重要な副次効果でした。年間数十万枚の契約書を扱う大企業では、ペーパーレス化により森林資源の保護に大きく貢献しました。ESG(環境・社会・ガバナンス)経営が重視される現代において、これは企業価値向上の重要な要素となっています。
契約管理の高度化も見逃せません。紙の契約書では検索や分析が困難でしたが、電子契約では契約内容のデータベース化、期限管理の自動化、契約条件の統計分析などが可能になりました。これにより、より戦略的な契約管理が実現されています。
電子契約の構造的限界
しかし、現在の電子契約システムには根本的な制約があります。最も重要なのは、依然として「中央集権的な管理者」に依存している点です。DocuSign、クラウドサイン、Adobe Signなどのプラットフォームは、契約データの保管、署名の検証、システムの運用をすべて自社で一元管理しています。
これは、従来の紙ベースの仲介者依存システムを、デジタル領域にそのまま移植したものです。ユーザーはプラットフォーム運営会社の継続性、セキュリティ、利用規約に完全に依存しており、この依存関係から逃れることはできません。
データポータビリティの問題も深刻です。ある電子契約プラットフォームから別のプラットフォームに移行する際、過去の契約データを完全に移行することは技術的に困難です。これにより、ユーザーは特定のプラットフォームに「ロックイン」される状況が生じています。
法的拘束力は確かに認められていますが、契約履行の自動化は限定的です。電子契約プラットフォームは、契約の締結と保管は効率化できますが、契約内容の履行監視、期限管理、違反時の自動対応などは依然として人間の判断と介入に依存しています。
国際取引における複雑性
グローバルな電子契約には、さらに複雑な課題があります。各国の電子署名法制は完全には統一されておらず、ある国で有効な電子署名が他国では認められない場合があります。EU圏の認定電子署名(QES:Qualified Electronic Signature)、アメリカの比較的緩やかな電子署名、中国の電子認証法など、地域ごとに異なる基準が存在しています。
データの越境移転規制も年々厳格化しています。GDPR、中国のサイバーセキュリティ法、ロシアのデータローカライゼーション法など、各国が自国民のプライバシー保護や国家安全保障を理由とする規制を強化しており、グローバルな電子契約プラットフォームの運営が困難になっています。
通貨や税制の違いも課題です。国際契約では複数通貨での決済、各国の税制への対応、為替リスク管理などが必要ですが、現在の電子契約プラットフォームではこれらの金融機能は限定的です。
スマートコントラクトとは?
Ethereumが切り開いた契約の新時代
2015年7月30日、Ethereumブロックチェーンの稼働開始は、契約概念における歴史的転換点となりました。ヴィタリック・ブテリンが19歳で発表したこのプラットフォームは、単なる暗号通貨を超えた「世界コンピューター」として設計されていました。
Ethereumの最大の革新は、ブロックチェーン上で「スマートコントラクト」を実行できることでした。これは1990年代に暗号学者ニック・サボが提唱した概念を、実用的な形で実現したものです。サボは「スマートコントラクトとは、契約条項を実行するコンピュータープロトコルである」と定義していましたが、当時の技術では理論に留まっていました。
Ethereumが実現したスマートコントラクトは、従来の契約概念を根本的に覆しました。これまでの契約は「人間が読んで理解し、人間が実行する文書」でしたが、スマートコントラクトは「コンピューターが理解し、自動実行するプログラム」です。この転換により、契約は静的な約束から動的な実行機構へと進化したのです。
if/thenロジックによる条件付き自動実行
スマートコントラクトの核心は、プログラミングにおける基本的な条件分岐である「if/then」ロジックにあります。「もし条件Aが満たされたら、自動的にアクションBを実行する」という単純な構造ですが、これをブロックチェーン上で不変かつ検証可能な形で実装することで、革命的な可能性が開かれました。
具体例で説明しましょう。従来の不動産売買契約では、「買主が代金を支払い、売主がそれを確認した後、所有権移転登記を行う」という手順が必要でした。この過程では、代金の支払い確認、登記手続き、所有権証明書の発行など、多くの人的作業と時間を要していました。
しかし、スマートコントラクトでは、「IF(指定されたウォレットアドレスに1,000,000円相当のETHが送金されたことが確認された場合)THEN(不動産NFTの所有権を自動的に買主のウォレットに移転する)」というロジックで、瞬時に取引を完結できます。
この自動実行は、人間の判断や介入を一切必要としません。条件が満たされた瞬間に、Ethereumネットワーク全体がその事実を検証し、プログラムされた通りの結果を実行します。これにより、従来は数日から数週間を要していた複雑な取引が、数分で完了するようになりました。
ブロックチェーンが保証する三つの革新的特性
スマートコントラクトが従来の契約システムと根本的に異なるのは、ブロックチェーン技術による三つの画期的な特性を持つからです。
第一に「仲介者不要」(Trustless)の実現です。この「Trustless」という概念は、「信頼が不要」ではなく「第三者への信頼が不要」という意味です。従来の契約では、当事者同士が信頼関係を構築できない場合、銀行、弁護士、公証人、裁判所などの信頼できる第三者機関が仲介役を務めていました。
しかし、スマートコントラクトでは、世界中に分散したEthereumノードが協調して動作することで、特定の仲介者に依存することなく契約の履行を保証します。この分散的な合意メカニズムにより、単一の機関や個人の腐敗、失敗、恣意的判断によって契約が影響を受けることがなくなりました。
第二に「改ざん不能」(Immutable)性です。一度Ethereumブロックチェーンに記録されたスマートコントラクトは、ネットワーク参加者の圧倒的多数(51%以上)の合意なしには変更できません。これは現実的には不可能に近い条件であり、事実上の改ざん不能性を保証しています。
この特性により、契約の事後的な改ざんや一方的な条件変更が防がれます。従来の契約では、力関係の変化や状況の変化により、強者が弱者に不利な条件変更を強要する事例が頻発していました。しかし、スマートコントラクトでは、最初に合意された条件が数学的に保護され、どちらの当事者も一方的に変更することはできません。
第三に「透明性」(Transparency)の確保です。スマートコントラクトのソースコードと実行履歴は、Ethereumブロックチェーン上で完全に公開されており、世界中の誰もが検証可能です。これは従来の契約にはない革新的な特性です。
従来の契約書は当事者以外には秘匿されており、契約内容や履行状況を第三者が確認することは困難でした。しかし、スマートコントラクトでは、契約の条件、実行状況、資金の動きなどがリアルタイムで公開されており、極めて高い透明性が保たれています。
プログラマブルマネーの革命
スマートコントラクトが可能にした最も革新的な概念の一つが「プログラマブルマネー」です。従来の通貨は単純な価値の保存・交換手段でしたが、暗号通貨とスマートコントラクトを組み合わせることで、お金自体に複雑なロジックを組み込むことが可能になりました。
例えば、「毎月1日に自動的に家賃を支払う」プログラマブルマネーを作成できます。借主のウォレットに十分な残高がある限り、毎月自動的に貸主に送金され、残高不足の場合は予め設定された連帯保証人のウォレットから支払われます。滞納の心配がなく、督促の手間も不要になります。
企業の経理業務でも革新的な応用が可能です。「売上の30%を自動的に税務当局に送金し、20%を設備投資資金としてプールし、15%を従業員ボーナス原資として積み立て、35%を事業運営資金として保持する」というロジックを組み込んだプログラマブルマネーにより、複雑な資金管理を完全自動化できます。
投資ファンドの分野では、さらに高度な応用が実現されています。「投資先企業の株価が20%以上値上がりした場合は自動的に利確し、10%以上値下がりした場合は損切りする」といった投資戦略を、感情に左右されることなく確実に実行するプログラマブルマネーが活用されています。
Code is Law:コードとしての契約の意味
「Code is Law」(コードこそが法である)という概念は、ハーバード大学のローレンス・レッシグ教授が提唱し、スマートコントラクトの本質を表現した重要な概念です。これは、従来の「人間が作った法律を人間が解釈して執行する」システムから、「数学的なコードが絶対的な規範として機能する」システムへの根本的転換を意味します。
従来の契約では、自然言語(日本語、英語など)で書かれた契約条項を人間が解釈し、紛争が生じた場合は裁判官が最終的な判断を下していました。しかし、自然言語には曖昧性があり、同じ文章でも異なる解釈が可能です。「合理的な期間内に」「善意で」「通常の商慣習に従って」といった表現は、具体的な行動指針を明確に定めていません。
スマートコントラクトでは、Solidityなどのプログラミング言語で書かれた条件が絶対的な規範となります。プログラムコードには曖昧性がありません。「if (balance >= 1000000)」という条件は、残高が1,000,000以上の場合にのみ実行されるという意味以外の解釈の余地がありません。
この数学的確実性により、契約の結果が予測可能になりました。当事者は事前に、どのような条件でどのような結果が生じるかを正確に知ることができます。これは、不確実性を排除し、より効率的な意思決定を可能にします。
自動執行の革命的意味
スマートコントラクトの自動執行機能は、人間社会における約束の概念を根本的に変えました。従来は「約束を守ることを期待する」システムでしたが、スマートコントラクトでは「約束が自動的に履行される」システムが実現されています。
人間の約束には常に破られるリスクがあります。経済状況の変化、感情の変化、価値観の変化などにより、最初の約束を守ることが困難になる場合があります。しかし、スマートコントラクトでは、人間の意思や状況の変化とは無関係に、プログラムされた条件が機械的に実行されます。
これは「信頼の自動化」とも呼ばれる革新です。相手を信頼する必要がなく、相手に信頼される必要もありません。数学的・暗号学的メカニズムが信頼を代替するため、見知らぬ相手との間でも安心して取引を行うことができます。
ただし、この革新には重要な含意があります。人間社会の複雑性や不確実性への対応能力が失われることです。従来の契約法では「信義誠実の原則」「事情変更の原則」などにより、予期しない状況に柔軟に対応していました。しかし、スマートコントラクトでは、プログラムされた条件のみが実行され、人道的配慮や状況の変化は自動的には考慮されません。
強みと課題
スマートコントラクトの圧倒的な優位性
スマートコントラクトが従来の契約システムに対して持つ優位性は、既に多くの分野で実証されており、その効果は従来の予想を大きく上回っています。最も重要な強みは、取引コストの劇的な削減です。
従来の不動産取引を例に取ると、仲介手数料、司法書士費用、登記費用、印紙税、融資手数料などで物件価格の5-10%のコストが発生していました。5,000万円の物件では250万円から500万円の取引コストです。しかし、スマートコントラクトを使用した不動産取引では、これらの中間業者への支払いが不要となり、取引コストはEthereumのガス代(通常数千円から数万円)のみに削減されます。コスト削減率は90%以上に達します。
時間の短縮効果も革命的です。国際送金を例に取ると、従来の銀行送金では、コルレス銀行を経由した複雑な経路により3-5営業日を要し、手数料も数千円から数万円かかっていました。しかし、暗号通貨による国際送金では、世界中どこへでも数分から数時間で送金でき、手数料は数百円程度です。
信頼の自動化による心理的負担の軽減も重要な利点です。従来の取引では、「相手が約束を守るかどうか」という不安が常に存在し、この不安を解消するために様々な担保や保証の仕組みが必要でした。契約保証保険、履行保証、連帯保証人などです。しかし、スマートコントラクトでは、条件が満たされれば数学的に確実に実行されるため、人間の信頼性への不安から解放されます。
国境を越えた取引の革命
グローバルな取引におけるスマートコントラクトの威力は特に顕著です。従来の国際契約では、各国の法制度の違い、通貨の違い、タイムゾーンの違い、言語の違いなどが重層的な障壁となっていました。
例えば、日本の投資家がアメリカの不動産に投資し、その物件をイギリスの管理会社が運営し、収益をスイスの銀行口座に送金するという取引を考えてみましょう。従来のシステムでは、4か国の法制度に準拠した契約書の作成、各国の規制当局への届出、複数の銀行との送金契約、為替リスクヘッジ契約などが必要で、数ヶ月の準備期間と数百万円のコストを要していました。
しかし、スマートコントラクトでは、これらすべての要素を単一のプログラムに組み込むことができます。賃料収入の自動分配、税金の自動計算・納付、為替レートの自動取得・適用、投資家への配当自動送金などが、人間の介入なしに実行されます。グローバルに統一されたEthereumネットワーク上で動作するため、国境という概念が存在しません。
24時間365日稼働する金融システム
従来の金融システムには営業時間という制約がありました。銀行は平日の9時から15時まで、証券取引所も平日の限られた時間のみの営業です。週末や祝日には取引が停止し、緊急時の資金調達や決済が困難でした。
スマートコントラクトベースのDeFiシステムは、この制約を完全に解消しました。Uniswap、Compound、Aaveなどのプロトコルは、年中無休で稼働し続けています。深夜でも週末でも、世界中どこからでも、融資の実行、投資の実行、取引の実行が瞬時に可能です。
この常時稼働システムは、特に異なるタイムゾーンの当事者間の取引で威力を発揮します。日本の投資家がヨーロッパの資産に投資し、アメリカの市場で取引するといった複雑な国際取引も、時差を意識することなく実行できます。
深刻な技術的リスクと課題
一方で、スマートコントラクトには解決すべき重要な課題も多数存在します。最も深刻なのは、バグによる致命的な損失リスクです。従来の契約書に誤字があっても、常識的な解釈により意図を汲み取ることができますが、スマートコントラクトのバグは取り返しのつかない結果をもたらす可能性があります。
2016年6月17日に発生したThe DAO事件は、この危険性を如実に示しました。DAOのスマートコントラクトに存在した再帰呼び出しの脆弱性を突かれ、約360万ETH(当時の価値で約60億円、現在の価値では約1兆円)が攻撃者によって奪われました。
この事件の深刻さは、単なる金銭的損失を超えて、Ethereumコミュニティ全体を分裂させたことです。資金を取り戻すためにブロックチェーンの履歴を書き換える「ハードフォーク」を実施するか否かで激しい論争が発生し、最終的にEthereumとEthereum Classicへの永続的な分裂という事態に発展しました。
2020年以降も、バグによる大規模な損失が頻発しています。bZx Protocol攻撃(2,500万ドル)、Poly Network攻撃(6億ドル)、Ronin Bridge攻撃(6億ドル)など、スマートコントラクトの脆弱性を突いた攻撃により、総額数十億ドルの損失が発生しています。
オラクル問題:現実世界との接続の困難
「オラクル問題」は、スマートコントラクトの根本的な課題の一つです。ブロックチェーンは基本的に閉じたシステムであり、外部の情報を直接取得することができません。しかし、多くの契約は現実世界の事象(気象条件、株価、為替レート、商品の配送状況など)に依存しています。
例えば、「明日の東京の最高気温が30度を超えたら保険金を支払う」という天候保険のスマートコントラクトを考えてみましょう。このコントラクトを実行するためには、外部の気象データをブロックチェーンに取り込む必要があります。この外部データを提供するサービスが「オラクル」です。
しかし、オラクルの存在は、スマートコントラクトの分散的特性を損なう重要な問題を提起します。オラクルが間違ったデータを送信したり、悪意を持って偽のデータを送信したりした場合、スマートコントラクトは誤った結果を実行してしまいます。
Chainlink、Band Protocol、API3などのオラクルサービスは、複数のデータソースを組み合わせたり、データ提供者にステーキング(担保)を要求したりすることで、この問題の解決を試みています。しかし、完全な解決策は未だ確立されておらず、スマートコントラクトの実用化における重要なボトルネックとなっています。
法的地位の不明確性
多くの国では、スマートコントラクトの法的地位が依然として曖昧です。従来の契約法は人間の意思表示を前提としており、自動実行されるコードをどのように法的に位置づけるかは新しい課題です。
日本では、2022年5月に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」でスマートコントラクトの活用推進が明記されましたが、具体的な法的フレームワークは未整備です。民法上の契約成立要件(申込みと承諾の合致)をスマートコントラクトにどう適用するか、契約に不備があった場合の救済方法、消費者保護の観点からの規制などが課題となっています。
アメリカでは州によって対応が分かれています。デラウェア州、ネバダ州、アリゾナ州などはスマートコントラクトの法的有効性を明示的に認める法律を制定していますが、連邦レベルでの統一的な規制は存在しません。
EUでは、MiCA(Markets in Crypto-Assets)規制やeIDAS規制などでデジタル技術の法的枠組みを整備していますが、スマートコントラクト特有の課題への対応は限定的です。
プライバシーとコンプライアンスの課題
ブロックチェーンの透明性は利点でもありますが、プライバシーの観点では深刻な問題となります。すべての取引履歴が公開されるため、取引パターンの分析により個人や企業の行動を推測することが可能です。
企業間の重要な契約では、取引条件や取引相手の情報が競合他社に知られることは大きな問題です。M&A交渉、新商品開発、戦略的提携などの機密性の高い取引には、現在の透明なブロックチェーンは適用困難です。
また、GDPR(EU一般データ保護規則)などのプライバシー規制との整合性も課題です。GDPRは個人データの削除権(忘れられる権利)を規定していますが、ブロックチェーンの不変性と矛盾します。一度記録されたデータを削除することは技術的に不可能であり、規制遵守が困難です。
まとめ:信頼の進化と新たなパラダイム
「法が人を守る」から「コードが強制力を持つ」へのパラダイム転換
スマートコントラクトの登場は、人類史における信頼と強制力の概念において、最も根本的な転換点を表しています。古代から現代まで、社会秩序は「法が人を守る」という理念の下で構築されてきました。法的ルールと司法制度が契約の履行を保証し、違反があった場合は国家権力が介入して強制執行を行うという仕組みです。
この従来システムでは、最終的な判断権は人間(裁判官、仲裁人、行政官など)が持っていました。法律の条文は一般的・抽象的に書かれており、具体的な事案への適用は人間の解釈と判断に委ねられていました。例外的な事情、社会通念、公平性といった人間的な価値観が契約解釈に反映され、硬直的な条文適用による不合理な結果を回避していました。
しかし、web3の世界では「コードが強制力を持つ」という全く新しいパラダイムが出現しています。スマートコントラクトでは、プログラムされた条件が満たされると、人間の判断や介入を一切必要とせず、数学的・暗号学的に確実に契約が実行されます。これは、人間の善意や道徳、国家の権威に依存しない、全く新しい形の強制力です。
この変化の意味は極めて重大です。
「アルゴリズム・ガバナンス」とも呼ばれるこの新しい統治形態では、人間の恣意性や腐敗、感情に左右されない純粋に合理的なルール執行が可能になります。一方で、人間社会の複雑性や不確実性への柔軟な対応能力は失われます。プログラムされた条件のみが絶対的な基準となり、そこに人間的な温情や例外的考慮は存在しません。
Web2からweb3への信頼メカニズムの革命
Web2時代の電子契約とweb3時代のスマートコントラクトの違いは、単なる技術的な改良ではなく、信頼構築メカニズムの根本的な思想転換を表しています。
Web2の電子契約システム(DocuSign、クラウドサインなど)は「中央集権的保証」に基づいています。プラットフォーム運営会社が中央管理者として機能し、契約の有効性、署名の真正性、データの保全性をすべて保証しています。ユーザーは、プラットフォーム運営会社の技術力、経営の継続性、倫理的行動への信頼に全面的に依存しています。これは従来の仲介者依存システムをデジタル化したものであり、信頼構造の本質的な変化はありません。
対照的に、web3のスマートコントラクトは「分散的保証」という革新的な概念を導入しています。特定の中央管理者に依存することなく、世界中に分散した数千のノードが協調して動作することで、契約の履行を保証します。Ethereumネットワークの場合、約40万台のノードが独立して動作し、その過半数の合意により取引の有効性が決定されます。
この分散的保証システムの最大の特徴は、システム全体の信頼性が個々の参加者の信頼性を上回ることです。ネットワーク参加者の大部分が善意で行動している限り、一部の悪意ある参加者が存在してもシステム全体の安全性は保たれます。
改めて契約の歴史を振り返ると、人類史における信頼の進化を俯瞰すると、血縁・地縁に基づく「人格的信頼」から、制度・権威に基づく「制度的信頼」を経て、アルゴリズム・暗号に基づく「数学的信頼」への移行が進んでいることがわかります。
ブロックチェーンによるスマートコントラクトは人類における契約の新しい在り方へなっていくかもしれません。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
🗓️イベント情報
8/27(水)18:30から、ソニー品川本社で「IP×ブロックチェーン」に関するWebXサイドイベントを開催します。ご興味ある方はぜひお申し込みください!
8/24(日)18:00から、「LINE Mini Dapp」に関するイベントのメディアパートナーとなりました。気になる方はぜひ以下よりご確認ください!
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら