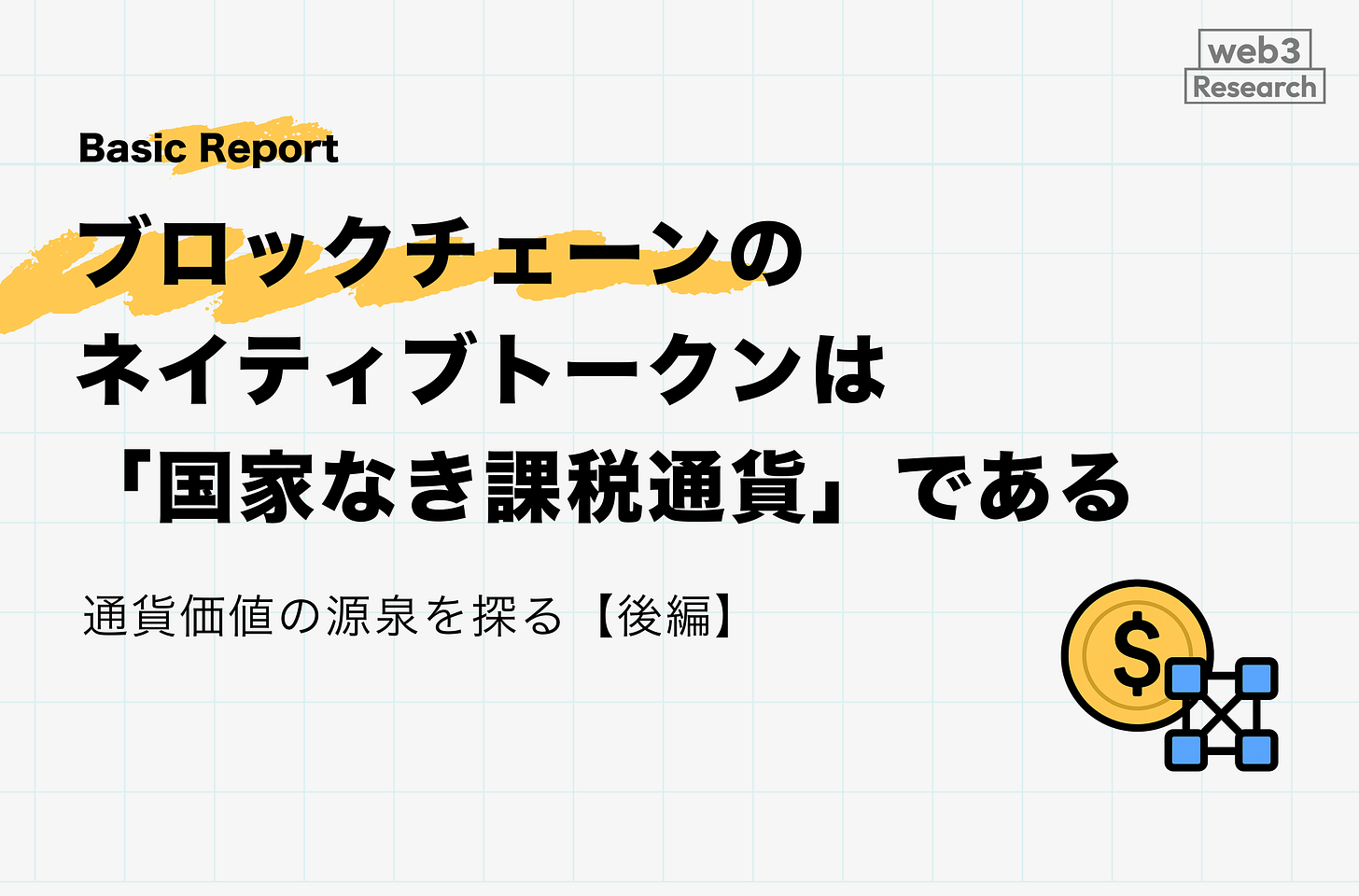おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日のお昼にはweb3の基礎の基礎レポートを更新しています。今週は「租税貨幣論」について解説します。ぜひ最後までご覧ください!
前編の振り返り
ネイティブトークンとは
ガス代は課税に似ている
国家通貨とネイティブトークンの比較
価格上昇圧力のメカニズム
まとめ
前編の振り返り
前編では、租税貨幣論という理論的枠組みを通じて、法定通貨の価値がどこから来るのかを詳しく見てきました。その核心は、「通貨価値は国家による納税義務によって支えられる」という洞察でした。
政府が法律により特定の通貨での納税を義務づけることで、その通貨への強制的な需要が創出されます。この需要は個人の選好や市場心理とは無関係に、法的義務として確実に発生するため、通貨価値の安定した基盤となります。日本円の場合、年間約60兆円規模の税収が、この強制的需要の源泉となっています。
また、政府支出による通貨供給と課税による通貨回収の循環構造により、通貨価値が持続的に維持されることも確認しました。この「発行→流通→回収」のサイクルが、現代の不換紙幣システムを支える基本的なメカニズムです。
国家のないブロックチェーン経済圏では何が価値を支えるのか?
前編で理解した租税貨幣論の枠組みは、従来の国家中心の通貨システムを説明する上で非常に有効でした。しかし、21世紀に入って出現したブロックチェーンベースの経済圏は、これまでとは全く異なる特徴を持っています。
ブロックチェーン上には政府も中央銀行も存在しません。法律による納税義務もなければ、物理的な強制力もありません。それにも関わらず、イーサリアムのETH、ビットコインのBTC、ソラナのSOLといったネイティブトークンは、時として数兆円規模の価値を持つに至っています。
これは一体なぜでしょうか。国家なき経済圏で、何がこれらのトークンに価値を与えているのでしょうか。この疑問に答えるため、本記事では租税貨幣論の視点をブロックチェーン経済圏に応用し、「ネイティブトークンは国家なき課税通貨である」という仮説を詳しく検証していきます。
結論を先に解説しておくと、ブロックチェーンのネイティブトークンは、ガス代という形の「課税」によって強制的需要が創出されており、これが租税貨幣論における納税義務と本質的に同じ機能を果たしていると言えます。
ネイティブトークンとは
まずはブロックチェーンのネイティブトークンについて、その定義と機能を明確にしておきます。ネイティブトークンの理解は、後の「課税」との類似性を理解する上で不可欠です。
定義と基本的役割
ネイティブトークンとは、特定のブロックチェーンネットワークにおいて、プロトコルレベルで組み込まれた基本通貨を指します。これは、そのブロックチェーンの「原住民通貨」とも言える存在で、ネットワークの基本的な機能と密接に結びついています。
技術的な位置づけ
ネイティブトークンは、ブロックチェーンのコンセンサスメカニズムと直接的に連携しています。例えば、イーサリアムのETHは、イーサリアムブロックチェーンのプロトコル自体に組み込まれており、ネットワークの基本機能を利用する際に必ず関与する設計になっています。
これは、ERC-20などの規格で発行される「トークン」とは根本的に異なります。ERC-20トークンはイーサリアム上で動作するアプリケーションにより発行される二次的な通貨ですが、ETH自体はイーサリアムネットワークそのものと一体不可分の存在です。
主要な機能領域
ネイティブトークンは、一般的に以下の機能を担っています。
ガス代(取引手数料)の支払い ブロックチェーン上で取引を実行する際に必要な手数料を、ネイティブトークンで支払います。これは最も基本的で重要な機能です。
バリデーター報酬 ブロック生成やトランザクション検証を行うバリデーター(マイナー)への報酬として、ネイティブトークンが支払われます。
ステーキング プルーフオブステーク方式のブロックチェーンでは、ネイティブトークンをステーキングすることで、ネットワークのセキュリティ維持に参加できます。
ガバナンス 一部のブロックチェーンでは、ネイティブトークンの保有量に応じてプロトコルの変更提案や投票に参加できます。
主要なネイティブトークンの例
現在活発に利用されている主要なネイティブトークンを具体的に見てみましょう。
Bitcoin(BTC)
最初の暗号資産であるビットコインは、シンプルながら強力なネイティブトークンです。ビットコインネットワークでは、すべての取引手数料がBTCで支払われ、マイナーへの報酬もBTCで支払われます。
ビットコインの特徴は、その機能が比較的限定的であることです。主に価値の保存と送金に特化しており、複雑なスマートコントラクト機能は持ちません。しかし、この単純さが逆に安定性と信頼性をもたらしています。
Ethereum(ETH)
イーサリアムのETHは、最も多機能なネイティブトークンの一つです。イーサリアム上では、シンプルな送金からDeFi、NFT取引、複雑なスマートコントラクトの実行まで、あらゆる操作にETHが必要です。
特に重要なのは、2021年に実装されたEIP-1559という仕組みです。この仕組みにより、取引手数料の一部が「バーン」されるようになり、ETHの供給量が実質的に減少する場合があります。これは後で詳しく分析する「デフレーショナリー圧力」の源泉となっています。
Solana(SOL)
ソラナのSOLは、高速・低コストな取引処理で注目を集めるネイティブトークンです。ソラナネットワークでは、取引手数料が非常に低く設定されていますが(1取引あたり約0.01円)、それでも必ずSOLでの支払いが必要です。
ガス代は課税に似ている
ネイティブトークンの最も基本的な機能である「ガス代支払い」は、租税貨幣論における「納税義務」と類似した特徴を持っています。
強制的な支払い義務
まず、ガス代支払いの「強制性」について見てみましょう。ブロックチェーン上で何らかの操作を行いたい場合、ガス代の支払いは完全に避けることができません。
取引実行の絶対的前提条件
イーサリアム上でERC-20トークンを送金したい場合を考えてみましょう。送金者がどれだけ多くのUSDCやDAIを保有していても、ETHを保有していなければ送金は実行できません。ガス代としてETHを支払うことが、取引実行の絶対的前提条件となっているからです。
これは、日本国内で所得税を支払う際に、どれだけ多くの米ドルや金を保有していても、最終的には日本円に交換して納税する必要があることと同じ構造です。選択の余地がない「強制性」が、両者に共通する特徴なのです。
回避不可能性
さらに重要なのは、この支払い義務が完全に回避不可能であることです。イーサリアム上でDeFiプロトコルを利用したり、NFTを取引したりする場合、どのような高度な技術を使用しても、ETHでのガス代支払いを回避することはできません。
これは技術的制約ではなく、プロトコルレベルでの設計です。イーサリアムのコンセンサスメカニズムは、すべての状態変更にガス代の支払いを要求し、そのガス代はETHでなければ受け付けません。
需要の必然性
この強制性により、イーサリアムネットワークの利用者は必然的にETHを保有することになります。DeFiで年利10%の運用を行いたいトレーダーも、NFTアートを販売したいクリエイターも、Web3ゲームを楽しみたいプレイヤーも、全員がETHを取得する必要があります。
この「必要に迫られた取得」こそが、租税貨幣論における納税需要と同じメカニズムです。選択ではなく必要性に基づく需要は、非常に安定的で予測可能な特徴を持ちます。
特定トークン以外での支払い不可
ガス代支払いにおけるもう一つの重要な特徴が、「支払い手段の限定性」です。これも租税貨幣論における法定通貨の地位と同じ構造を持っています。
プロトコルレベルでの限定
イーサリアムのガス代は、ETH以外では絶対に支払えません。これは、利便性や慣習の問題ではなく、プロトコルの基本設計です。バリデーターがガス代として受け取れるのはETHのみであり、他のトークンでの支払いは技術的に不可能です。
ソラナでも同様で、どれだけ豊富なSPLトークンを保有していても、取引手数料はSOLでなければ支払えません。ビットコインネットワークでも、取引手数料の支払いはBTCに限定されています。
代替手段の排除
重要なのは、この限定が完全であることです。「通常はETHだが、緊急時には他のトークンでも可能」といった例外規定は存在しません。また、「市場レートで他のトークンと交換してガス代を支払う」といった自動的な仕組みも、基本的には提供されていません。
この排他性により、ネイティブトークンは各ブロックチェーン経済圏における「法定通貨」としての地位を確立しています。法律ではなく、プロトコルによって「法定」されているのです。
セキュリティとスパム防止機能
ガス代システムは、単なる課金メカニズムではありません。ネットワークのセキュリティ維持とスパム防止という重要な機能も担っています。この点でも、租税制度との類似性が見られます。
計算資源の有限性
ブロックチェーンネットワークの計算資源は有限です。すべてのバリデーターが同じ計算を実行する必要があるため、無制限の取引を処理することはできません。ガス代システムは、この有限な資源を適切に配分するための市場メカニズムとして機能します。
高いガス代を支払う意思のあるユーザーの取引が優先的に処理され、低いガス代しか支払わない取引は後回しにされるか、場合によっては処理されません。これにより、ネットワーク資源の効率的な利用が実現されます。
スパム攻撃の防止
ガス代が存在しなければ、悪意のあるユーザーが大量の無意味な取引を送信し、ネットワークを麻痺させることが可能になります。ガス代システムにより、そのような攻撃には相応のコストが必要となり、経済的に割に合わなくなります。
これは、租税制度が公共サービスの維持費用を調達するだけでなく、社会の安定性維持にも寄与することと類似しています。課税により、社会参加にはある程度のコスト負担が必要であることを明確にし、フリーライダーの問題を抑制します。
国家通貨とネイティブトークンの比較
ここまでの分析を踏まえ、国家通貨とブロックチェーンのネイティブトークンを体系的に比較してみましょう。両者の共通点と相違点を明確にすることで、「国家なき課税通貨」という概念の妥当性を検証できます。
共通点:強制的需要
最も重要な共通点は、両者とも「強制的需要」によって価値が支えられていることです。
法的義務 vs プロトコル義務
国家通貨の場合、法律による納税義務が強制的需要を創出します。憲法と税法により、納税者は特定の通貨での納税を義務づけられ、この義務に従わなければ法的制裁を受けます。
ネイティブトークンの場合、プロトコルによるガス代支払い義務が強制的需要を創出します。ブロックチェーンのコンセンサスルールにより、利用者は特定のトークンでのガス代支払いを義務づけられ、この義務に従わなければ取引が実行されません。
義務の普遍性
両者とも、該当する経済圏に参加するすべての主体に義務が課されます。日本円の場合、日本国内で経済活動を行うすべての個人・法人に納税義務が発生します。ETHの場合、イーサリアムネットワークを利用するすべてのユーザーにガス代支払い義務が発生します。
義務の継続性
また、両者とも一回限りの義務ではなく、継続的な義務です。税金は毎年発生し、ガス代は取引のたびに発生します。この継続性が、安定した通貨需要の基盤となります。
違い:発行権限、供給ルール、信頼の基盤
一方で、両者には重要な違いも存在します。これらの違いが、それぞれの通貨システムの特徴を決定づけています。
発行権限の所在
国家通貨の発行権限は、政府と中央銀行が握っています。日本円の場合、日本政府と日本銀行が共同で通貨供給量を決定し、必要に応じて追加発行や回収を行います。この権限は、政治的プロセスを通じて行使されます。
ネイティブトークンの発行権限は、プロトコルのルールによって規定されます。ビットコインの場合、発行スケジュールは予めプログラムされており、人為的な変更は極めて困難です。イーサリアムの場合も、発行量の変更にはコミュニティの合意とハードフォークが必要です。
供給ルールの透明性
国家通貨の供給ルールは、政策判断によって変更されることがあります。金融危機時の量的緩和や緊急時の財政支出など、状況に応じて柔軟な対応が可能ですが、将来の供給量は不確実です。
ネイティブトークンの供給ルールは、多くの場合、予めコードで規定されており、透明性が高いです。ビットコインの2100万枚上限や半減期スケジュール、イーサリアムのEIP-1559によるバーンメカニズムなど、将来の供給量がある程度予測可能です。
信頼の基盤
国家通貨の信頼は、政府の統治能力、経済力、政治的安定性などに基づいています。これらの要因は複雑で、時として急激に変化する可能性があります。
ネイティブトークンの信頼は、プロトコルの技術的堅牢性、コミュニティの合意、ネットワーク効果などに基づいています。これらの要因も変化しますが、技術的特性により一定の予測可能性があります。
価格上昇圧力のメカニズム
ネイティブトークンが「国家なき課税通貨」として機能することを理解した上で、なぜこれらのトークンに価格上昇圧力が生まれるのかを分析してみましょう。法定通貨との比較も交えながら、価格形成の独特なメカニズムを解明します。
利用増加による需要拡大
ネイティブトークンの価格上昇圧力の最も基本的な要因は、ブロックチェーンネットワークの利用増加による需要拡大です。
ブロックチェーンネットワークは、典型的なネットワーク効果を示します。利用者が増えるほど、そのネットワークの価値が向上し、さらに多くの利用者を惹きつけます。イーサリアムの場合、DeFiプロトコルの数が増えると、それらを利用したいユーザーが増加し、結果的にETHの需要が拡大します。
この循環は自己強化的な特性を持ちます。ネットワークの価値向上→利用者増加→ガス代需要増加→トークン価格上昇→ネットワークの魅力度向上、という正のフィードバックループが形成されます。
供給制限(バーン、半減期)
需要拡大と並んで重要なのが、供給サイドの制限メカニズムです。多くのネイティブトークンには、供給量を制限する仕組みが組み込まれており、これが価格上昇圧力を生み出します。
ビットコインの半減期メカニズム
ビットコインの半減期は、最もよく知られた供給制限メカニズムです。約4年ごとに、マイナーへの報酬が半分になるため、新規供給量が段階的に減少します。
2020年の第3回半減期以降、ビットコインの年間供給増加率は1.8%まで低下し、金の年間供給増加率(約2%)を下回りました。この供給制限により、需要が一定でも価格上昇圧力が生まれます。
さらに、ビットコインの総供給量は2100万枚に限定されており、2140年頃には新規発行が完全に停止します。この絶対的な希少性が、長期的な価格上昇期待を支えています。
イーサリアムのバーンメカニズム
イーサリアムは2021年のEIP-1559実装により、全く新しい供給制限メカニズムを導入しました。取引手数料の一部(ベースフィー)が永続的に「バーン」されるようになったのです。
このメカニズムにより、ネットワーク利用が活発な時期には、ETHの供給量が実質的に減少します。2022年9月にプルーフオブステークに移行して以降、ETHの年間供給増加率は大幅に低下し、時期によってはデフレーション(供給減少)状態になっています。
ステーキングによる流通減
プルーフオブステーク型のブロックチェーンでは、ステーキングが流通量減少の大きな要因となっています。
ソラナではSOLの約70%、カルダノではADAの約75%がステーキングに参加しており、実際に取引可能なトークンは総供給量の3分の1以下となっています。
この大幅な流通量減少により、同じ需要水準でも価格上昇圧力が強くなります。経済学の基本原理に従い、供給量の減少は価格上昇をもたらします。
投資需要
最後に、純粋な投資対象としての需要も、価格形成において重要な役割を果たしています。
デジタルゴールドとしてのビットコイン
ビットコインは「デジタルゴールド」として、価値保存手段への投資需要を集めています。限定的な供給量、非中央集権的な特性、政治的影響の受けにくさなどが、この需要を支えています。
機関投資家の参入
2020年以降、機関投資家の暗号資産への参入が本格化しました。マイクロストラテジー、テスラ、エルサルバドル政府などがビットコインを準備資産として採用し、大きな価格インパクトを与えました。
機関投資家の投資は、個人投資家とは異なる特徴を持ちます。長期保有を前提とし、大きなロットでの購入を行うため、供給量に対する影響が大きくなります。
まとめ
ブロックチェーンのネイティブトークンは、租税貨幣論の枠組みでその価値を理解できる通貨システムであることを解説してきました。
共通点
強制的需要の創出
国家通貨が納税義務によって強制的需要を創出するように、ネイティブトークンはガス代支払い義務によって強制的需要を創出します。この需要は、利用者の選好とは無関係に、ネットワーク利用のための絶対的必要性として発生します。
支払い手段の限定
国家通貨が法律により納税手段として限定されるように、ネイティブトークンはプロトコルによりガス代支払い手段として限定されます。この排他性により、各ブロックチェーン経済圏における「法定通貨」としての地位が確立されます。
循環構造の存在
国家通貨が政府支出→経済流通→納税回収の循環を持つように、ネイティブトークンもバリデーター報酬→経済流通→ガス代回収の循環を持ちます。この循環により、持続的な通貨システムが実現されています。
最大の違い:政治的恣意 vs コード化されたルール
国家通貨とネイティブトークンの最も重要な違いは、ルール変更のメカニズムにあります。
政治的判断 vs 技術的実装
国家通貨の場合、税率変更、通貨発行量調整、制度変更などは政治的判断により行われます。これらの判断は、選挙結果、経済状況、国際情勢など様々な要因に影響され、時として短期的な政治的利益が長期的な経済合理性を上回ることがあります。
ネイティブトークンの場合、基本的なルールはコードで実装され、変更にはコミュニティの技術的合意が必要です。政治的な思惑よりも、技術的合理性と経済的インセンティブが重視される傾向があります。
透明性と予測可能性
国家通貨の政策変更は、しばしば事前の十分な説明なしに実施されます。量的緩和、金利変更、緊急時の特別措置など、市場参加者にとって予測困難な変更が頻繁に発生します。
ネイティブトークンの仕様変更は、通常、長期間の議論とテストを経て実施されます。また、コードがオープンソースであるため、将来の変更可能性も含めて透明性が高く保たれています。
展望
「国家なき課税通貨」としてのネイティブトークンの概念は、通貨システムの新しい可能性を示しています。政治的影響を受けにくく、透明性が高く、予測可能なルールに基づく通貨システムは、従来の法定通貨システムの問題点を補完する存在として機能する可能性があります。
ただし、これらのシステムも完璧ではありません。技術的リスク、スケーラビリティの問題、規制リスクなど、様々な課題が存在します。最終的には、法定通貨システムとブロックチェーンベースの通貨システムが共存し、それぞれの特徴を活かした使い分けが行われる未来が予想されます。
重要なのは、租税貨幣論という理論的枠組みを通じて、これらの新しい通貨システムの本質を理解し、適切に評価することです。通貨価値の源泉は、最終的には「強制的需要」にあり、それが国家による課税であれ、プロトコルによるガス代であれ、基本的なメカニズムは共通しています。
法定通貨もネイティブトークンもこれが全てではありませんが、租税貨幣論という考え方がその価値の裏付けとなっている可能性は大いにあります。前編と後編を通して、その理解の参考になれば幸いです。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
✨有料購読特典
月額10ドル(年額80ドル/月額6.6ドル)で有料購読プランを用意しています。有料購読いただいている方には以下の特典がございます。
週2本の限定記事の閲覧
月曜:1週間のマーケット&ニュースまとめ記事(国内外の20以上メディアから1週間のニュースをキュレーションして紹介)
木曜:Deep Report記事(通常の内容よりも深い調査や考察を盛り込んだ記事 / 公開記事では言えない裏事情も偶に公開)
1,500本以上の過去記事の閲覧
無料で公開された記事も公開1週間後以降は有料購読者以外は閲覧できなくなります。すでに1,500本以上の過去記事が存在し、その全てを見放題です。
不定期のオフ会への参加
オフライン/オンラインにて不定期で有料購読者限定のオフ会を開催します。
※特典は現時点のものであり今後変更の可能性がございます。変更の際はニュースレターでお知らせします。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら