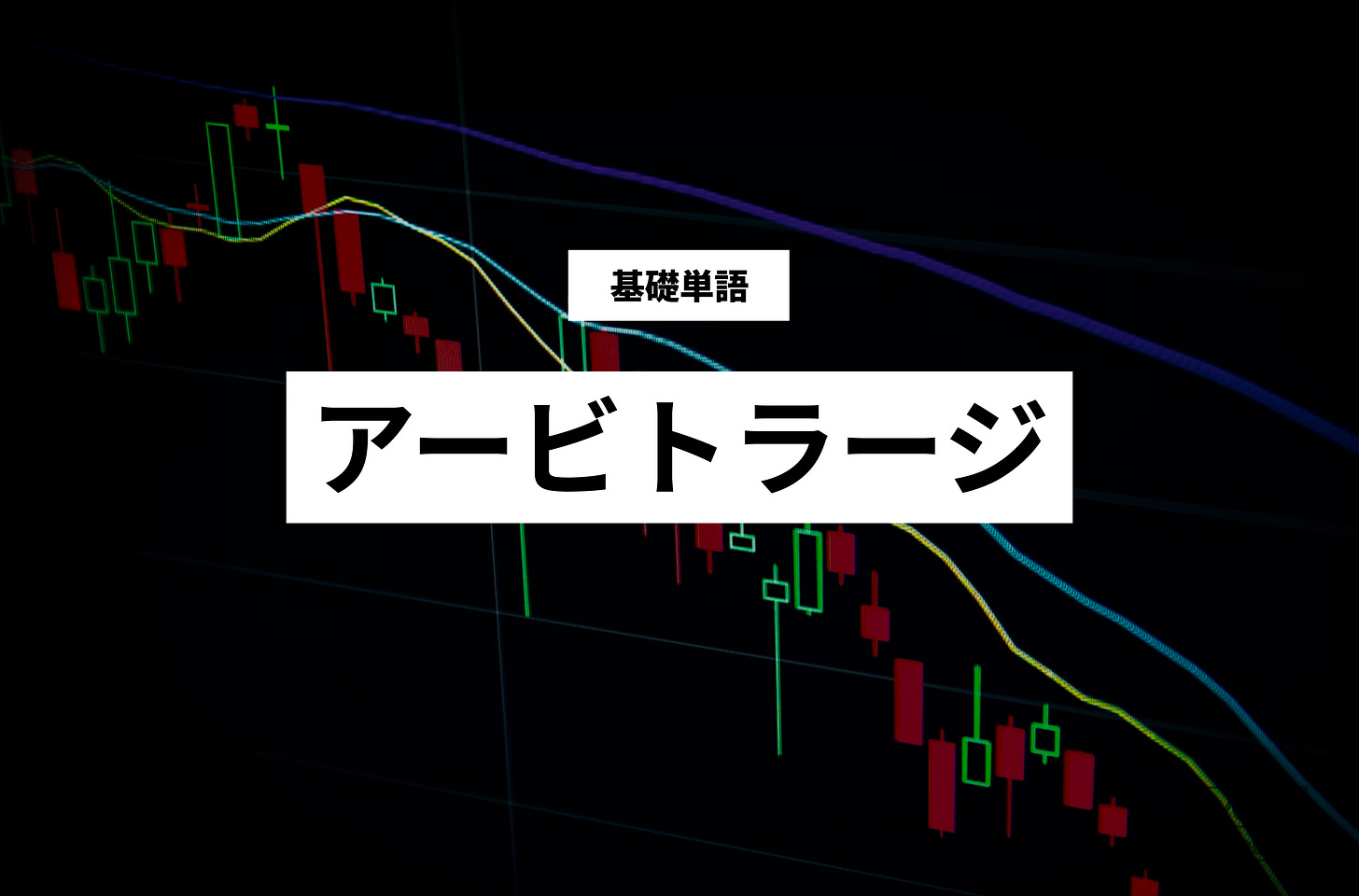おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
毎週土日の昼にはweb3の基礎レポートをお送りしていましたが、少し派生して1つ1つの「単語」解説記事を更新してみます。各記事をサクッと読めるような文量にして、改めて振り返れる、また勉強できるような記事を目指していきます。
本日は「アービトラージ」です。
ぜひ最後までご覧ください!
導入:市場の歪みを修正する「見えない調整役」
「アービトラージ(Arbitrage)=裁定取引」は、一見すると、抜け目ないトレーダーによる単なる利益追求活動のように思えるかもしれません。しかし、アービトラージは市場全体の価格を均一に保ち、効率的な状態へと導く非常に重要な役割を担っています。
特にweb3の世界、とりわけAMM型のDEXにおいては、アービトラージは価格の歪みを自動的に修正する「調整役」として機能しています。
中央管理者が価格を決定しないDEXにおいて、なぜその価格がBinanceやCoinbaseといった中央集権型取引所(CEX)の価格と常に近い水準に保たれているのでしょうか? その答えが、アービトラージの存在にあります。この記事では、市場を整えるアービトラージの仕組みとその意義について解説します。
裁定取引の原理:価格差が利益を生み、市場を均衡させる
アービトラージ(裁定取引)の定義は、「同一の資産が、異なる市場で異なる価格を持つとき、その価格差を利用してリスクなく利益を得る行為」です。
具体的な例で考えてみましょう。
市場A(例:Binance)でのETH価格 = 2,000ドル
市場B(例:Uniswap)でのETH価格 = 2,020ドル
この状況を発見したトレーダー(アービトラージャー)は、次のような行動をとります。
価格の安い市場Aで、1ETHを2,000ドルで購入する。
同時に(あるいは直後に)、価格の高い市場Bで、1ETHを2,020ドルで売却する。
これにより、トレーダーは1ETHあたり20ドルの差益を得ることができます。
重要なのは、この取引が市場価格に与える影響です。
市場AではETHの買い注文が入るため、価格は上昇圧力(2,000ドル→)を受けます。
市場BではETHの売り注文が入るため、価格は下落圧力(→2,020ドル)を受けます。
アービトラージャーたちが利益を求めてこの取引を繰り返すことで、市場Aと市場Bの価格差は急速に縮まり、最終的には両市場の価格がほぼ同じ水準(例:2,010ドル)で均衡することになります。
このように、アービトラージは個々のトレーダーの利益追求活動でありながら、結果として全ての市場間の価格を自動的に整合させ、市場全体の効率性を高める機能を持っているのです。
AMMにおけるアービトラージ:価格の「遅れ」を修正するBotたち
AMMは、その価格決定メカニズムの特性上、アービトラージの機会を常に提供しています。「x*y=k」モデルでは、プールの価格は外部市場の動向とは独立して、プール内の資産比率によってのみ決定されます。そのため、市場全体の変動に対して、AMMの価格反応は少し遅れることになります。
例えば、あるニュースによって市場全体でETHの価格が急騰したとします。CEXでは即座に価格が反応しますが、AMMのプール価格は、誰かがそのプールで取引を行わない限り変化しません。
この「遅れ」を解消するのが、アービトラージャー(多くの場合、自動化されたBot)です。
具体例を見てみましょう。
市場全体のETH価格(CEX):2,000ドル
UniswapのETH/USDCプール価格:1,950ドル(市場変動に遅れている状態)
Botは即座にこれを検知し、UniswapでETHを買い、USDCを支払います。BotがUniswapでETHを買うと、プール内のETH量が減少し、USDC量が増加します。これにより、「x*y=k」のバランスが変化し、Uniswap上のETH価格は上昇します。Botは、Uniswapの価格が市場価格である2,000ドルに一致するまで、この取引を継続します。
このプロセスにより、DEXの価格は外部市場の価格に追随し、常に「正しい価格」へと自動的に修正されるのです。
しかし、このメカニズムは流動性供給者(LP)にとっては複雑な影響をもたらします。LPは、アービトラージャーが市場の歪みを修正する過程で、割安になった資産を放出し、割高になった資産を取得することになります。
これは、価格変動がなければ保有し続けていたであろう資産ポートフォリオと比較して損失を生む可能性があり、これが「インパーマネントロス(変動損失)」の本質的な原因の一つです。つまり、アービトラージャーの利益は、LPが支払ったコストによって賄われている側面があるのです。
MEVとアービトラージの境界線
アービトラージが市場の健全な調整機能である一方で、その実行プロセスにおいては倫理的・技術的な課題も存在します。その代表例がMEV(Maximal Extractable Value)です。
アービトラージは、価格差を誰よりも早く見つけ、取引を実行することで成立します。ブロックチェーン上では、トランザクションの順序を決定する権限はブロック生成者(マイナーまたはバリデーター)にあります。
MEVは、この権限を利用して、ブロック生成者自身や、彼らと協力する専門のBot(サーチャー)が、アービトラージの機会を“横取り”したり、他のユーザーの取引を利用して不正な利益を得たりする行為を指します。
例えば、あるBotが大規模なアービトラージ機会を発見し、トランザクションを送信したとします。ブロック生成者はそのトランザクションを見て、自分自身で同じ取引を行うトランザクションを作成し、元のBotの取引よりも先に(フロントラン)挿入することができます。また、前回の記事で解説した「サンドイッチ攻撃」も、他者の取引を利用して人為的にアービトラージの機会を作り出すMEVの一種です。
こうした敵対的なMEVは、市場の公平性を脅かす深刻な問題となっています。この問題に対処するため、web3コミュニティでは「フェアなアービトラージ」を実現するための様々な試みがなされています。
例えば、Flashbotsは、サーチャーとマイナーが透明性の高いオークションを通じてMEVを抽出する仕組みを提供しています。また、CowSwapのようなDEXアグリゲーターは、MEVの影響を最小限に抑える設計を採用しています。
アービトラージは「市場を正す自動調整機構」ですが、その設計次第で善にも悪にもなり得るという二面性を持っています。
アービトラージの社会的意義:分散市場の「見えない調整役」
web3の市場は常に分散しており、全ての取引情報を集約した「完全な統一板」は存在しません。無数のDEX、CEX、そして異なるブロックチェーン上に市場が散らばっているのが現状です。
こうした分散化された環境において、アービトラージは市場と市場をつなぎ合わせ、価格を平準化する「見えない調整役」として機能します。もしアービトラージが存在しなければ、同じ資産であっても取引所ごとに全く異なる価格がつき、市場は混乱してしまうでしょう。
これは、従来の中央集権型取引所において「マーケットメイカー」と呼ばれる専門業者が担っていた役割(流動性を提供し価格を安定させる)を、アルゴリズムと経済的インセンティブによって自動化したものと捉えることができます。分散市場が効率的に機能するために、アービトラージは不可欠な要素なのです。
まとめ
アービトラージ(裁定取引)は、市場の歪みを利用して利益を得ると同時に、その歪みを修正する自律的なメカニズムです。
前回の記事で解説した「スリッページ」が、AMMにおける流動性の限界による「歪みの発生」であるとするならば、「アービトラージ」は外部市場との比較による「歪みの修正」と言えます。
この「歪みの発生」と「歪みの修正」という2つの概念を理解することによって、中央管理者のいないweb3の市場が、なぜ秩序を保ち、効率的な価格形成を実現できているのか、その全体像が見えてくるでしょう。
免責事項:リサーチした情報を精査して書いていますが、個人運営&ソースが英語の部分も多いので、意訳したり、一部誤った情報がある場合があります。ご了承ください。また、記事中にDapps、NFT、トークンを紹介することがありますが、勧誘目的は一切ありません。全て自己責任で購入、ご利用ください。
About us:「web3 for everyone」をコンセプトに、web3の注目トレンドやプロジェクトの解説、最新ニュース紹介などのリサーチ記事を毎日配信しています。
Author:mitsui @web3リサーチャー
「web3 Research」を運営し、web3リサーチャーとして活動。
Contact:法人向けのリサーチコンテンツの納品や共同制作、リサーチ力を武器にしたweb3コンサルティングや勉強会なども受付中です。詳しくは以下の窓口よりお気軽にお問い合わせください。(📩 X / HP)
→お問い合わせ先はこちら