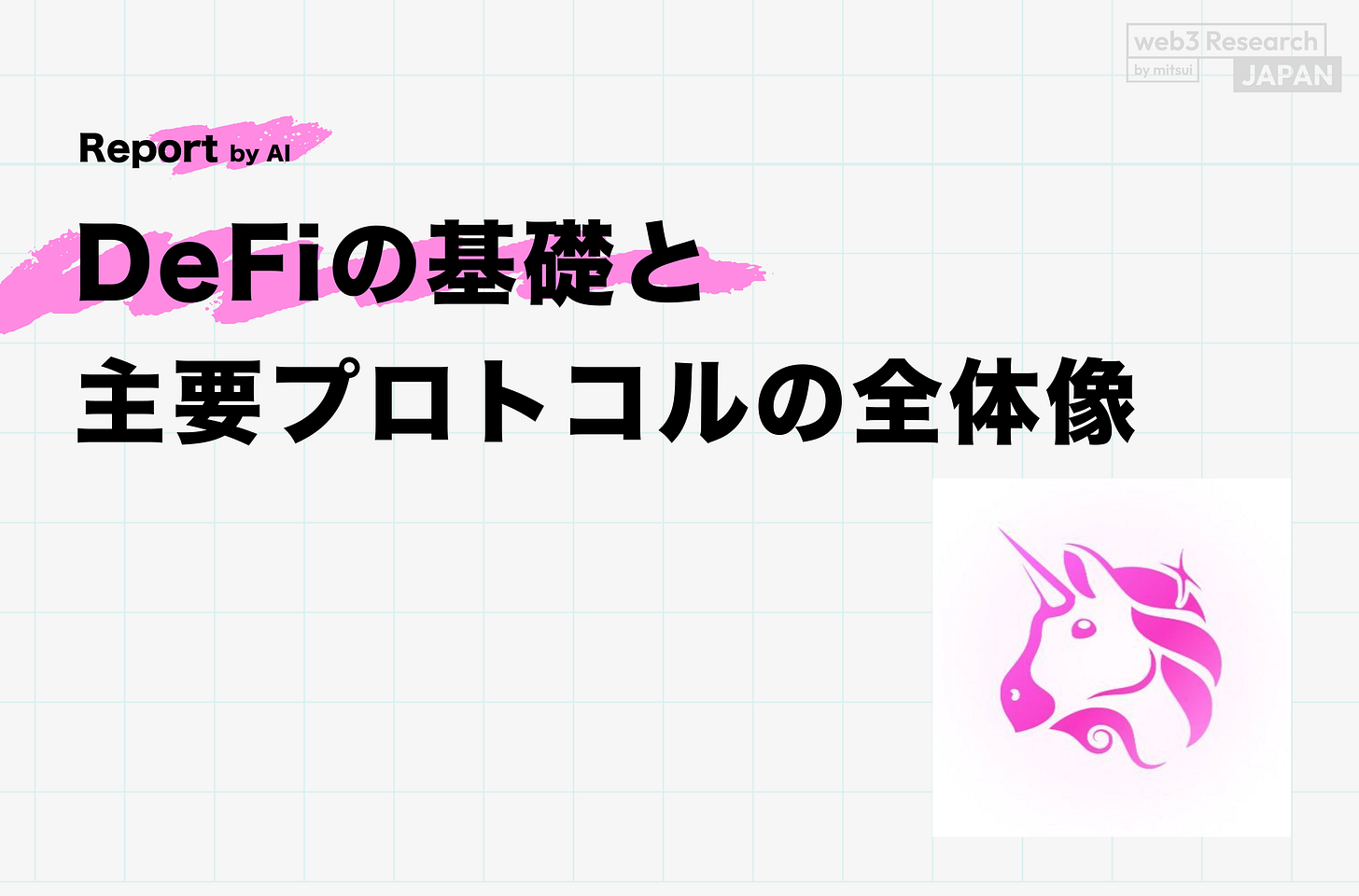おはようございます。
web3リサーチャーのmitsuiです。
先週から始まりましたが、土日のお昼はAIによるレポートを更新します。
普段は最新のトレンドや注目プロジェクトを紹介していますが、ここでは過去からの歴史を振り返る系の記事を投稿していきます。レビューはしていますが、一部内容に間違いがあるかもしれませんので、ご了承ください。
それではどうぞ!
第1章:はじめに──DeFiとは何か
第2章:DeFiの歴史と進化のタイムライン
第3章:主要プロトコルの徹底解説
第4章:DeFiのメリットと社会的インパクト
第5章:DeFiにおけるリスク要因
第6章:前編のまとめ・後編への導入
第1章:はじめに──DeFiとは何か
1-1. DeFiという言葉の背景
「DeFi(Decentralized Finance)」とは、中央管理者を介さずに金融サービスを実現しようとする概念・仕組みの総称です。従来、銀行や証券会社、取引所などの中央管理者を通して行われていた貸付・取引・保管などの業務を、スマートコントラクトと呼ばれるプログラムを使い、ブロックチェーン上で自動化・分散化することで実装します。
「web3」という言葉が指し示す“分散型インターネット”の文脈において、金融分野はとりわけ大きなインパクトを受けています。データや資産をユーザーが自らコントロールし、仲介業者なしにやり取りできる──そんな新しい金融の姿がDeFiの目指すところです。
1-2. CeFiとの比較
これまでの暗号資産の世界でも「中央集権型金融サービス(CeFi)」は存在してきました。たとえば暗号資産取引所がユーザーの資産を預かり、取引手数料を取るビジネスモデルです。これらはユーザー体験が比較的わかりやすく利便性も高い反面、取引所がハッキングされるリスクや資金凍結リスクなど、中央管理者に頼る構造ゆえの問題を抱えていました。
DeFiは、こうした中央管理者を取り除き、ユーザーが**「自分のウォレット」で資産を保有しながら金融サービスを利用する**というモデルを打ち立てる点で大きく異なります。ブロックチェーン上のスマートコントラクトを通じて、ユーザー同士が直接貸し借りをしたり、取引できるようになるのです。
第2章:DeFiの歴史と進化のタイムライン
2-1. 初期の分散型取引所(DEX)
DeFiという言葉こそまだ一般的ではなかったものの、ブロックチェーン上で非中央集権的に資産を交換する試みは早くから存在していました。代表例としてEtherDelta(2017年頃に活発化)が挙げられます。
EtherDeltaはイーサリアム上に構築された分散型取引所で、ユーザーは秘密鍵を自分で管理しながらERC-20トークンの取引が可能でした。
ただしUI/UXが非常に使いづらく、また注文板(オーダーブック)をスマートコントラクト上に実装する仕組みはガス代がかさむなどの課題があり、主流にはなれませんでした。
2-2. DeFi Summer(2020年頃)の爆発的成長
「DeFi」という言葉が一躍脚光を浴びたのは、2020年の夏(通称:DeFi Summer)です。この頃、UniswapやCompound、Aaveといったプロトコルがユーザーに「流動性マイニング報酬(Liquidity Mining)」を提供し始めました。
例:UniswapのLP(Liquidity Provider)になると、独自のトークンUNIが配布される。
これによって参加者が大量の資金をプロトコルに預け、資金量(TVL:Total Value Locked)が爆発的に増加したのです。
DeFi Summerでは、年利が100%を超えるような極端なリターン事例も多く、投機的な資金が殺到しました。一方で、過剰な期待と不十分なリスク管理によってハッキングやrug pull(開発者が資金を持ち逃げする行為)なども相次ぎ、DeFiの光と影がともに認識された時期でもあります。
第3章:主要プロトコルの徹底解説
3-1. Uniswap:分散型取引所の代名詞
Uniswapは「AMM(Automated Market Maker)」という仕組みを広く普及させた分散型取引所の代表例です。
従来のオーダーブック方式とは異なり、トークンAとトークンBのプールを用意し、価格はプールの残高比率によって決まります。
流動性提供者(LP)はプールに資産を預けることで取引手数料の一部を報酬として得る仕組みです。
AMMモデルの斬新さとシンプルさから爆発的に利用者が増え、Uniswapの成功が「DEX=使いにくい」というイメージを大きく変えました。
AMMの数学的原理:x * y = k
Uniswap V2では、プール内のトークン量を x(トークンA) と y(トークンB) とした場合、
x×y=k
という一定値(k)を保つようにトレードが実行されます。価格はプール内の残高比に応じて動的に決まるため、使用者はオーダーブックに注文を出す必要がなく、即時スワップが可能になります。
課題:インパーマネントロス
一方で、流動性提供者には「インパーマネントロス(IL)」というリスクがあります。プール内で片方のトークン価格が大きく上がった場合、プール全体のトークン比率が変わり、単純にトークンをホールドしていた場合と比べて最終的な価値が少なくなる可能性があるのです。このリスクをどう評価し、手数料収入で補うかがLPの腕の見せどころでもあります。